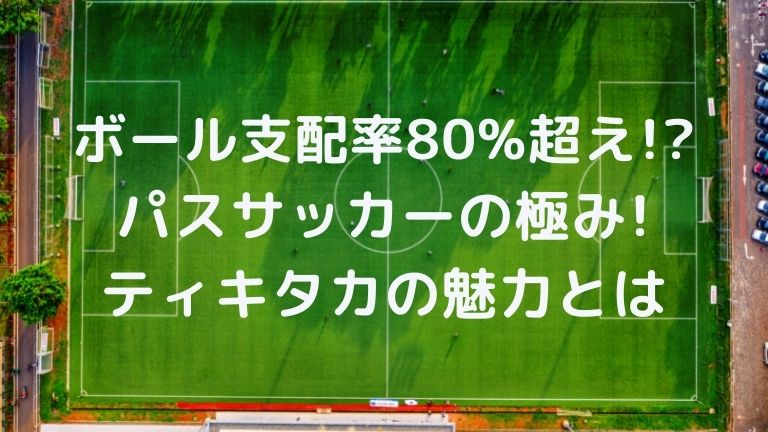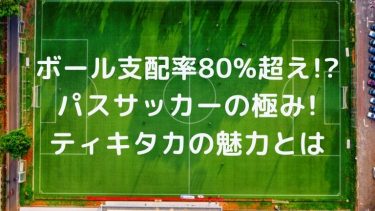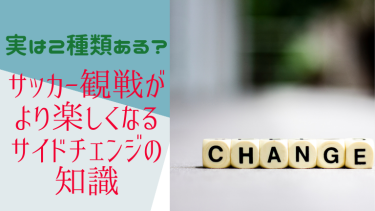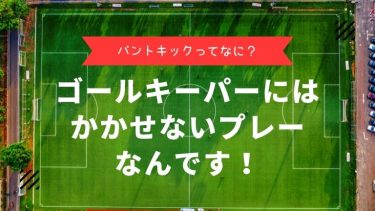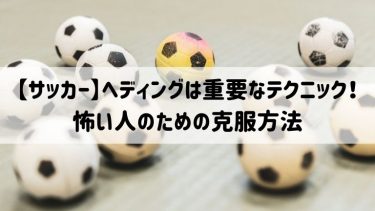ティキタカとは、サッカーのスペイン代表やFCバルセロナ(以下バルサ)が得意とした、少ないタッチ数で短いパスを連続させる攻撃スタイルです。
まるで時計の秒針のように、小気味よいリズムを刻むためそう呼ばれています。
(「チク・タク」の音を、スペイン語では「ティキ・タカ」と表現します)
今回の記事では、サッカー界に一大旋風を巻き起こしたティキタカの魅力をお伝えします。
ティキタカの誕生

実況中に生まれた言葉
ティキタカという言葉を最初に公の場で使用したのは、2006年のワールドカップドイツ大会において、実況を担当したスペイン人のアンドレス・モンテスです。
グループステージのスペイン対チュニジア戦で、スペインのパスが何本も優雅につながるのを見てモンテスは、「ティキ・タカ、ティキ・タカ!」と表現しました。
プレースタイルの起源
実際は2006年よりかなり前から、ショートパスを主体に戦う戦術はスペインに存在しています。
その起源とされるのが、80年代後半からバルサで指揮を取ったオランダ人ヨハン・クライフです。
その後、バルサの中心選手だったペップ・グアルディオラが、2008~2012年に監督としてバルサ流のティキタカを体系化。
世界的なトレンドに押し上げました。
ティキタカの特徴

圧倒的なボール支配率
ボール保持者を複数の味方が近距離でサポートし、トライアングルを形成。
パスコースをいくつも作るのがティキタカの特徴です。
高度な戦術理解とスムーズな連携、そしてボールコントロールの技術を要します。
ロングボールを蹴りこみ、一発で仕留めるという発想はありません。
ギャンブルをしないため、ボール支配率はおのずと高くなります。
現にリオネル・メッシを擁した2010年前後のバルサの試合では、支配率80%以上という試合がいくつもありました。
瞬間的な攻守の切り替え
ティキタカは、守備においても強みを発揮します。
敵にボールを奪われたとしても、多くの味方プレーヤーが近くにいるため、すぐに集団でプレスをかけることができるからです。
つまりパスを受けるためのポジションが、ボールを失った瞬間から守備陣形として使えるのが魅力。
ティキタカにおける攻撃と守備は一体で、のちのハイプレス戦術へとつながります。
ティキタカの欠点

カウンターに脆い
攻守に強みを持つティキタカですが、さりとて無敵ではありません。
選手間の距離を短く保つためには、高いディフェンスラインが絶対条件。
つまり、最後列の守備ラインと味方GKの間に広大なスペースができてしまうのです。
そのためボールロストしたあと、高い位置での集団プレスをかいくぐられたら大ピンチ。
最後尾にいる守備者の後ろを、カウンターで突かれてしまうからです。
攻撃に時間がかかる
ティキタカは、シュートまで時間がかかるのもデメリット。ディフェンダーはもちろん、キーパーですらめったにロングキックをしません。
最後尾から丁寧にボールをつなぎ、ビルドアップしていきます。そのぶん敵に余裕を与え、陣形を整えられてしまうのです。
また、固められた守備を崩すには、技術・戦術眼・献身性が備わったハイレベルな選手を揃える必要があり、
どのチームもがティキタカを採用できるわけではありません。
ティキタカで成功したチーム

FCバルセロナ
2008~2012年にバルサの監督としてチームを統率したペップ・グアルディオラは、ティキタカを高レベルで実現できた指導者です。
メッシ、シャビ、イニエスタ、ブスケツ、ビジャなど、技術と機動力をあわせ持つ選手たちに恵まれたことが最大の理由と考えられます。
かつて、80年代後半から90年代の初頭のバルサは、各国の代表選手をずらりと揃え「ドリームチーム」と呼ばれていました。
そこで中盤のコンダクターとしてタクトを振るっていたのが、スペイン人のグアルディオラです。
引退後には戦術家として才能を開花させ、2008年にバルサの監督に就任するやいなや、コパデルレイ、UEFAチャンピオンズリーグ、スペインリーグの3冠を獲得。
2011~2012年のシーズンを最後にチームを離れますが、就任中に獲得したタイトル数は14個におよびます。
磨き上げられたティキタカ戦術によって、恩師クライフが率いたドリームチームを上回る成績を残したのです。
スペイン代表
ティキタカを武器に黄金期をむかえたグアルディオラのバルサ。
その中心選手であるシャビ、イニエスタ、ブスケツ、ビジャを主軸に据えたスペイン代表は、ボールを圧倒的に支配する内容で勝ち続けます。
2008年にユーロを制すると、2010年には悲願のワールドカップ初優勝。勢いは衰えることなく、2012年のユーロも連覇します。
スペインサッカーとティキタカが、絶頂期を迎えたのです。
2008~2012年のバルサとスペイン代表においては、能力の高い選手たちが同時代にプレーしティキタカを高次元で実践できたことが大成功の要因。
しかし、永遠に勝ち続けられる戦術はありません。どんな夢にも、終わりは訪れます。
それが、ゲーゲンプレスの大流行です。
ティキタカ時代に幕

クロップの魔法陣
ティキタカの世界制覇と時を同じく、2010~2011年シーズンにドイツのブンデスリーガでは、革新的な戦術を用いたチームが話題になっていました。
ユルゲン・クロップ監督が率いる、ドルトムントです。
クロップの看板となる戦術が、ゲーゲンプレス。「ゲーゲン」とは対立や対抗を意味するドイツ語で、英語の「バーサス」に近い使われ方をします。
つまりゲーゲンプレスとは、プレスを受けないための戦術。相手にわざとボールを持たせ、狙い時を探ります。
そして、敵が攻撃のギアを上げようと無防備になった瞬間、組織的な守備でボールを回収するのです。
いわば、クロスカウンターのような斬新な発想。奪ったあとは手数をかけず、素早くゴール前にボールを運び、スプリントに長けた選手たちを殺到させます。
仕掛けた罠にかかるまで泳がせるゲーゲンプレスは、「クロップの魔法陣」とも呼ばれる大胆不敵な戦術です。
そのため当時のドルトムントは、ボール支配率が低い試合ほど勝率が上がるという面白い結果になりました。
稀代の策士クロップは、2010~2012年のブンデスリーガを2連覇することとなります。
戦術は時代とともに
ゲーゲンプレスが世界的に認知されたのと入れ替わるように、ティキタカの影は薄くなっていきました。
ボール保持が前提のサッカーは、ゲーゲンプレスの格好の餌食となるからです。
さらにはスペイン代表の、世代交代が始まったことも拍車をかけます。
自信を深めたクロップは、2015年にイングランドプレミアリーグのリバプールの監督に就任。
戦術をさらに進化させると、チームをプレミア初優勝に導く快挙を成し遂げます。
そもそもゲーゲンプレスは、ティキタカ攻略のために編み出されました。時代をリードする戦術はいつも、王者を倒すために作られます。
「盛者必衰」の言葉にならえば、クロップとて永久にチャンピオンではいられません。
まとめ

万華鏡のように選手が配置を変え、選手間をボールが小気味よく移動するティキタカは、サッカーに芸術性を求めるスペイン人に好まれました。
戦術の合理化と選手のアスリート化が進む現代サッカーにおいて、アートのようなパス回しは、もはや必要ないのかもしれません。
しかし、観衆に幸せを感じさせ、なにより選手自身が楽しそうにプレーするティキタカは、
サッカーを愛する人々の記憶の中で、いつまでもその心地よいリズムを刻んでいます。