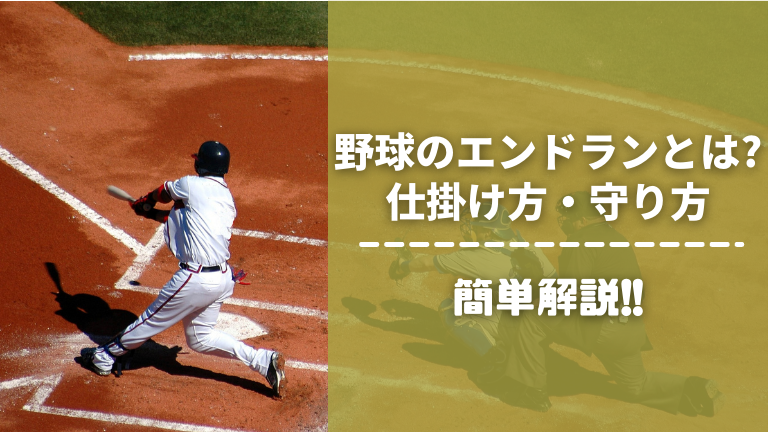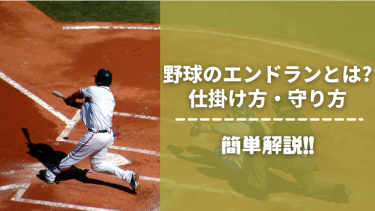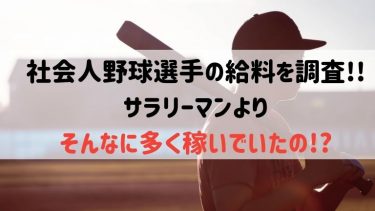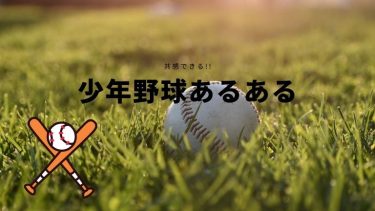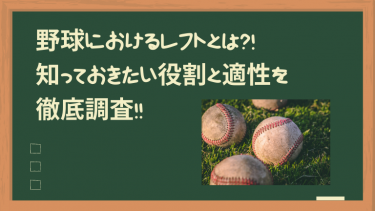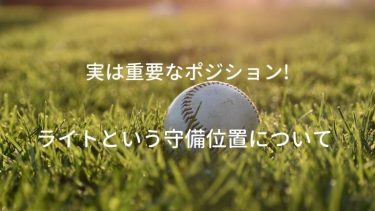野球のエンドランって、どんなものかご存知でしょうか。
野球中継を見ていると、「エンドランを仕掛けた」ということがありますが、
野球に詳しくなかったり、初心者だと、どんなものかよくわからないですよね。
この記事では、野球のエンドランについて、戦術の概要、メリット・デメリットや仕掛け方・守り方を解説します。
✅月額:3,480円 ※個別登録より「1,270円おトク」
✅「年間1万試合以上のライブ配信」のDAZNスタンダード
✅「国内作品見放題数 第2位」のDMMプレミアム
エンドランとは

「エンドラン」とは、「ヒットエンドラン」という戦術のことで、省略してエンドランと呼ばれることが多いです。
英語にすると、「hit and run」で、直訳すると「打つと走る」ということですよね。
どういう戦術かというと、
「ピッチャーが投げると同時にランナーがスタートを切り、バッターはヒッティングしてランナーの進塁を狙う」という戦術です。
ヒットになれば、ランナーが進んでバッターも残るので、大きくチャンスが広がり、大成功です。
また、仮に打球が内野ゴロになってしまっても、ダブルプレーにならずにランナーが進塁できれば最低限の成功です。
失敗例は、バッターが空振りしてしまい、ランナーが飛び出してアウトになるパターンです。
また、打球がフライやライナーになってしまうと、最悪の場合、ランナーが帰塁できず、ダブルプレーになることもあります。
このように、成功するとチャンスが拡大する戦術ですが、失敗するとチャンスをつぶしてしまうリスクのある戦術でもあります。
エンドランの種類

バントエンドラン
バッターがヒッティングする代わりに、バントをする場合が「バントエンドラン」です。
ヒットエンドランに比べてバントエンドランのほうが、確実にバットに当てることができるので、
進塁させやすいというメリットがあります。
また、バントのうまいバッターであれば、ランナーが走ったときの守備側の動きを見て、
内野の空きスペースに転がすことで内野安打を狙うこともできます。
一方で、ランナーを走らせているため、ミスして小フライになってしまった場合は、ダブルプレーのリスクが高まります。
バスターエンドラン
さらなる応用として、ランナーを走らせてバスターをする場合が、「バスターエンドラン」です。
バスターは、バントの構えからヒッティングする打ち方で、守備側が極端なバントシフトをしてきたときに有効です。
これにエンドランをかけることで、さらに進塁を狙うかなり積極的な戦術になります。
ランエンドヒット
ヒットエンドランに似たもので、「ランエンドヒット」という戦術があります。
ランエンドヒットは、ランナー中心に考える戦術で、バッターはボールの球種やコースを見て打つか見逃すかを選びます。
例えば、単独でも盗塁可能なランナーが出たときに、ランエンドヒットのサインを出して、
良いボールであればヒッティング、悪いボールであれば見逃して盗塁というような狙いで使います。
この戦術を選択してバッターがあえて打つ場合は、フライやライナーでダブルプレーにならないように特に注意する必要があります。
エンドランのメリット・デメリット

メリット
(1)ゴロを打てた場合、ランナーが進塁しやすい
ランナーがスタートを切っているため、内野ゴロであってもダブルプレーになる可能性が低く、ランナーを進塁させることができます。
最低限、ランナーを進塁させるためには、内野手の正面でも良いので、とにかくゴロを打つことが重要です。
(2)ヒットを打てた場合、さらに先の塁を狙いやすい
ランナーがスタートを切っているため、シングルヒットであっても、2つ先の塁まで進塁できる可能性が高まります。
例えば、一塁にランナーがいる場面のエンドランで右方向にヒットが出ると、
スタートを切っているおかげで三塁まで進塁することができます。
これは、大成功パターンですね!
(3)2ストライクの状態からでも仕掛けられる進塁打
バントは、2ストライクからファウルしてしまうとアウトになってしまいますが、エンドランの場合はヒッティングなのでファウルになっても問題ありません。
なので、2ストライクからでもエンドランを仕掛けることで進塁を狙うことができます。
ミートがうまいバッターであれば、バントよりも使いやすいかもしれません。
ただし、バッターが空振りしてしまった場合、バッターが三振、ランナーが挟まれてアウトとなれば、
「三振ゲッツー」になってしまい、チャンスを完全につぶしてしまうので注意が必要です。
(4)内野手がベースカバーに入るため、ヒットゾーンが広がる
ランナーがスタートを切ることで、内野手が盗塁のタッチプレーのためにベースカバーに入るため、塁間にスペースが生まれます。
つまり、一時的にヒットゾーンが広がることになるので、そこに打つことができればヒットになる可能性が高まります。
このメリットを活かすには、盗塁のときのベースカバーの動きをあらかじめよく観察しておくことが重要です。
特に二塁については、ショートかセカンドか、どちらがカバーに入るのかを把握しておくことで、狙うゾーンを絞っておくことができます。

デメリット
(1)小フライやライナーのときにダブルプレーになる
ランナーがスタートを切っているため、打球が小フライやライナーになると、ランナーの帰塁が遅れてしまい、ダブルプレーになってしまいます。
これだとチャンスを完全につぶしてしまうことになるので、大きなデメリットといえます。
(2)空振りしたときにランナーがアウトになる
バッターが空振りしてしまった場合や、戦術を読まれてピッチアウトされた場合には、単独で盗塁を行ったのと同じになります。
そのまま盗塁成功すれば問題ないですが、ランナーはバッターを見ながら走らないといけないので、盗塁ほど走塁に集中できません。
また、盗塁が得意でないランナーの場合は、アウトになる可能性が高まります。
前述した2ストライクからの「三振ゲッツー」にならないように、注意が必要です。
エンドランを仕掛け方~タイミング~

試合の流れを変えたい
エンドランは、試合が膠着した展開になっていて、何とかゲームの流れを変えたいという場面で使うのが有効です。
成功すると、チャンスが大きく拡大するだけでなく、攻撃側が積極的な雰囲気に、守備側は押され気味の雰囲気になります。
これは単純にバントをして進塁するよりもイケイケの雰囲気になりますよね。
仮に失敗しても、膠着した試合の場合には影響が少なく済みます。
ほかに有効なケースとしては、接戦の試合展開で中盤以降に使うパターンです。
序盤から積極策の失敗で流れに乗れないリスクを負うよりも、何か流れを変えたい場面で使うほうが有効です。
以上より、戦術選択の考え方として、現状の流れを変えたい、リスク承知で積極策を仕掛けたい試合展開で有効です。
逆に、リスクを取らなくても良い試合展開ではあえて使う必要はありません。
ストライクカウント
ヒッティングする必要があるので、ストライクがきやすいカウントで仕掛けるのが基本です。
具体的には、ボール先行になっている(2ボール・0ストライク)またはフルカウント(3ボール・2ストライク)のときです。
ただし、守備側としても戦術を読んでいるので、ピッチアウトなど意図的にストライクを外してくる可能性もあります。
それも踏まえて仕掛けるかどうか見極める必要があります。
アウトカウントは1アウトが多い
エンドランを仕掛けるタイミングとして、アウトカウントは、ノーアウトか1アウトの場合があります。
基本的にノーアウトの場合は、バントが進塁打の基本ですが、点差や試合展開によっては、積極策のエンドランを選択するのもありです。
ただし、ダブルプレーだと一気にチャンスがなくなってしまうので、ゴロやヒットが期待できるバットコントロールのうまいバッターが条件
になってきます。
最もエンドランを仕掛けやすいのが、1アウトの場合です。
単にバントをすると2アウトになってしまい、次のバッターに賭けるしかなくなってしまいますが、
エンドランだと、うまくいけば進塁打プラスアルファを期待することができます。
エンドランに対する守り方

エンドランは攻撃側の戦術ですが、守備側としてどのように対応すべきでしょうか。
まずは、ランナーがスタートを切ってきますので、単独の盗塁に備えてベースカバーに入る必要があります。
ただし、エンドランの可能性を頭に入れておかないと、不用意にヒットゾーンを大きく広げてしまうことになります。
基本的な対応の仕方は、少しベース寄りに守っておき、ヒッティングの有無を確認してから、ベースカバーに入るという形です。
また、バントに備えた守備シフトの場合は、通常の守備位置よりも偏っているため、よりエンドランの可能性をあらかじめ頭に入れておかないと、いざそうなったときに混乱してしまいます。
対応の仕方は、この場合も同様で、ランナーのスタートですぐにベースカバーに入るのではなく、バッターの動向を見てから動くようにします。
このように、守備側としては、不用意にヒットゾーンを広げないよう、バント、盗塁、エンドランのそれぞれをあらかじめ想定して守ることがポイントです。
まとめ
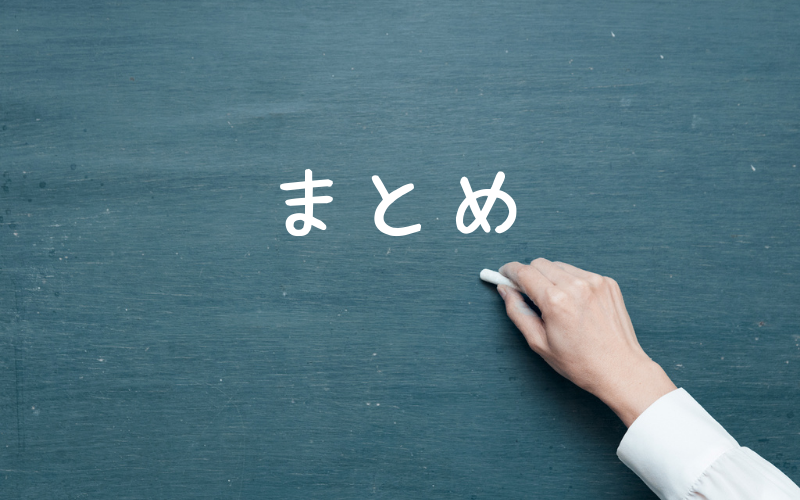
今回は、「野球のエンドラン」について解説しました。
これで、エンドランについて、戦術の概要、メリット・デメリットや仕掛け方・守り方をおさえることができたと思います。
ぜひ参考にしてみてくださいね。