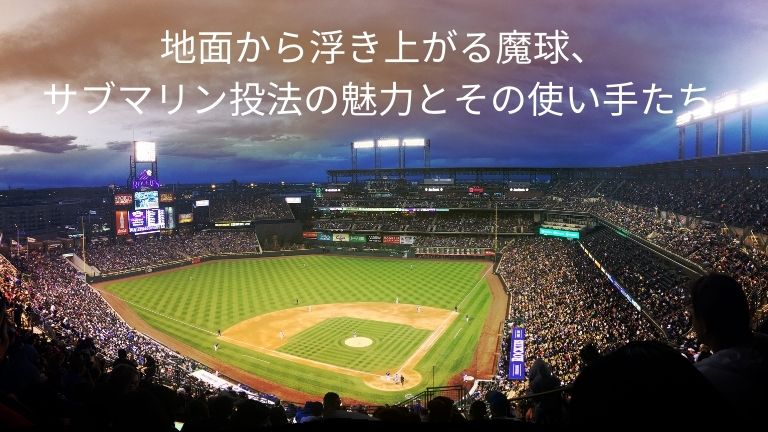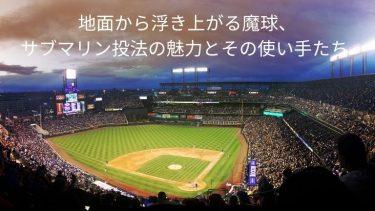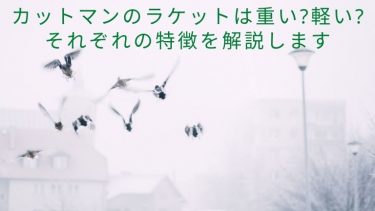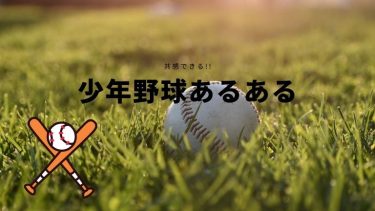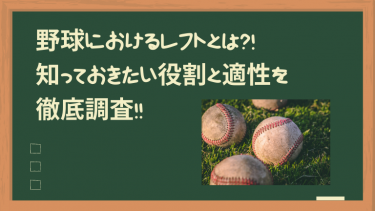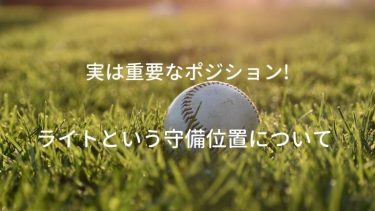サブマリン投法とは、野球の中の投げ方の一つで、アンダースロー、下手投げとも呼ばれています。
地面スレスレから放たれるその球筋は、バッターからみると下から上に上昇してくるように見え、
潜水艦になぞらえてサブマリン投法と呼ばれるようになりました。
そんなサブマリン投法についてご紹介します。
サブマリン投法の定義

サブマリン投法は、ボールを投げる際に腕が水平を下回る角度になっている投法で、
ピッチングモーションから急激に重心を下げ、腕をしならせて投げるのが特徴です。
米国のバイオメカニクス研究者によると「利き腕は体幹に対して90度を保っているが、腕の位置が水平より下がっている投法」
をサブマリン投法と定義付けられています。
このような概念が知られる以前の日本では、「手首を立てている」投手はサイドスロー、
「手首を寝かせている」投手はサブマリンとする区分法もありました。
それゆえに、サイドスローとの切り分けが微妙な投手もいました。
サブマリン投法の長所、短所

一般的にオーバースローと呼ばれる上から投げる投法に対して、サブマリン投法というのはどのような違いがあるのでしょう。
サブマリン投法の長所
地面スレスレから上昇してくる軌道のボールは打者の予測をずらす効果があり、ボールの下を叩いてしまいやすくなります。
このため、球速がそれほど高くなくても打者にとっては打ちにくい球を投げることができます。
また、サブマリン投手の絶対数が少ないのと、球筋を再現できるピッチングマシンも少ないため、
サブマリンの球筋を打ち返す練習をすることが難しいことも有利に働きます。
腕をしならせて投げる投法であり、肩や肘への負担はオーバースローより低いとされています。
サブマリン投法の短所
通常、投手は走者を背負った際、盗塁の隙を与えないためにクイックモーションで投げますが、
サブマリン投法の場合は、クイックモーションが難しく盗塁されやすいというのは短所の一つです。
コントロールの難しさとその球筋から、与死球が多いことも挙げられます。
球速が高くなくても打ちにくい点は長所に挙げましたが、その反対に速い球を投げるのが難しい投法でもあります。
肩や肘への負担は低い反面、踏み出す足に負担がかかるため、下半身の強化が必要とされています。
フォークボールが投げるのが難しい点も短所ですが、落ちる球としてはシンカーが有効で、多くのサブマリン投手はシンカーを修得しています。
サブマリン投法の使い手たち

日本プロ野球界のサブマリンの使い手たちをご紹介します。
重松通雄
日本プロ野球界におけるサブマリン投手第1号と言われている選手です。
皆川睦雄
サブマリン投手として初の200勝を達成した投手です。
プロ入り後3年目の時に二桁勝利を挙げたものの肩を痛めてしまい、コーチの勧めでサブマリンに転向した経歴を持ちます。
当時捕手であった野村克也選手と共にカットボールを研究し習得。日本で初めてカットボールを投げた投手とも言われています。
足立光宏
60年代から70年代の阪急を支えたサブマリン投手。
特に日本シリーズで強さを発揮し、通算9勝は歴代3位の記録です。
その中でも、巨人に対しては8勝4敗という好成績を残しています。
また、巨人のV9時代においては阪急の対巨人戦の成績は8勝20敗でしたが、そのうち5勝は足立選手によるものでした。
山田久志
サブマリン投手として最多となる284勝を記録した選手で、日本史上最高のサブマリン投手と称されています。
チームメイトであった足立選手とは対照的に日本シリーズでは相性が悪く、6勝9敗と不本意な成績でした。
また、ストレート中心の投法に限界を感じた際に、足立選手にシンカーの投げ方を教わりにいきましたが、
「ストレートが通用するうちはシンカーは投げるな」と拒否されたそうです。
これは、「山田がシンカーを覚えたら脅威となり、すぐに自分に取って代わる存在になるのが分かっていたため教えたくなかった」
と足立選手が引退後に語っています。
それだけ認められた存在だったということですね。
そこから山田選手は足立選手からシンカーを盗み取ろうと毎日のように研究を重ねたそうです。
数年後に足立選手から投げ方のヒントをもらい、そこから本格的にシンカーを使い始め、更なる活躍を見せました。
落合選手に対して3本塁打を浴びた試合では、狙われているのを分かっていながら、得意球のシンカーで勝負したというエピソードもあります。
そして清原選手にシンカーを本塁打にされた1988年に引退を決意、引退後はコーチおよび監督としても活躍されました。
渡辺俊介
世界一低いと言われるリリースポイントが特徴で「ミスターサブマリン」という通称を持つ選手です。
一般的なサブマリン投法よりも更に低く、地上約3cmの位置でボールをリリースしており、ただえさえ球筋が分かりにくいサブマリン投法ですが、
更に特殊な球筋が持ち味でした。
また、投球動作開始からリリースまでの時間を変化させる技術を持ち、タイミングを外す投球も得意としていました。
一方で、調子が悪い時には地面に手を擦ってしまうこともあり、あらぬ方向へ暴投してしまったこともありました。
13年のロッテでの選手生活の後、メジャー挑戦しますが結果を残せず解雇、独立リーグにてプレーを続けました。
その後日本に帰国。
プロ野球ではなく、社会人野球の「日本製鐵かずさマジック」にコーチ権選手として就任。2020年からは監督に就任しています。
近田豊年
この選手をご存知の方は少ないと思います。
1987年にドラフト外で南海ホークスに入団。左右両投げという日本プロ野球初のスイッチピッチャーでした。
元々左利きでしたが、左用のグローブが無く、右投げで野球をしていたことがきっかけで、利き腕の左はオーバースローですが、
右はサブマリン投法でした。
左右どちらでも使える6本指グローブが特注され話題となっていました。
しかし、「まずは左を一人前にしてから」という監督方針により、残念ながら公式戦で右のサブマリンを披露する機会はありませんでした。
まとめ

日本プロ野球、メジャーリーグ共にサブマリン投法の使い手は少ないです。
オーバースローやサイドスローと比べて身体全体を使う難しさ、球速の出しにくさなどが使い手が少ない理由でしょう。
しかし、地面スレスレから投げる美しいピッチングフォームと、そこから放たれる球筋は魅力的なものですから、
今後も名手と呼ばれる使い手が現れることを期待しています。
現在の現役投手にも、牧田和久選手、高橋礼選手といったサブマリンの使い手もいますので、今後の活躍が楽しみですね。