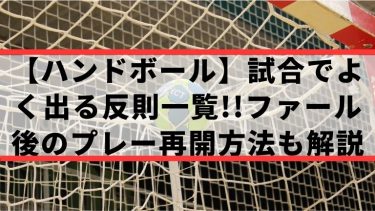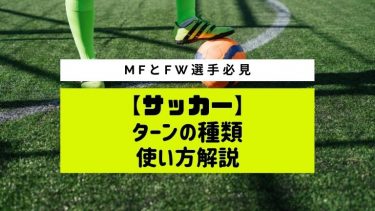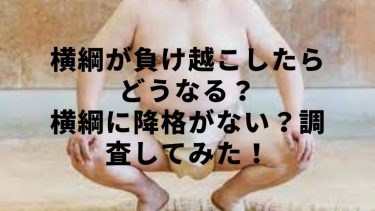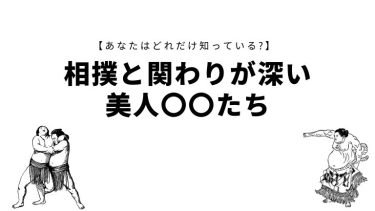大相撲は日本の国技で、その起源は奈良時代まで遡る事が出来ます。
当時は、武器は何も所持していない証拠にふんどしだけで行っていたのです。
そのふんどしがを期限に現在の「回し」になったといわれています。
大相撲では、力士がつける回しには多くの種類の色がありますが、回しの色には基準などが設けられているのでしょうか?
力士がつける回しには種類がある!本場所の回しにも取り決めが!

力士がつけている回しには、2種類の回しがあります。
・稽古用の回し
・大相撲本場所で使用する締め込みという回し
更に稽古用の回しでは、十両以上の力士は白色、幕下以下は黒色の回しと決められています。
稽古用の回しの素材は堅い木綿生地を使い、幕下以下は稽古用の回しを本場所でも使います。
ただ、十両以上(関取)は、大相撲本場所において回しの色は、力士によって多くの色を使用します。
回しの色の規定とは
日本相撲協会の力士規定には、回しの色は規定によって紺または紫系の色を使う事を定めています。
こちらを守るとすると、十両以上の全ての力士は、紺または紫系の回ししか見る事が出来ないはずです。
実際は、大相撲本場所において力士の回しの色は、金色や赤・緑なども私用されています。
力士規定を十両以上の力士は相撲協会が定める力士規定を守っていないことになるのです。
力士規定を無視しているわけですから、回しの色を規定通り守っている力士以外には、何らかの罰則を受けるのでは?と思ってしまいます。
しかし、回しの色が紺または紫系以外の力士は罰則を受けることなく、
いろいろな色の回しをつけて大相撲本場所において取り組みを行っているのです。
相撲協会の理事の八角親方も現役の時には、紺または紫系以外の回しの色を使用しています。
大相撲本場所において、実は相撲協会事態は、暗黙の了解が実態なのです。
お偉いさんも現役時代に好き勝手していたからこそあまり強くは言えないのが実態のようです。
大相撲本場所の色は誰が決める?

大相撲本場所において、力士がつける回しの色の規定はあるが、暗黙の了解では罰則の規定はありません。
でも、疑問もあります。
大相撲本場所において、力士がつける回しの色は、誰が決めているのか?という事です。
確かに、相撲協会は紺または紫系を規定に載せてはいますが、何色を付けても罰則がないのが現状ですから、
じゃ~どの人物が色を決めているのでしょう。
力士がつける回しを決めるのは誰?
大相撲本場所において、様々な色がありますが本人がそうやって決めているのでしょうか。
・本人または親方が決めたりしている
・力士の後援会から回しが贈られた場合には、後援会の回しをつける
・力士本人が決める場合には、尊敬する先輩力士と同じ色の回しを選ぶことが多い
・親方が選ぶ場合には、力士が親方に頼む
・中には両親から贈られた回しをつけることもある
大相撲本場所において、力士がつける回しの色の取り決めは、無いようですが幕下から十両に上がったときに後援会から、
関取になったお祝いとして色付きの回しが贈られることが多いようです。
幕内上位力士と幕内下位力士で色の変化がみられる?
大相撲本場所において、幕内力士では上位力士(横綱・大関など)と下位力士(前頭)では、回しの色の変化がみられることがあります。
後援会から力士が昇進したお祝いとして色付きの回しを贈られることがありますが、
幕内上位力士となると力士本人の意向が後援会などにも伝えることが出来るようです。
これには、大相撲本場所においての勝負が関わっていると考えられます。
色付きの回しの場合には、回しに水分(汗など)が染み込むと、伸びやすくなる傾向があるようで、
取り組みの時に相手力士に回しを取られやすくなるのです。
回しをとられてしまうと、勝敗に大きく影響を及ぼす可能性が高くなります。
しかし、幕内力士でも上位力士となると、黒色や紺色などが多くなっていくのです。
これらの色は水分を含んでも、回しが伸びやすくなるという事がなく、きつく締めても緩まることがありません。
回しが緩むことがないという事は、相手力士の手が回しに入りにくくなるのです。
回しが取れなければ、有利な体制を取れないという事になります。
幕内力士でも上位力士は、下位力士と違って黒色や紺色の回しをつける率が高くなるのです。
本場所用回しと稽古用の回しの長さや洗濯はどうするの?

大相撲本場所において力士がつける回しの色の選択については親方や後援会などが関係しています。
稽古用の回しは木綿ですが、本場所用の回しは絹を使用しているのです。
本場所用の回し
・長さ:6mから9m
・幅:約80cm(これを4つ折りまたは6つ折りにして使用)
・値段:本場所用の回しの値段は70万から100万円する
本場所用の回しは、高価なものという事がわかります。
回しは、絹布のため高価になりますから、そうやすやすと交換することが出来ないのです。
また、本場所用の回しは体になじむまで、何年もかかるために力士は1本の本場所用の回しを使用し続けることになります。
大相撲の力士が使う回しは色に関係なく、洗濯はしないのか?
大相撲の場合力士は、稽古用の回しと本番用の回しを持っています。
しかし、体になじむまで使用し続けるので、気になるのが回しは洗濯するのか?という事です。
本場所用の回しは、博多織や西陣織を使用することで、絹布を使用しているために洗濯することができません。
交換するまで、洗わない事が通常なのです。
衛生上あまりよろしくはないのでは?と考える方もいるでしょう。
稽古用の回しは、木綿布に糊で固められているために、使用する前に糊を落とすために洗濯というよりもブラシで糊を落とすことをします。
本場所用の回しは、洗濯することが出来ないので、消毒液やファブリーズ的なもので手入れをして、
相撲部屋の屋上から垂らして乾燥させるという方法をとるのです。
洗濯することが出来るのは、稽古用の回しのみということになります。
力士が本場所用・稽古用の回しは、古来から洗濯してはいけないといわれているのです。
回しを洗っていい時は、師匠が他界した時だけになります。
大相撲は神事にあたりますから、神様は穢れを嫌うことから、力士がつける回しも神事に携わるものとして、
穢れを払うということで洗濯してくださいという事になるのでしょう。
現在は、各相撲部屋によって回しの洗濯については違いがあるようです。古来からの習わしを守っている部屋は、かなり少なくなってきています。
まとめ
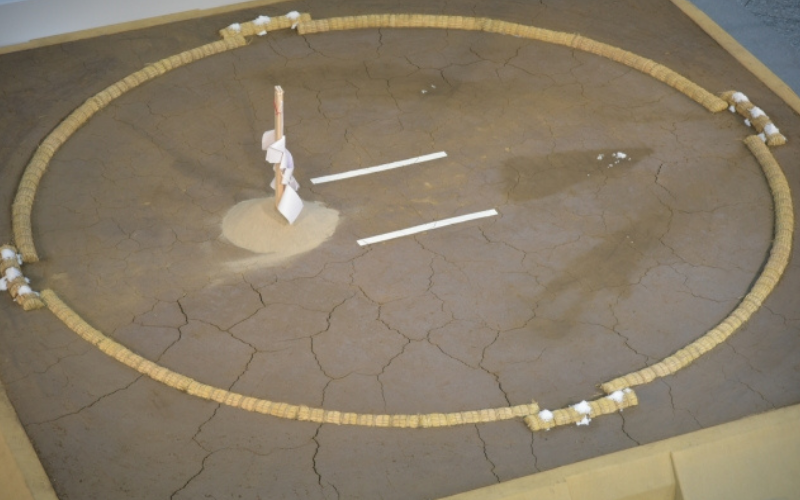
大相撲での色の規定について紹介してきました。
- 回しには、本場所用の回しと稽古用の回しの2種類がある
- 十両以上の力士は稽古用の回しは白色で幕下以下は黒色を使用する
- 使用する回しは、相撲協会の規定では紺または紫系と決められている
- 色の回しを使用している力士が多いが、相撲協会は黙認している
- 回しは、力士本人だけでなく、親方や後援会などが決める
- 回しは、古来から洗濯しないのが習わしだが、衛生上現在は洗う部屋もある
などという事がわかりました。
力士がつける回しにはいろいろな事情がある事がわかったと思います。
カラーテレビが導入され始めたころから増加しているようで見ている側も応援の方も力士を識別しやすいですね。