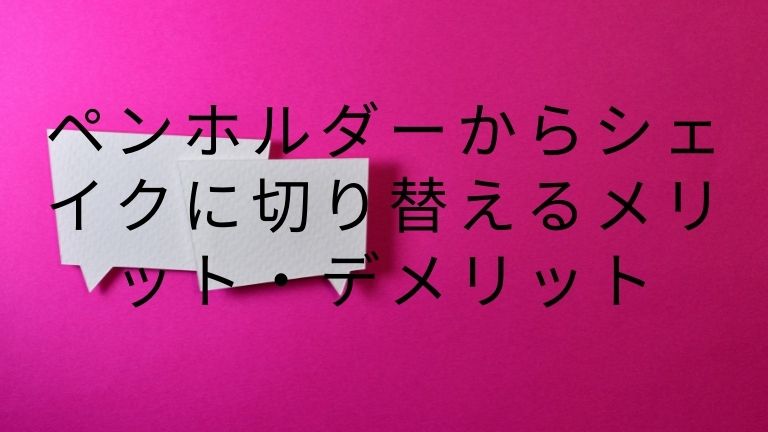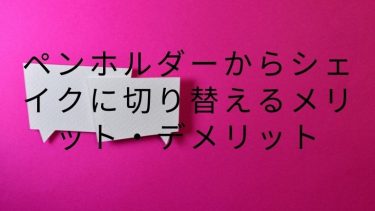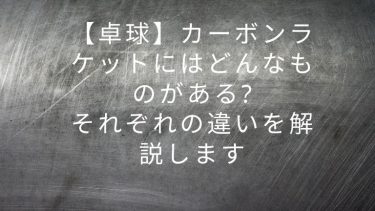卓球は、一昔前までは「地味である」だとか、「何か暗い」などと捉えられることの多いスポーツでした。
しかし、最近の日本卓球選手の目覚ましい活躍により、一躍人気のスポーツになったように感じられます。
実際、日本の卓球人口はとても多く、1000万人もいると言われています。
競技人口だけに絞っても、250万人もいるそうなので、思ったよりも多いのではないでしょうか。
さて、そんな人気のある卓球ですが、卓球のラケットにはどのようなものがあるでしょうか。
昔から卓球を楽しんでこられた人であれば、ペンのようにラケットを持つ、ペンホルダーラケットを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
実は、現代卓球において、ペンホルダーの選手はかなりレアになってきています。
現在ペンホルダーでプレーしているが、今後シェイクハンドに転向したい、という人も多いのが現状です。
そんな人への注意点も含め、紹介していきます。
ペンホルダーの特徴

前述のように、昔から卓球をプレーされている人の間で人気なのがペンホルダーです。
ペンホルダーの特徴は色々とありますが、まず第一に挙げられるのが、「ラバーが片面だけ」という点でしょう。
これは言い換えると、ラケットの総重量が軽いということでもあります。
ペンホルダーは、その持ち方から、基本的にラケットを反転することに適していません。
中には、グリップ部を替えて反転できるようにしたものもありますが、これは粒高などを使う、
いわゆる「攻守切り替え型」の選手に限ったことが多いです。
また、基本的にラバーが片面だけなので、裏ソフトラバーや、変化型でない表ソフトラバーを使う選手が多い傾向にあります。
ペンホルダーの選手は、日本が「卓球王国」だった一昔前においては、ほとんどが「前陣速攻型」の選手でした。
これがペンホルダーの第二の特徴と言えるでしょう。
前陣速攻とは、卓球台からあまり離れずに早いピッチで攻撃を仕掛けていくスタイルです。
ペンホルダーの第三の特徴は、「移動範囲が大きい」ことです。
なぜかというと、ペンホルダーのバックハンドは、フォアハンドに比べて威力的にかなり見劣りがしてしまいます。
ペンホルダーの持ち方だと、構造的にどうしてもバックハンド打撃で威力を出すことが難しいのです。
ペンホルダーの選手は「ペンドラ」と呼ばれることも多く、「ペンドラ」と言えば大きく回り込んでのフォアハンドドライブが主力武器です。
一撃一撃の打球はとても強力なのですが、バックハンドに威力がなく、
どうしても移動距離が大きくなってしまうので、スタミナが必要となってくるプレースタイルです。
シェイクハンドの特徴

シェイクハンドは、ラケットの両面にラバーを貼る、現代卓球においては主流のスタイルです。
第一の特徴として、ラケット両面にラバーを貼ることから、「ラケットの総重量が重い」ことが挙げられます。
先ほどのペンホルダーであれば、平均重量は130〜140gほどですが、シェイクハンドだと平均重量は180〜190gもあります。
たった40〜50gくらいの違いですが、予想以上にその差は大きく、普段ペンホルダーしか使わない選手であれば、腱鞘炎になりかねません。
シェイクハンドの第二の特徴は「プレースタイルが限定されない」ことです。
前述のペンホルダーだと、前陣速攻型か、攻守型の選手が多いのが現状です。
しかし、シェイクハンドの選手だと、カットマンから前陣速攻型までと、カバーできるプレースタイルの範囲が非常に広いのです。
これは、一度シェイクハンドに慣れてしまえば、将来的にどのようなプレースタイルも選ぶことができるということを意味します。
卓球を始めた時に、多くの選手は指導者から「攻撃マン」になることを勧められます。
しかし、始めたばかりの頃は、選手自身の実力や経験が足りず、本当に自分に適しているプレースタイルを自分で把握することはできません。
なので、後々プレースタイルを変更するようになる、ということは往々にして起こりうるのです。
そのような状況になっても、シェイクハンドでさえいれば、選べる選択肢は多くあります。
ペンホルダーからシェイクハンドへ転向するメリット

現代卓球は、歴代最速のピッチだと言われます。
卓球が人類史に登場してから、卓球の速度は増すばかり。
そんな中、ペンホルダーからシェイクハンドへの転向をする人が増えています。
ここでは、シェイクハンドへ転向するメリットについて紹介していきます。
まず、第一のメリットとして、「バックハンドの弱さがなくなりピッチの早い現代卓球についていける」ということが挙げられます。
ペンホルダーの特徴の中で触れた通り、ペンホルダーの最大の弱点はバックハンドにあります。
もちろん、バックハンドの上手い選手は多く存在していますが、
それでもその選手のフォアハンドの威力とバックハンドとでは比べるべくもありません。
バックハンドが弱点なので、全てフォアハンドでカバーしようとするあまり、フットワークが必要となり、動きが大きいために隙も生じます。
そうすると、現代卓球の早いピッチについていけなくなる、という結果になってしまう場合が多いでのです。
こうした悪循環が、シェイクハンドに転向することで解決します。
また、シェイクハンドに転向する第二のメリットとして、「多彩な攻撃が可能になる」ことが挙げられます。
シェイクハンドはラケットの両面にラバーを貼るので、表面と裏面とで異なるラバーを貼ることもできます。
異なる種類のラバーから繰り出される打球は異質ですので、相手を撹乱することができるようになります。
ペンホルダーだと、基本的にラバーが片面にしかありませんので、異質攻撃をすることは困難なのに対し、
シェイクハンドだとさまざまな組み合わせを選ぶことができるのです。
ペンホルダーからシェイクハンドへ転向するデメリット

それでは、逆にペンホルダーからシェイクハンドへ転向するデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
第一のデメリットとして、「慣れるのに時間がかかる」ことが挙げられます。
実は、ペンホルダーからシェイクハンドへ転向を試みるけれど、やはり長年親しんだグリップの違いに耐えられず、
転向を断念してしまう人が少なくありません。
特に、ペンホルダーの選手には比較的年配の人が多く、小さい頃から握り続けてきたペンホルダーのグリップを手放せない人が多いようです。
実際に両方のラケットを握ってみると分かるのですが、シェイクハンドに比べてペンホルダーはグリップがかなり固定されます。
そのグリップに慣れてしまうと、シェイクハンドのグリップは、「グラグラする」と感じてしまうのです。
卓球では、相手の打球に合わせた面を作ることが大切で、それには角度の作りやすいペンホルダーの方が適しています。
また、第二のデメリットとして、「ラケットが重くなってしまう」ことが挙げられます。
シェイクハンドの特徴の箇所でも触れましたが、軽いペンホルダーラケットを長年使用していたプレーヤーであればあるほど、
シェイクハンドへ転向した時に感じるラケットの重さはひとしおです。
そのまま無理して使い続けると、故障にもつながりかねません。
もし、シェイクハンドラケットが重いと感じたら、できるだけラケット自体の重量が少ないものを選んだり、ラ
バーの種類を変えて、少しでも軽くしてから徐々に慣らすといいように思います。
まとめ

ペンホルダーとシェイクハンドのそれぞれの特徴と、ペンホルダーからシェイクハンドへ転向する際のメリット・デメリットに関して説明しました。
これから、シェイクハンドへ転向しようと思っている人は参考にしてみてください。
ポイントは、徐々に慣らすことです。
くれぐれも、怪我や故障のないように、無理のない程度で、素敵な卓球ライフをお過ごしください。