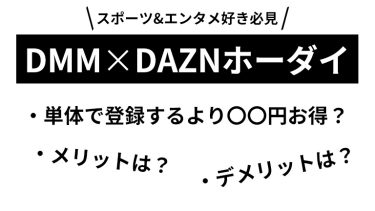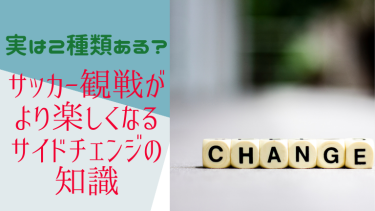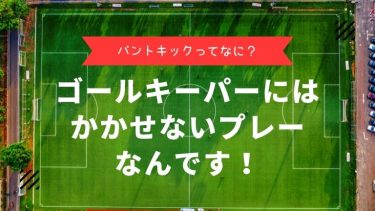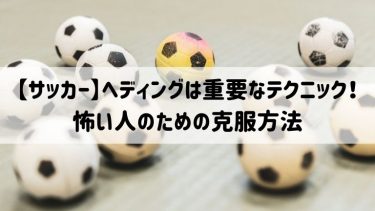サッカーの試合において、重要な役割を担う審判。
サッカーの審判は、他のスポーツと比較すると少し毛並みが違ってきます。
通常のスポーツにおける審判は、プレイに対して反則がないかを見ますが、サッカーの審判は、ルールの中で円滑に試合をコントロールすることが求められます。
サッカーの審判が円滑に試合をコントロールするために必要不可欠なアイテムが、レッドカードやイエローカードです。
カードは、レッドカードとイエローカードの2種類に別れていますが、レッドカードとイエローカードの違いは何か、
どのような場面でカードが出るのかをピックアップしながら紹介していきます。
サッカーのカード

サッカーは、前後半90分で戦うスポーツで、時間が止まらず流れが常に変化します。
時間を止めずに試合が進行できるのが一番ベストですが、プレイの判断が遅れて相手選手を倒してしまったなどの行為があった場合は、
速やかに試合を中断しなければいけません。
しかし、相手選手が倒れても相手チームが有利な状況下にある場合は、そのまま試合を続行し、中断後に注意などをする、
レッドカードやイエローカードを出す裁量権が与えられているのが審判です。
しかし、ファールやカードの基準や判断が審判一人一人によって解釈が異なり、国によって審判の判断も全く変わってきます。
何故審判の判断基準が異なるのかというと、審判が育ってきた国や地域の文化、環境に哲学などが大きく関わってくるからです。
例えば、日本ですとルールに厳格で、特に後ろからのチャージに対してはものすごく過敏に対応しがちです。
しかし、サッカー発祥のイングランドでは、チャージに対してはあまり厳しくありませんが、
相手を欺くプレイや審判の見えないところで足を削るなどの行為には非常に厳しく対応します。
サッカーの反則に対しては、国や地域、審判の判断が異なりますが、当然カードの基準も国によって異なります。
わざと手でボールに触ったなどの悪質行為以外は、審判によってカードが出る出ないが変わってくるということも日常茶飯事です。
カードの種類
サッカーの試合で審判が持っているカードは、イエローカードとレッドカードの2種類です。
イエローカードとレッドカードは、何らかの反則行為があったと審判が判断した場合に該当選手に提示されるもので、
当然カードの種類によって反則の重さが変わってきます。
イエローカードよりもレッドカードの方が反則の度合いが重くなり、レッドカードを提示された選手は、
場合によっては数試合の出場停止処分が科せられる場合があります。
レッドカードとイエローカードの違い

サッカーの試合で、審判が選手に対して提示するレッドカードやイエローカードですが、イエローカードを見ない試合はまずありません。
しかし、レッドカードも数試合毎に1枚は必ず見るもので、何故使用回数がこれほどまでに違うのか、疑問に持つ方も多くいます。
ここからは、レッドカードとイエローカードの違いについて解説していきます。
レッドカード
レッドカードは、サッカーの試合において最も重い処分になり、提示された選手は速やかにフィールドから退場しなくてはなりません。
プレイ中に乱暴な行為を働く、人を噛むなどの他、相手選手の得点チャンスを反則で止める場合もレッドカードの対象になります。
更には暴言を吐く、差別発言や差別と捉えられるジェスチャーをする、下品な発言をするなど、
相手選手や審判に対して不愉快な発言やジェスチャーをした場合もレッドカードの対象になります。
1発退場を提示された選手は、次回のリーグ戦ならリーグ戦、カップ戦ならカップ戦の主催試合に出場することはできません。
更に、後日委員会が設けられ、レッドカードの内容によっては数試合の出場停止になる場合もあります。
最悪の場合、永久追放処分や刑事訴追されるなど重い処罰が待っている場合もあります。
イエローカード
サッカーのイエローカードは、反則や反スポーツマンシップ行為に対して該当選手に提示される警告のカードです。
危険なプレイはもちろんですが、審判の判定にしつこく意義を唱えたり、プレイの再開を遅延させる、審判からの注意に従わない、
無断でフィールドから離れるなどの場合もイエローカードの対象になります。
1選手が1試合で2枚のイエローカードが提示されると退場となり、次の主催試合に出場することはできません。
リーグ戦やカップ戦で、規定枚数以上のイエローカードが提示された場合も同様で、次試合の出場停止処分が科せられます。
ここが変だよ、カードの場面
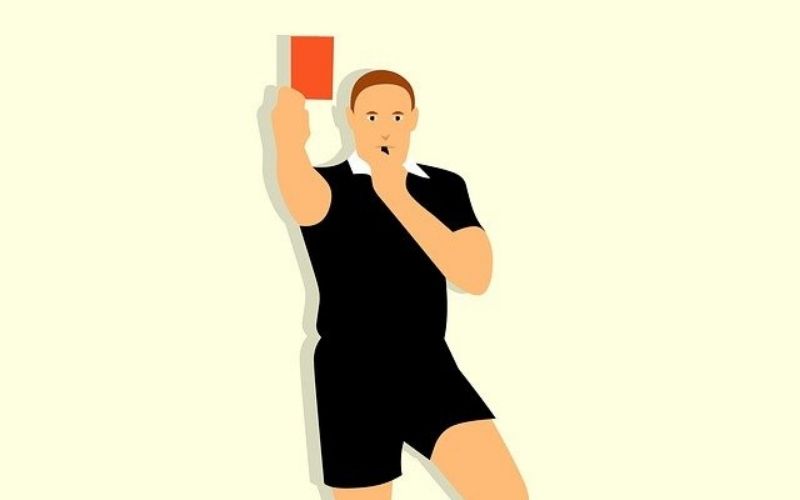
サッカーの試合でよく目にするカードですが、場合によっては選手自身の今後に影響する場合もありますので、
提示する審判は常に公正中立であり、冷静な判断を下さなくてはなりません。
しかし、審判も人間ですから公平さを欠いて、カードで思わぬトラブルを招く試合もあります。
絶対にあってはならないカードで荒れた主な試合を、Jリーグを例にして紹介します。
カップ戦決勝でカードを乱発
2008年3月1日に行われた、フジゼロックススーパーカップ決勝、鹿島アントラーズ対サンフレッチェ広島の試合は、
審判が冷静さを欠き、両チーム合わせてイエローカード11枚、レッドカード3枚が提示される異常な試合となりました。
判定そのものに問題はなかったのですが、選手と審判の信頼関係が希薄だったこと、
カードを提示せず注意で済んだ場面でもカードを提示したなどが浮き彫りとなり、該当試合を担当した審判は無期限担当割り当て停止の処分を受けました。
カードの有無で試合が荒れる
2018年11月24日に行われたJ1リーグ第33節、清水エスパルス対ヴィッセル神戸戦の後半アディショナルタイムで、
両チームの選手が接触で倒れたにも関わらず、審判が試合を止めないどころか、対象の選手にカードを提示しない場面がありました。
更に、アディショナルタイムの時間計測を誤る、接触行為が相変わらず続いたのにプレイを続行しカードも出さないなど、
両チームの審判に対する不満が爆発し、ついには乱闘騒ぎにまで発展してしまいます。
円滑に試合を進めるのは当然のことなのですが、危険なプレイに対しては速やかに中断してイエローカードやレッドカードを提示する勇気も必要です。
監督やベンチメンバーもカード対象
Jリーグ史上最大の珍事となったのが、2009年10月17日に行われたJリーグディビジョン1第29節、横浜Fマリノス対名古屋グランパス戦です。
後半35分過ぎ、横浜Fマリノスの選手がピッチにうずくまり、試合を中断しようと、横浜Fマリノスのゴールキーパーがボールを外に蹴り出します。
外に蹴り出したボールは、偶然にも当時名古屋グランパス監督だったドラガン・ストイコビッチ氏の元に来るのですが、ここからが珍事の始まりとなります。
ストイコビッチ氏は、来たボールを革靴のままダイレクトで相手ゴールに蹴り出し、約50メートル以上離れた横浜Fマリノスゴールに吸い込まれました。
選手時代は、Jリーグ屈指のスターであったストイコビッチ氏のプレイに観客から歓声が上がります。
しかし、一連のプレイが審判への侮辱行為と判断され、ストイコビッチ氏は退席処分を言い渡されます。
現行のルールですと、監督でもカード対象となり、ストイコビッチ氏にレッドカードが提示され1発退場となりますが、
当時のサッカーのルールでは監督の罰則規定がなかったため、退席処分となりました。
まとめ

サッカーの試合において重要な局面となるレッドカードやイエローカード。試合においては様々な物議を醸しだし、
DAZNの「ジャッジリプレイ」などで議論が交わされます。
サッカーの試合では審判もゲームの一部と捉えられて、サッカーの試合が終わった後でも試合の内容や、
レッドカードやイエローカードの場面で語り合うサッカーファンが大勢います。
何気なく見ているサッカーの試合、正しい判定とレッドカード、イエローカードは試合を盛り上げる一つのキーアイテムになるでしょう。