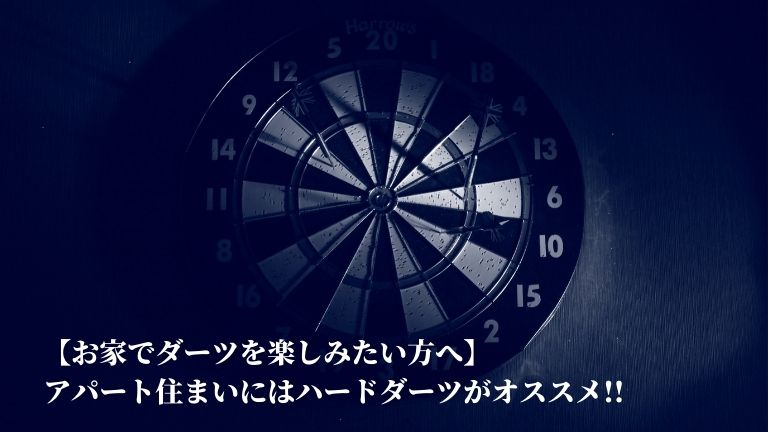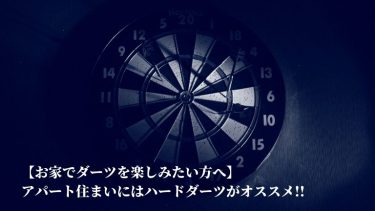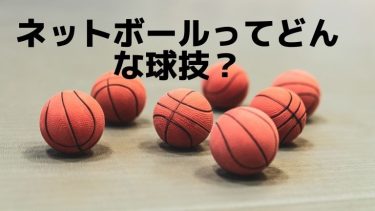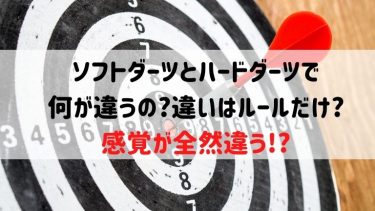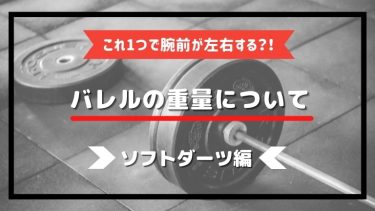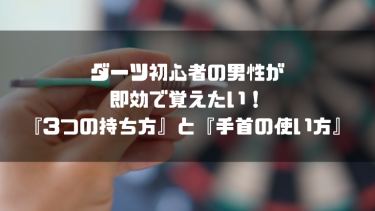「ダーツを家でも楽しみたい」。そんな想いを持っている方も多いと思います。
近年、日本でもダーツバーなど気軽にダーツを楽しめるお店が増え、身近にプレーできるようになりました。
しかし、更なる上達を目指して練習しようとすると頻繁に通うことになり、出費もかなりのものになってきます。
そのため、自宅にダーツボードを設置して、一人でじっくり練習できる環境が欲しくなるのは自然の流れだと思います。
しかしながら、マイホームの方はまだしも、アパートなどの賃貸住宅に住まれている方には、中々ハードルが高い部分もあり、導入を躊躇っている方も多いと思います。
そんなアパート住まいの方でもダーツボードを設置できるポイントを紹介していきます。
自宅に設置する際に気をつけるポイント

ダーツは射的競技の一つであり、競技ルールが定められています。
それゆえ公式な大会への出場を視野に入れている場合は、ルールに遵守した設置をすることが大前提となります。
その際に注意すべきポイントについて以下の4点を解説していきます。
ダーツの種類
ダーツにはスティール・ティップ・ダーツとソフト・ティップ・ダーツの二種類あり、それぞれハードダーツ、ソフトダーツと呼ばれています。
ハードダーツは矢でいう鏃の部分にあたるポイントという部品がが金属製のもので、ソフトダーツはポイントがプラスチック製なのが大きな相違点です。
そして、ダーツボードの素材については、ハードダーツ用は麻で出来ており金属製の矢が直接刺さりますが、ソフトダーツ用のボードはプラスチック製で細かく穴が開いており、その穴に刺さる仕組みになっています。
それに伴い、センサーでスコアが自動計算されるのもソフトダーツの特徴の一つです。
また、ハードダーツではダーツがボードに刺さらないと得点にならないのに対し、ソフトダーツでは刺さらずに落下してもセンサーが反応していれば得点として認められます。
ボードサイズについてもサイズが異なり、ハードダーツは13.2インチ、ソフトダーツは15.5インチとなっておりソフトダーツの方が大きくなっています。
さらに、ボードからスローイングラインの距離もハードダーツは237cmに対して、ソフトダーツは244cmと若干長いです。
以上のように、細かい所で相違点がありますが、近年では手軽で安全ということと、点数を自動計算されたり、結果の記録を残せるということで、ソフトダーツが広く普及しています。
ですが、残りの3つのポイントを考慮すると、自宅で練習する際はハードダーツを設置することをお勧めします。
スローイングの距離確保
ダーツを投げる距離もルールで規定されていますので、これは絶対に確保できているかを確認すべき項目です。
そのためにはまず部屋の広さをしっかり把握する必要があります。
その際、スローイングラインまでの距離だけでなく、ダーツボードの厚さ、投げるモーションに必要なスペースを確保できていることも重要です。
スローイングに必要な広さは個人差もあるため一概には言えませんが、合計で320cmは確保しておきたい距離です。
そして、万が一部屋の広さ足りず十分な距離を確保できなかった場合、斜めにレイアウトする検討もしてみてください。
わずか2.6m×2.6mの部屋でも対角線は3.6mほどになり、規定の距離を確保できることになります。
ここでも、ハードダーツではソフトダーツより必要な距離が短くなるため、スペース確保に若干の余裕ができる点がポイントの1つです。
騒音問題
ダーツは静かな競技というイメージがありますが、ボードに刺さる時の音は意外と大きく、騒音問題のタネになります。
ソフトダーツの場合、この音がかなり響くため、遮音性の弱いアパートでは昼間でも気を使ってしまうレベルです。
その点、ハードダーツはボードが麻でできておりクッション性が高いため刺さった時の音が静かなのが特徴です。
この点が自宅で設置する場合にハードダーツをオススメする一番の理由です。
特に仕事帰りの深夜に練習時間が集中する方には外せないポイントとなります。
また、足音もトラブルになりやすい騒音です。
投げた後ボードにダーツを取りに行き、スローイングラインに戻るという移動を繰り返す競技のため、意外なほど足音が下の階に響いていることがあります。
少し古いアパートでは、生活の中のちょっとした移動の足音でもミシミシ聞こえてくるレベルの遮音性ですので、頻繁に歩くことが必要なダーツは近隣からのクレームのリスクが高いとも言えます。
これについては、歩く場所にカーペットを敷くなど、クッション性のある物で吸収させることで、ある程度緩和させることができます。
壁と床の保護
100%ボードを狙うことができれば心配無用でしょうが、大きく外して壁に刺さってしまったり、上手く刺さらずに床に落下させてしまったりと、ボードを外してしまうこともあるため、壁と床に対してもしっかりと保護をしておく必要があります。
マイホームの場合は自己責任で直す直さないも決められますが、賃貸の場合、退去時に修繕費用が取られる可能性もありますので、なるべく傷つけないようにしておくことが重要です。
壁については、一見ハードダーツの方が攻撃性が高いように思えますが、ソフトダーツでも壁に向かって投げれば普通に刺さってしまいます。
騒音に対して問題無い環境でソフトダーツを導入する場合にも、壁の保護はしっかりとやっておいた方がよいです。
基本的な保護としては、バックボードと呼ばれるダーツボードの後ろに大きな板を取り付けることです。
初心者のうちはなるべく大きめな物を用意したほうが安心できるかと思います。
バックボード付きのスタンドというのも販売されており、高さも既に規定値で設置されている上に、壁からの距離も離れるため、壁保護に対してより安全側にできます。
また、サラウンドと呼ばれるボードの周りを保護するクッション材もありますので、合わせて使用すると更に安心です。
床についても、フローリングの場合はダーツが落下してしまった際に予想以上に傷つけられます。
これについては足音対策と合わせてカーペットを敷くことで保護できますので、フローリングの方は十分な広さのカーペットを用意して敷くようにしましょう。
まとめ:アパート住まいにはハードダーツ

以上のことを踏まえると、特にアパート住みの方にはハードダーツがオススメです。
単に騒音だけの問題ではなく、ダーツボードの大きさも小さいため、コントロールの訓練には良いという声もあります。
デメリットとしては、ダーツの重量がハードとソフトで異なるため、投げる際の感覚が微妙に違うと感じることが挙げられます。
ただし、これについても基本的には同じ投げ方で両立可能とも言われており、そこまでシビアに考えなくてもよいと思います。
それ以上に近隣からのクレームで自宅でのダーツ禁止になっては意味がありませんので、
部屋に設置する際は近所迷惑回避を最優先にすべきでしょう。
まずはハードダーツを設置して練習時間を確保し、沢山投げる環境を作ることが上達への近道でしょう。