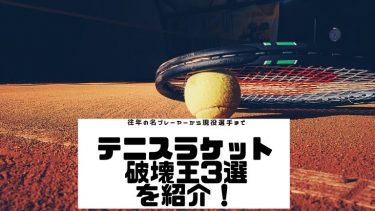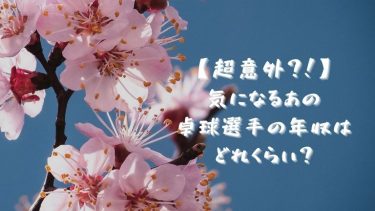この記事にたどり着いたということは、あなたは卓球をしているか、
もしくはこれから始めようとしている、もしくは興味がある方かもしれませんね。
卓球には、ローカルルールというような、その世界独特の流儀、いわゆる「あるある」が多く存在しています。
ここでは、特に初心者にありがちな卓球あるあるを紹介していきます。
卓球をプレーしたことのある方なら、納得されるものも多くあると思いますよ。
卓球あるある〜用具編〜

さっそく参りましょう。
まずは用具に関してです。
用具は卓球選手にとって命とも言える存在。
そして、それだけに誰もが味わったことのある、ローカルルールも多くありますよ。
卓球用具は、ラケット1つとってもさまざまな種類があります。
その数だけ「あるある」も存在すると言っても過言ではないでしょう。
粒高ラバーを「イボ」・「イボ高」と呼ぶ
みなさんは、粒高ラバーはご存知でしょうか?
そう、少し卓球をかじったことのある方ならご存知の、回転を反転してしまうラバーのことです。
正式名称は「粒高=つぶだか」と読むのですが、卓球界隈ではなぜか「イボ」と呼ばれています。
もしくは、「イボ高=いぼだか」とも。
皮膚にできるあのイボって、あれほどの高さはないように思いますが。
特に、ご年配の方が「あ〜、あの選手はイボだからね〜」などと渋い顔をして粒高選手のことを表現するのは、よく見る光景でもあります。
卓球歴が浅い選手には、とにかく嫌われがちな「イボ」の紹介でした。
新入部員はラバー付きラケットを買ってしまう
これも、世間一般から誤解を受けやすい「あるある」の1つです。
中でも、いわゆるお遊びで卓球をしたことがある方が勘違いされている場合が多いのですが、
競技卓球では、ラケットとラバーは初めからくっついているものではありません。
100円均一のお店などでは、ラバー付きラケットが売られているので、そう思われる方も多いと思うのですが、
本来、選手は自分好みのラケットを買った上で、これまた自分に合うラバーを自分で貼っているのですね。
100円で売っているようなラケットは、「レジャー用ラケット」と呼ばれており、競技用のラケットとは、その性能・価格面で大きく差があります。
実際に2種類のラケットで玉突きをしてもらうと分かると思いますが、レジャー用ラケットは球があまり跳ねません。
ラバーにも摩擦がなく、卓球の核心である回転をかけることも難しく思います。
あとは、なぜか裏ソフトラバーではなく、表ソフトラバー一択の場合が多いですね。
ところが、競技用のラケットは、球がよく跳ね、裏ソフトラバーの場合の回転量は比べようもありません。
これから部活を始めよう、ということで卓球部の扉を叩いた新入部員などは、
顧問の先生から「明日からラケットを持って来いよ」などと言われ、レジャー用のラケットを買ってしまうこともあるようです。
公立の学校の場合だと、顧問の先生も卓球経験者とは限りませんから、部員には用具を買うべき店名なども伝えて欲しいものですね。
ラバークリーナーの使いすぎが招く悲劇
「ラバークリーナー」なるものの存在をご存知でしょうか?
卓球プレーヤーの方以外には馴染みの薄い言葉かもしれませんね。
ラバークリーナーは、文字通りラバーの表面をキレイにするための物で、卓球専門店や大きめのスポーツ用品店などで手に入れることができます。
このラバークリーナー、なぜか卓球初心者の方こそがよく使っています。
卓球専門店の店員さんから勧められるままに購入するパターンが多いようです。
クリーナーを使うこと、それ自体はラバーの表面を常にキレイに保てるので良いことなのですが、
練習や試合の度にクリーナーを使っていると、逆にラバーの表面が白くなり、俗にいう「ラバーが死んだ状態」になってしまうんですね。
毎日クリーナーを使うことは、頻度的にやりすぎですので、少なくとも2〜3回に1回程度に抑えるようにしてみてください。
筆者の所属していたクラブには、一流選手がたくさんいましたが、不思議なことに、強い選手ほどラバークリーナーを使っていませんでした。
ラバー表面の汚れは、ガラスを拭くときのように「はぁーっ」と息を吹きかけて、手の平でこするだけでも、
かなりキレイになりますので、よければ試してみてくださいね。
卓球あるある〜プレー編〜

「あるある」は、用具だけにとどまりません。
卓球の試合をよく見ていると、レジャースポーツとして楽しんでいるときには見られない、トリッキーなプレーが多々あります。
トリッキーな見た目からも判断できますが、プレーの中にはある程度の習熟度が必要なものも。
ここではプレーに関する「あるある」を紹介していきます。
ラケット反転あるある
みなさんは、卓球選手がラケットをクルクルと回すのをご覧になったことはありますか。
このラケットをクルクルとする動作は「ラケット反転」と呼ばれています。
ここで、ラケットの種類に注目して欲しいのですが、卓球のラケットには、昔ながらのペンホルダーラケットと、
比較的新しいシェイクハンドラケットがあります。
実際にラケットを持つアクションをしていただければ分かるのですが、ラケットをスムーズに反転するにはペンホルダーが適しています。
反転する際に、軸となる指がないとスムーズに回転することができないからなんですね。
もっと言えば、ペンホルダーの中でも、いわゆる「中国式ペン」と呼ばれる、ラケット両面にラバーが貼ってあるタイプのもので使われる技術です。
ただ、ペンホルダーであっても、これはかなりの高等技術。
特に、経験の浅い選手だと、反転しようとしてラケットを落としてしまい、その音が試合会場にこだまする、なんてこともよくあります。
しかし、難易度の高い技術であるが故に、反転をマスターすると対戦相手の脅威となることができるでしょう。
自分のプレーが思ってたのと違う
「強くなりたい!」という志を持った卓球選手であれば、自分のフォームを気にしたことは何度もあるでしょう。
その際に役立つのが動画の撮影です。
ビデオカメラを持参し、試合中や練習中に自分のプレーを撮影している選手は、卓球界では珍しくありません。
最近では、スマホを使って簡単に動画撮影をすることもできるので尚更ですよね。
さて、この撮影した動画を見て、自分のフォームのチェックを行うわけなのですが、初めて自分の動きを見た人は必ず衝撃を受けます。
それは、あまりにも自分が「こうだ」と思っているプレーと、動画に収められたプレーがかけ離れているからなんですね。
誰に言うでもなく、「自分のプレーはこんなに不恰好ではない」と弁明したくなるほどです。
どんな競技にも当てはまりますが、自分の動きを客観的に捉えるのはとても重要なこと。
初めは目を覆いたくなるような気持ちになりますが、何度か繰り返していくとフォームも改善され、
「自分もなかなか悪くない」と思えるようになりますので、ぜひ動画撮影は続けて欲しいものです。
まとめ

卓球をプレーしたことのある人なら、「あ〜、分かる分かる」という内容もあったのではないでしょうか。
ここに挙げた「あるある」は、ほんの一例で、学校の部活や地域のクラブなど、その組織にしかないローカル「あるある」も存在するでしょう。
また、「あるある」を多く見つけられるということは、あなたの経験値が上がっているということも意味します。
単純に探すのも楽しい、「あるある」を、見つけてみてくださいね。