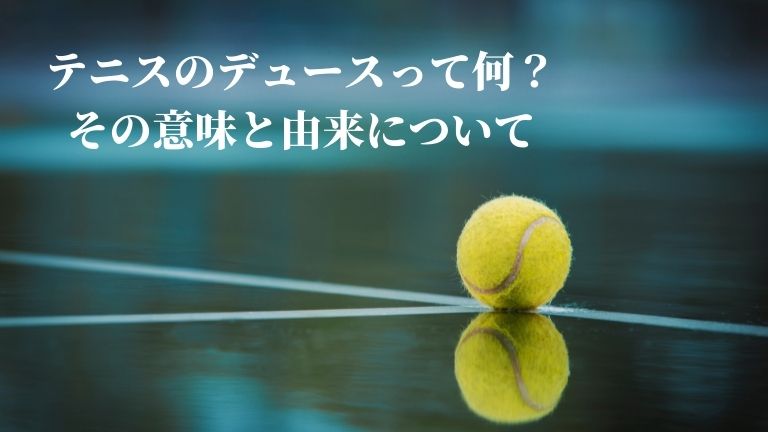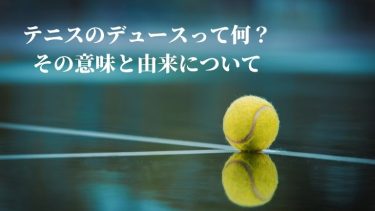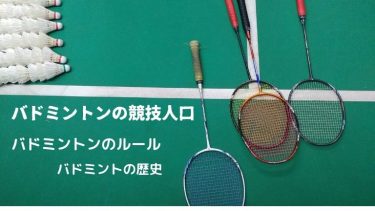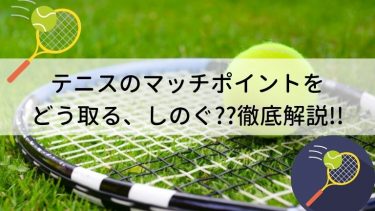テニスの試合を観戦していると、得点のコールの際に「デュース」と言われることがあります。
今回のこの記事では、その「デュース」の意味と由来について紹介します。
「デュース」の意味

「デュース」は英語表記で「Deuce」となりますが、
テニスなどのスポーツでゲームポイントに対して残り1ポイントの状態で同点になることを言います。
相手チームとの点差がある場合には、次の1ポイントの獲得でゲームを取れますが、
「デュース」の場合は2ポイント連取しないと「デュース」が繰り返されることになります。
この「デュース」というルールは元々はテニスに対して定められたものですが、バレーボールにも採用されています。
バレーボールはバドミントンから派生したスポーツとも言われていますが、テニスのルールを踏襲しているとも言われています。
また、バドミントンや卓球では、「デュース」という用語はルール上は定義されていませんが、
同点からの2ポイント連取というルール自体は存在しているため、会話の中の言葉として使われることはあります。
「デュース」の語源

「Deuce」という単語には、トランプの2の札、サイコロの2の目など、2という意味が含まれています。
この言葉がテニスなどの「デュース」にも使われているのですが、
元々の語源はフランス語で「a deux le jeu」という言葉(両者は同点である)から来ているという説もあります。
また「deux」もフランス語で「2」という意味であり、あと2点必要というところから派生したとも言われています。
いずれにしても、「2」という数字が語源にあるようです。
テニスにおける「デュース」

テニスでは、サーブ権を持っている選手が左右交互にサーブを打ちますが、右側を「デュースサイド」、
左側を「アドバンテージサイド」と言います。
この呼び方は「デュース」のルールからきています。
ゲーム内の得点が40-40になると「デュース」となりますが、その際必ず右側からサーブ・レシーブをするため、
右側のエリアは「デュースサイド」と呼ばれます。
また、どちらかが点を取ると、「アドバンテージサーバー」もしくは「アドバンテージレシーバー」となり、左側からサーブ・レシーブをします。
それゆえ、左側のエリアを「アドバンテージサイド」と呼びます。
また、ゲームカウントについても通常7ゲーム先取で1セットが基本ですが、6-6となった場合は2ゲーム差が付くまでセットが続けられます。
過去最長の試合は、2010年のウィンブルドン選手権でのジョン・イスナー選手とニコラ・マユ選手の試合ですが、
最終の5セットにて2日に渡る日没中断を経て、ゲームカウント70-68でイスナー選手がセットを取り勝利をしています。
テニスでは試合時間短縮のためにタイブレーク方式も採用されていますが、大会によっては非採用となっており、
このような長時間の試合がしばしばみられます。
タイブレーク中の「デュース」

試合時間短縮のためにタイブレーク方式が採用されていると紹介しましたが、そのタイブレークにも「デュース」は存在します。
タイブレークは、まず最初にサーブを打つ選手がデュースサイドから1本打ち、
次からはアドバンテージサイド→デュースサイドという順番で2本打つのを繰り返します。
そして、どちらかが7ポイントを先取した時点で終了し、そのセットを獲得できます。
しかし、そのポイントが6-6になると「デュース」となり、2ポイント差が付くまで続けられることとなります。
通常のゲームと異なるのは、両者のポイントの合計が6の倍数になるとコートチェンジが行われることです。
「デュース」無しの試合:ノーアドバンテージ方式

更に試合によっては円滑な試合進行を目的として「デュース」無しで行われる場合もあります。
ノーアドバンテージ方式と呼ばれていますが、その場合は40-40になったとしても、次の1ポイントでゲームが決まります。
そして、ノーアドバンテージ方式の場合は、40-40時点のサーブ・レシーブはデュースサイド固定ではなく、
レシーバーがどちらのサイドでレシーブするか選択できます。
レシーバーに選択権があるため、サーバーの苦手なサイドを選ぶこともでき、一つの駆け引きでもあります。
まとめ

「デュース」というのは、追いつかれた側からすると流れを引き戻すための気持ちを入れ替えるタイミングであり、
追いついた側からすると一旦ポイントを失ってもいい状況になったという安心感が生まれる状況でもあります。
いずれにしても、試合の流れが変わる大きなポイントとなります。
このような駆け引きに注目しながら、試合を観戦するとより楽しめると思います。