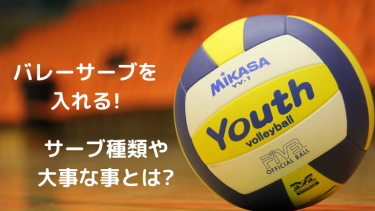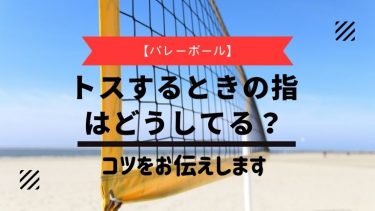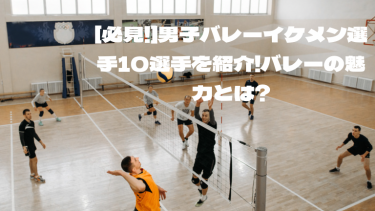バレーの試合観戦はドキドキと感動が止まらないですよね。
日本のバレーは特につなぐバレーなので、取れないだろうと思われるボールを拾うシーンでは、かなり感動します。
バレーは展開が早いので、観戦中は目が離せない状態になるかたも多いのではないでしょうか。
とても楽しいスポーツバレーボールですが、元々どこの国のスポーツなのか、バレーボールの歴史など気になったことはありませんか?
今回は、そんなバレーについて知っていて得するような面白雑学を調べてまとめてみました!
これからのバレー観戦でもバレーをやっているという方でも、バレーの雑学を知っているとまた違ったバレーが見えてきますよ♪
バレーの歴史は100年以上!

なんとバレーは100年以上前に作られていたそうですよ!
100年以上前の暮らしなどもなかなか想像できませんが、バレーボールはそんな時代で出来上がったのかと驚きです。
とても長い歴史がありますが、一体誰がどのようにしてバレーボールを作りあげたのでしょうか?
そして、今のバレーボールと一体何が変わったのかも調べてみましたのでご覧ください♪
バレーボールはアメリカで生まれた
当時、同じ室内での球技はバスケットボールがとても人気でした。
しかし、バスケットボールはハードなスポーツなので、その動きについていけるのは若い世代だけと限定されてしまいます。
バスケットボールはコートの端から端まで走るので、体力のある若者しかできないといったイメージでしょうか。
ぶつかり合ったりもするので確かに老若男女幅広くできるスポーツとはかけ離れている気がします。
1895年明治28年に幅広い世代でも何か楽しめる球技スポーツはないかと考えついたのが、「バレーボール」です。
当初は、動き回る白熱したスポーツではなく、レクリエーションのようなので競技ではなかったようですね。
当時の名前は「ミノネット」
バレーボールはテニスやバドミントンをヒントにして考案したそうです。
当初はバドミントンのネットを使ってプレーしていたため、考案された当時「ミノネット」と呼ばれていました。
その後、ルールもいろいろ変わっていき、最終的に「バレーボール」となりました。
「バレー」はテニスボールが落ちる前に相手へ打ち返すことの「ボレー」から来ているそうですよ。
ミノネットってなんだか聞いてもどんなスポーツなのか想像できないです!
もし、このまま名前が変わっていなかったら、今のバレーボールはまた違ったスポーツになっているかもしれませんね!
初めは人数無制限だった!

バレーといえば6人制やローテーションなどがあたりまえになっていますよね。
しかし、バレーができた当初アメリカでは人数無制限だったそうですよ!
無制限ってなんだか逆にやりずらい気もしますが。笑
ではなぜ無制限から、今の日本が6人制に変わったのでしょうか。
バレーボールの人数についての歴史を調べてみました!
最初の16人制を決めたのは日本
日本にバレーが入ってきたのは、1910年明治43年のころです。
このとき、発祥の地アメリカでも人数に関するルールはなく、人数も無制だったので、日本では16人制と決めました。
そのあとは、ルールの見直しで、12人になり、9人にまで減り、9人制が定着し日本では9人制のバレーが主流となったようです。
人数変更されていった歴史を表にまとめてみました。
| 1910年 (明治43年) |
日本 | 16人制と決める。 |
| 1920年 (明治53年) |
アメリカ | 6人制ローテーションルール確立。 |
| 1920年 (明治53年) |
ヨーロッパ | アメリカの影響で6人制ローテーションルールでヨーロッパにバレーが入ってくる。 |
| 1927年 (昭和2年) |
日本 | 日本でのルール見直し後9人制が確立。 |
| 1947年 (昭和22年) |
国際バレーボール連名fiveが設立。 ルールは6人制を採用。 |
|
| 1951年 (昭和26年) |
日本 | 他の国より遅く加盟。 9人制だった日本も6人制を導入。 |
国際バレーボール連名five設立後は、人数以外にもネットの高さや、コートの広さなどが決まりました。
9人制と6人制の違いは?
国際バレーボール連名five加盟後6人制が導入された後も9人制はママさんバレーの間で愛されています。
そこで、6人制と9人制のバレールールの違いはなにがあるのかを調べてみました。
・ネット高さ
・ライン
・アンテナ位置
・マッチ数
・1セットの点数
・ローテーションの有無
・サーブ
・ブロック
バレーを進化させた「東洋の魔女」

アメリカで生まれたバレーボールですが、ほとんどの技が日本から生まれたことをご存知でしょうか?
1964年の東京オリンピックでは女子バレーが正式種目に決定し、初代金メダルを獲得したのは日本です!
そこで繰り広げられた日本独自の沢山の技に、相手チームたちは圧倒され日本は「東洋の魔女」と呼ばれるよになりました。
そして東京オリンピックで日本女子バレーが金メダルを獲得してからの日本は空前のバレーブームとなったようです。
では、なぜ日本バレーが強く成長したのでしょうか?
日本が考え出した技と、強さの秘訣を調べてまとめてみました。
回転レシーブ
「東洋の魔女」を育て上げた大松博文監督は「起き上がりこぼし」をヒントにこの技を作りました。
滑り込んでのレシーブは、体制を整えるのに時間がかかってしまうので体制が整わず、次への対応ができないとボールを繋げることはできません。
しかし、回転レシーブはすぐに体制を整えることができるので、次の展開へとすぐに対応することができます。
回転レシーブは現在基礎になっていますので、バレーを始めたときはみんなが経験するかもしれませんね。
時間差攻撃
速攻の時間差攻撃はもともと1972年に行われたミュンヘンオリンピックに向け、男子バレーボール日本代表たちが考案したのですが、「東洋の魔女」も時間差攻撃を取り入れることにしました。
技以外での強さの秘訣
「東洋の魔女」が強かった理由は、ズバリかなりの練習量です。
・昼3時〜翌朝2時まで(バレー練習)
1日10時間とかなりの練習量ですよね。
10時間練習でバレーの技や心まで鍛え上げられたのかと思います。
長い練習時間で強い技が出来上がり、バレーを進化させたのかもしれませんね。
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、バレーの雑学で歴史について、日本のバレーが進化させたということについて調べてまとめてみました。
バレーができたばかりの頃は人数が無制限だったと言うことには、少し驚きました。
そして、日本のバレーが今のバレーでも使われている技を作ったということは日本人として誇らしく思いますね。
練習時間は、現在だとブラックになってしまいますが。笑
バレーの雑学は調べれば調べるほどバレー沼にハマっていくと思います。
これからバレーを始めるというかたも、今すでにバレーをしているというかたもバレーの雑学を見るとまた違ったバレーが見えてくるはずです。
最後までご覧くださり、ありがとうございました。