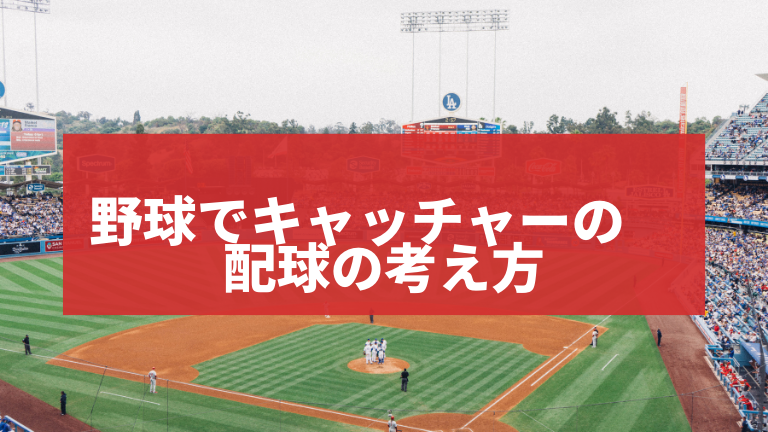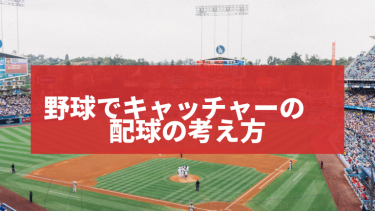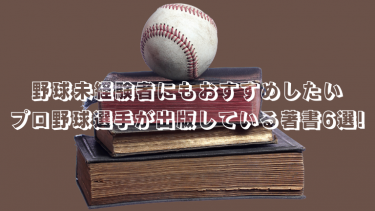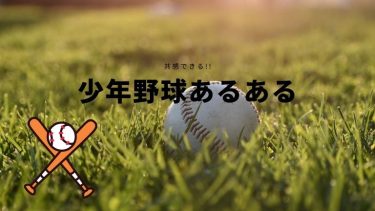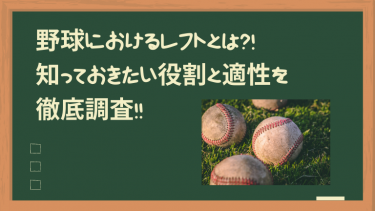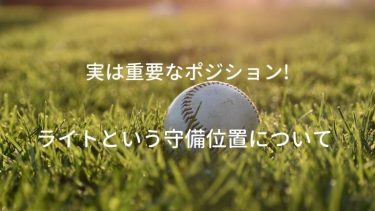テレビで野球を見ていると、キャッチャーがピッチャーにサインを出しているのがわかります。
キャッチャーは、唯一グラウンドを全体を常に見えるポジションになるのです。
試合の流れやピッチャーの調子やバッターへの配球などを、常に考えていなければなりません。
それほどキャッチャーは重要なポジションになるのです。
では、キャッチャーがリードするとキャッチャーが配球を考えるでは違いはあるのでしょうか。
また、配球には基本はあるのでしょうか。
野球でキャッチャーのリードと配球の違いって何?

TVで野球を見ていると
「今日のキャッチャーのリードはいいですね。」
「今のキャッチャーの配球は良かったですね。」
などという話を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
では、野球でリードと配球の違いとは何がちがうのでしょう。
- リード:ピッチャーの状態を見極めて投球内容の組み立てを考え、更に試合全体の流れを考える。
- 配球:ピッチャーの状況からバッターをどうやって、アウトにできるのかを考える。
大まかに野球でリードと配球を分類すると、このような違いが判ります。
常に野球の試合の中で、キャッチャーピッチャーの状況を考えながら試合の流れを組み立て、
更に配球で1人1人のバッターをどうやってアウトにするかを考えていることになるのです。
リードと配球の違いを簡単に説明!
キャッチャーは、試合の中でリードと配球を常に考えていることになります。
リードと配球の違いが、よく分からないという方もいるでしょう。
簡単に説明するとリードは試合を大きく捉えることになります。
リードで試合を大きく捉える中に、配球がありバッターとの対戦を行っていると考えるとわかりやすいはずです。
大きい円がリードで、その円の中に配球という小さい円があると考えると理解しやすくなります。
キャッチャーは、野球をする上で常に頭を働かせながら行動するポジションという事になるのです。
野球でキャッチャーの配球の基本ってあるの?

野球でキャッチャーの配球の基本の見本となるのが、プロ野球ではないでしょうか。
プロ野球のキャッチャーはある程度、ピッチャーをリードしながら、
ピッチャーの今日の出来を考えて配球とバッターの狙い球を読みながら配球を考えることになります。
キャッチャーの配球を見ていても基本ってあるのか? と思うかもしれませんが、ピッチャーの状態にもよりますが、配球の基本はあるのです。
配球の基本
ストライクゾーンの真ん中からバッターから見て遠くにボールを投げさせることが配球の基本になります。
なぜなら真ん中からバッターの遠くにボールを投げさせることで、長打を打たれる可能性が少なくなるからです。
外角球が好きなバッターも一ますが、配球の基本は真ん中からバッターから遠いストライクゾーンを中心の組み立てになります。
なぜ、配球の基本はバッターから遠くで、バッター寄りではダメなのか?
バッターに近いボールは内角といいます。
内角球がダメという訳ではありませんが、内角球は長打を打たれる可能性が高くなる傾向があるのです。
バッターの技術になるのですが、腕をたたみながらスイングすることになるのですが、
力をバットに乗せやすくバットの芯に当たる可能性が高くなり長打になる可能性が出てくるからになります。
キャッチャー的には、試合展開を優位に運びたいわけですから、配球はどうしても真ん中からバッターから遠いゾーンにボールを投げさせることで、
バッターのスイングの力を削ぐことで打ち取る可能性があるからです。
配球の基本はバッターから遠い所にボールを集中させることで、内角球で勝負するという配球も考えもできます。
配球は、キャッチャーとバッターの配球の読みが勝負所といってもいいでしょう。
基本の忠実の配球でバッターから遠いボールで勝負するのでも問題は有りませんが、それだとバッターに読まれてしまう可能性があるのです。
基本に忠実はかまわないのですが、配球はバッターから遠いノール一辺倒では、確実にヒットにされる可能性も出てきます。
キャッチャーは、バッターの調子やバッターの得意なのが内外角を知っておく必要があり、
更にはピッチャーの今日の調子も把握しながら配球を決めなければならないのです。
野球でキャッチャーの配球の基本となるボールは何?

キャッチャーはピッチャーの今日の調子を把握しなければならないのですが、ピッチャーの持ち球をも念頭において配球を決めていきます。
しかし、配球の基本となるボールは、ずばりストレートです。
ストレートの出来によって、キャッチャーの配球が生きてくることになります。
ストレートに伸びの有無で、勝負球にできるかどうか、見せ球にするかを決めなければならないからです。
キャッチャーの配球が良くても、ピッチャーのストレートの出来次第で試合の流れがつかめないという事が野球では、多々あります。
キャッチャーは、常にストレートを基本に配球を考えて試合の流れを考えていることになるのです。
ストレートが良い状態ならば、相手のチームの打順が2巡するくらいまでは、勝負球にストレートを用いた配球をします。
ストレートが悪い状態では、初回からストレートを見せ球にして変化球で勝負するようになってくるのです。
キャッチャーの配球には、ピッチャーの良しあしも関わってきます。
ある程度ストレートの出来が良い場合は、長い回を投げることが可能ですが、
ストレートが悪い場合には、ピッチャーの交代を考えながらの配球をしなければならなくなるのです。
配球はキャッチャーの考えが大きく反映される?
ピッチャーの持ち球をうまく使って配球を考えるのがキャッチャーの役割の1つです。
ピッチャーの持ち球
- ストレート
- カーブ
- スライダー
- チェンジアップ
- フォーク
この5つが多くのピッチャーの持ち球の主流になります。
ストレートを基本に、そのピッチャーの勝負球で三振を取りに行くことがベストな選択になるのです。
外角中心にストレートの配球をして、ストライクゾーンから外に逃げていくスライダーという配球で三振を狙うのも1つの配球のパターンになります。
また、外角に変化球を集めて、内角にストレートでバッターに内野ゴロを打たせるのも配球のパターンなのです。
配球は一辺倒ではなく、バッターとの読みの勝負で、いかにバッターをアウトにできるかが、キャッチャーの配球の考え方になります。
変化球が得意なピッチャーの場合には、決め球には変化球を使うとバッターに思わせながら、ストレートで勝負してくる配球も考えられるのです。
配球は常に試合の流れを読みながら、同じバッターには同じ配球をしないことで、バッターの読みを外させることもしなければなりません。
キャッチャーが配球を決める前に、バッターをチラチラ見ていることがありますが、それはバッターが何を考えているのかをチェックしているのです。
さっきよりバットが若干短いから変化球を待っている・足のスタンスが若干広ければ、ストレートを狙っているなど、
バッターの癖も考慮に入れて配球を決めていることになります。
まとめ

野球でキャッチャーの配球について紹介してきました。
- リードはピッチャーの状態を見極めて投球内容の組み立てを考え、更に試合全体の流れを考える。
- 配球はピッチャーの状況からバッターをどうやって、アウトにできるのかを考える。
- 配球の基本はストライクゾーンの真ん中からバッターから見て遠くにボールを投げさせる。
- 内角の配球をする場合には、長打を打たれる可能性があるので、外中心の配球が基本となる。
- 配球をする上で基本となるボールはストレート。
- キャッチャーは配球を考えるうえでバッターとのボールの読みの勝負をもしている。
などという事がわかりました。
配球については難しく感じますが、TVで野球観戦している場合には画面の下に配球の枠が表示されているので、
これを見ながら次のボールの配球を考えて野球の試合を楽しむことができます。