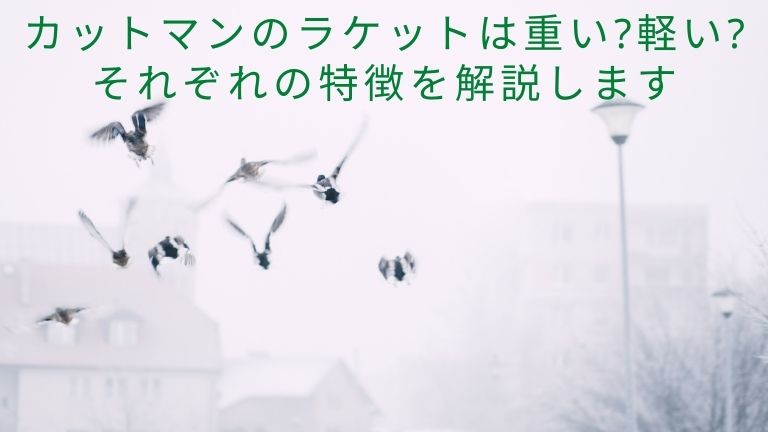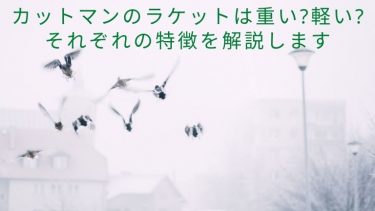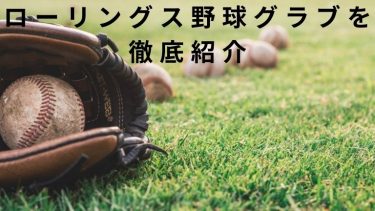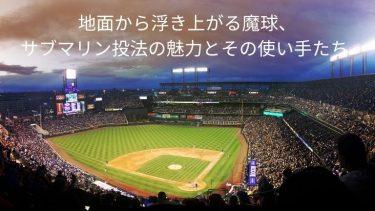卓球のプレースタイルの中でも、ひときわ目立つカット主戦型。
その立役者であるカットマンですが、カットマンのラケットに対してどのようなイメージを持っていますか。
卓球をプレーしたことのある人ならご存知でしょうが、カットマンのラケット面は、攻撃マンより大きいのが一般的です。
しかし、なぜラケット面が大きいのかについて考えたことのある人は少ないかもしれません。
ラケット面が大きいと、当然ラケット面の小さいラケットよりも、総重量は重くなってしまいます。
この記事では、そんなカットマンのラケットの重さや、軽いラケットを使うメリットについて解説していきます。
カットマンのラケットが重い理由

前述の通り、カットマン用のラケット面は、攻撃マン用のラケット面より大きく作られています。
卓球界では、ラケットそのものの重量はカットマン用のラケットが一番重いのです。
ではなぜ、カットマン用のラケットは面が大きく、そして重量が重くできているのでしょうか。
それには次のような理由があります。
面が大きいと回転がかけやすい
卓球のボールに強い回転をかけるには、できるだけ長い時間、ラバーの表面にボールを食い込ませる必要があります。
それでは、面の大きいラケットと小さいラケットでは、どちらの方が回転がかかりやすいでしょうか。
当然、面が大きい方が貼ってあるラバーの大きさが大きいので、より長い時間ボールをラバーに食い込ませることができます。
カットマン用のラケット面が大きいのは、これが理由なのです。
ラケットが重いとスイングの助けになる
カットマンのラケットスイングは、攻撃マンのそれとはベクトルが違います。
一般的に攻撃性のボールは、後ろから前にスイングします。
しかし、カット性のボールは大きく、上から下へスイングするのです。
動画などでカットマンのスイングを見て、実際に試すと分かりますが、ちょうど薪を斧で割るような感じでスイングします。
そのため、英語ではカットマンのことを「チョッパー」と言います。
この上から下に振り下ろす動作ですが、手に持った用具(ここではラケット)に、ある程度の重さがあった方が、スイングスピードが上がるのです。
そのため、プレーヤーに特別な筋力がなくても、回転量の多いカットボールを打つことができます。
カットマン用のラケットの中には、あえて総重量をとても重く作っているものがあります。
Nittaku社の「剛力」というラケットが、とても重いことで有名です。
トッププロの中には使いこなしている選手もいますが、重いラケットを操ることができれば、まさに鬼に金棒と言えるでしょう。
軽いラケットを使うメリット

それでは、カットマンのラケットが軽くなると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
スイングスピードが上がる
カットマンが回転量の多いカットボールを打つには、上から下へのラケットスイングを可能な限り速くする必要があります。
先ほどは、ラケットの重量がスイングスピードを上げる助けになる、と解説しました。
それはそれで事実です。
しかし、あまりにラケットが重いと、そもそも振り抜くことが難しい場合もあります。
ラケットが重すぎるせいで、スイングスピードが遅くなってしまうと、
ラケットの重さで増されたスイングスピードが帳消しになってしまう場合もあります。
その点、ラケットの総重量が軽いと、あまり筋力を使わずとも速いスイングをすることができ、
結果的に下回転量の多いボールを放つことができるのです。
また、カットマンは台から離れた位置でカットすることが多いですので、対戦相手は、カットボールの回転量を正確に把握することができません。
同じようなスイングで、下回転量の多いボールとナックル性のボールを出し分けることができれば、試合を優位に運ぶことができるでしょう。
スタミナを温存できる
カット主戦型は、あらゆるプレースタイルの中で一番体力を使います。
カットマンは、通常台から遠く離れた位置で、相手の攻撃をカットしています。
すると、当然ですが対戦相手はネット側にボールを落とそうとします。
前後に揺さぶりをかけてくるわけです。
攻撃型の選手は、台の近くでプレーすることが多いので前後への移動で体力を使うことはあまりありません。
このように、カットマンはただプレーするだけでも、とてもスタミナが必要なのです。
他のプレースタイルより、スイングが上下に大きいこともスタミナが必要な要因の1つです。
そこで、ラケットをできるだけ軽いものにすれば、スイングによるスタミナ消耗を抑えることができるのです。
軽いラケットを実現するために

カットマンがラケットを軽くするために、現実的なのは、バック面のラバーを粒高に変えることです。
多くのカットマンはフォア面に裏ソフトラバーを貼っています。
フォア面に裏ソフトを貼った状態で、バックにも裏ソフトを貼ってしまうと、重量が増えてしまいます。
カットマンが粒高ラバーを貼ることで、次のようなメリットがあります。
変化幅の大きいボールが打てる
来たボールを粒高ラバーで当てて返すと、回転を反転することができます。
それでは、来たボールを粒高ラバーでカットして返すと、どのような回転のボールになるのでしょうか。
実は、相手のドライブ回転が強ければ強いほど、その回転を利用し、強力な下回転のカットとして返すことができるのです。
もちろん、裏ソフトラバーでも、とても切れた下回転カットを繰り出すことは可能です。
しかし、裏ソフトの場合だと、相手の球の回転量をそのまま利用することはできず、
逆に相手の強烈なドライブ回転の影響を直に受けてしまうのです。
そのため、回転量の多いドライブボールであれば、中途半端なカットでは返球できなくなってしまいます。
しかし、粒高ラバーであれば、相手の回転を利用することができるので、比較的簡単に切れたカットをすることができます。
その上、「切る、切らない」といった操作も比較的容易です。
対戦相手としては、とても切れた下回転カットの後にナックルカットを打たれることになるので、混乱してしまいます。
多くのカットマンが、バック面に粒高を貼っていますが、その背景にはこのような理由があるのです。
プッシュなど、多彩な戦い方ができる
粒高でできるのは、切れた、もしくは切れていないカットだけではありません。
前陣攻守切り替え型に見られるように、ラケットを小さく動かしてのプッシュ打法も繰り出すことができます。
粒高のカットだけでも厄介なのに、プッシュまで織り交ぜられたら、対戦相手としてはたまったものではありません。
このように、相手のミスを誘いながら、チャンスボールはフォア面でスマッシュする場面はとても格好良いものです。
ラバーそのものが軽い
カットマンが粒高ラバーを使う利点として、粒高ラバーは、ラバーそのものが飛び抜けて軽い、ということが挙げられます。
一枚ラバーという、今ではほとんど使われていないラバーを除けば、ラバーの中で一番軽いのは粒高ラバーです。
軽さだけでも優秀なのに、前述したようなメリットもついてくるので、多くのカットマンが粒高ラバーを選んでいるのでしょう。
まとめ

カットマンのラケットが重い理由や、軽いラケットを使うことのメリットについて解説してきました。
スタミナ勝負のカットマンの方は、ぜひ参考にしてみてください。