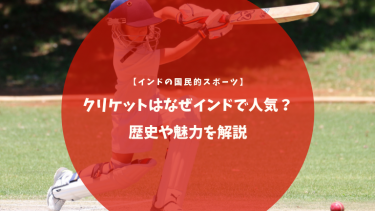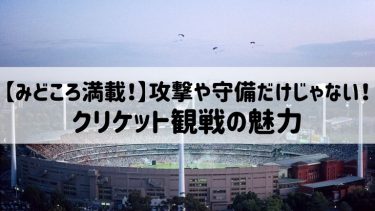聞いたことはあるけれど、ルールは知らない人が多いクリケット。
実はクリケットには他のスポーツにはない、クリケット独自のティータイムという時間が存在します。
クリケットを知らない人は、あまり聞いたことがないかもしれませんね。
今回は、クリケットのティータイムとは一体どのようなルールなのかを解説します。
クリケットとは

日本では馴染みがないのでマイナーなスポーツなイメージですが、実は世界での競技人口は約1億5千万人もいるんです。
これは競技人口ランキング世界第2位で、世界的にはサッカーに続いての人気となっています。
野球やバスケットよりも競技人口が多いだなんて、意外ですよね!
ちなみに、日本での競技人口は約4000人です。世界的には人気なのですが、日本ではあまり普及していないことがわかります。
クリケットが盛んな国には、発祥に地イギリスの他にもインド・オーストラリア・バングラディッシュなどがあり、その存在は多くの国の人たちに愛されています。
野球の起源とも言われている
基本的には平たいオールのようなバットでピッチャーから投げられる球を打ち返すような、野球に非常に近いスポーツです。
クリケットの歴史はとても古く、実は野球よりも早くその存在はあったようです。
およそ16世紀ごろから始まったとされるクリケットは、野球の起源とも言われています。
野球と似ていると思っていましたが、本当は逆で野球がクリケットに似ていたのですね。
ルールは野球と同じ?
クリケットのルールはご存知でしょうか?
野球の起源とも言われているので、一見ルールも似ているような気がしますが、実は似て非なるもの。
日本ではメジャーである、野球のルールと比べながら簡単にご紹介いたします。
クリケットのルール
1チーム9人制の野球に対し、クリケットは11人制でおこないます。
守備側のチームは投手(ボウラー)が1名・キャッチャー(ウィケットキーパー)が1名・野手(フィールダー)が9名の合計11人での構成です。
表裏で攻守を切り替えを9回繰り返して競うのが野球であるのに対し、クリケットは攻守の切り替えは一回のみです。
また、野球では3回アウトを取れば交代であるのに対し、クリケットではなんと10回アウトを取ったら交代という恐ろしいアウト数なのです。
クリケットを野球の回数で表すと、たったの1回表裏で試合は終了してしまう事になります。
そう考えると、なんだかすぐに試合が終わってしまいそうに思えますよね。
ですが、この10回アウトをとることが難関で10回アウトを取るまでに半日〜1日かかってしまうことがあります。
攻撃側は1番から11番までの打順を決め、順番に打席に立っていきます。
ここで面白いのが、攻撃側は必ずしもボールを打たなくても良いというところです。
アウトにさえならなければ良いので、そうならない為にボールを見送ることも可能です。
10人をアウトにすることも大変なのに、まず1人をアウトにするところから既に難しいのですね。
野球はピッチャー・キャッチャー・内野手・外野手など、ポジションが固定されています。
選手は自分のポジションを伸ばすように練習に取り組みますよね。
クリケットでは、10人をアウトにするまで1人のボウラー(投手)が続けて投げることは体力・身体的にも困難です。
そこで、投手は6回投げる事に次の人へ交代することになっています。
投手を誰か固定して決めるのではなく、全員が順番に投手になっていくのですね。
選手11人の全員が、打者と投手両方の役割をしなければなりません。
選手全員がどちらのポジションを楽しめることも、クリケットの魅力の一つなのかもしれませんね!
ティータイムってなに?

クリケットに存在する独特なルールが、この「ティータイム」です。
クリケットのルールであるティータイムとは言葉の通りの意味で、試合の休憩時間中にランチや紅茶を楽しむことです。
ティータイムと聞くと、「え?試合中にお茶を飲むの?信じられない!」と驚く人も多いことでしょう。
サッカーやバスケットの試合のように各チームごとにベンチに戻って10分休憩をして、その間に水分補給・敵に聞こえないように自陣で作戦会議をする…。
そんな私たちの想像す試合の休憩時間とはかけ離れていますよね。
なぜ、クリケットにはわざわざお茶を飲む時間が設けられているのでしょうか?
その理由は主に3つあります。
試合時間が長い
クリケットの試合時間はどのくらいだと思いますか?
実はクリケットは1試合に午前中に2時間、午後に2時間、夕方にも2時間もかかる超ロングタイムなのです。
1試合に1日がかりとは…なかなか他にはないスポーツですね。
これは、10回アウトを取らなければ攻守の交代とならないことや、全員に打順が行き渡るまで終われないことが要因と言えるでしょう。
世界での最長の記録としては、1試合になんと5日間もかかったことがある程です!
これほど長い試合時間となると、試合の間に休憩時間を挟まなくては疲れてしまってとてもやっていられませんね。
なので、クリケットの基本としては
などのように途中に長い休憩が入るのです。また、試合時間によっては2時間毎にティータイムが入ることもあります。
クリケットの面白いところは、休憩時間もただ休む時間ではなく敵味方や審判も関係なくランチやお茶を一緒に食べて飲んで楽しむところです。
試合には出ていないけど選手の家族も一緒にテーブルを囲んだりもするそうです。
なんだか、応援する側も楽しくなりますよね。
ティータイムは大切な文化
もともとはイギリスの貴族たちが始めたとされているクリケット。
時間に余裕がある貴族たちの遊びが発祥なので、試合時間も気にせずゆっくりと行われているなどといった説もあります。
また、紅茶の国イギリスではティータイムを重要視する文化が根強く存在しています。
ティータイムが日常的に存在し心と体を豊かにしてくれる時間として現在もとて大切にされ、その心は競技にも取り入れられているのですね。
交流の場とされているから
イギリスではクリケットは国技であり、紳士的なスポーツとして考えられます。
名門学校でも、体育の時間にクリケットが授業の一環として取り入れられる程です。
その為、もちろん勝負の勝ち負けも重要な事なのですがそれと同じくらいに、人との交流も大事に思われています。
勝負の場と社交の場と、2つの意味が合わさっているのですね。
なので、ティータイムやランチタイムの時には敵味方で別れることなく、その場にいる全員で楽しくお茶を飲んで会話を楽しみます。
おしゃべりが好きな人が多く、誰とでも気さくにコミュニケーションが取れて、社交的なイギリス人らしい考え方ですね。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
最初はお茶を飲むなんて、楽な競技なんだろうなと思われたかもしれません。
ですが、実は1試合に1日もかかってしまう程の大変な競技であるが故のティータイム制度でもあったのですね。
このティータイムがあることによって敵も味方も関係なく交流を楽しめるところは、クリケットならではの魅力や楽しさが隠されているのかもしれません。
日本ではまだまだマイナーなスポーツであるクリケットですが、その競技人口は年々増え始めています。
一度経験してみると、案外ハマってしまうかもしれませんよ。