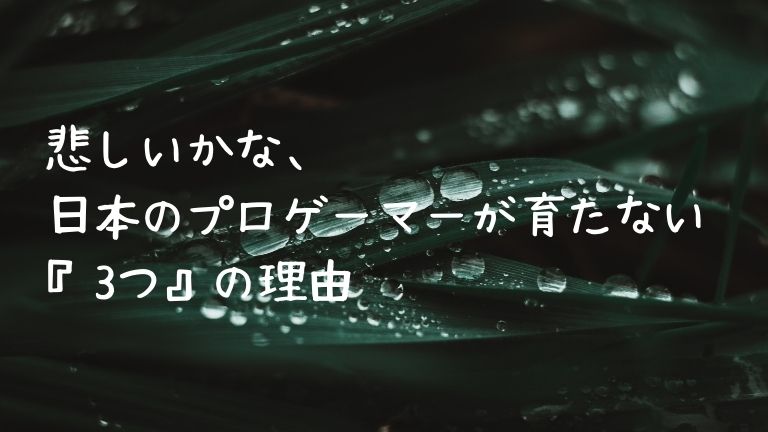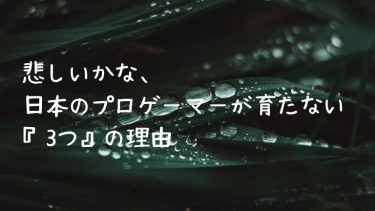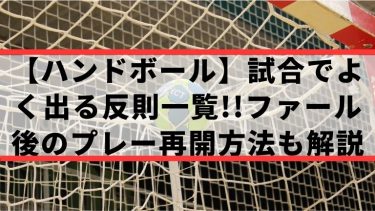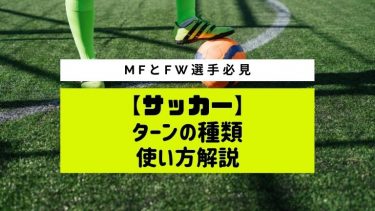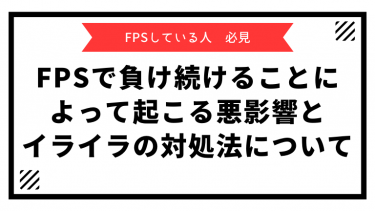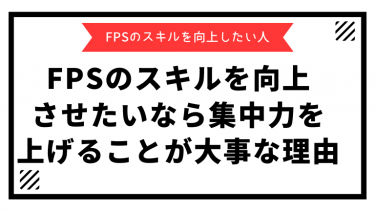近年、日本でもようやく「eスポーツ」が浸透してきました。
野球、サッカー、レース、格闘など様々な種類のゲームで対戦し、しのぎを削る姿は、まさにスポーツそのもの。
最近では、オンラインで対戦できる環境が整ったので、ますますその人気に拍車がかかっています。
しかし、日本のeスポーツの強さは、海外に比べて、弱いと言わざるを得ないのが現状です。
なぜなのでしょうか?
日本のeスポーツの歴史、置かれている状況を、海外勢とも比較しながら、日本のプロゲーマーが弱い理由を掘り下げていきましょう。
✅月額:3,480円 ※個別登録より「1,270円おトク」
✅「年間1万試合以上のライブ配信」のDAZNスタンダード
✅「国内作品見放題数 第2位」のDMMプレミアム
eスポーツとは?

eスポーツの意味にいくまえに、まず最初に、スポーツの意味に立ち戻ってみましょう。
「え?!スポーツって、サッカーとか野球とか体を動かすものでしょ」とほとんどの人が思うでしょう。
確かに、それは正解です。
しかし、手元にある国語辞典によれば
「陸上競技、野球、テニス、水泳、ボートレースなどから登山、狩猟にいたるまで
、遊戯・競争・肉体的鍛練の要素を含む身体運動の総称」(広辞苑第六版)、
「余暇活動・競技・体力づくりとして行う身体運動。陸上競技・水泳・各種球技・スキー・スケート・登山などの総称」(大辞林第三版)
と書かれています。
余暇を利用した身体を使った活動であり、そこに「競う」という要素も含まれます。
つまり、スポーツには「競う」という意味が大前提にあるのです。
そういう意味では、eスポーツは、れっきとしたスポーツと言えるでしょう。
次に、eスポーツの定義を見てみましょう。
「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称です。
(日本eスポーツ連合のHPから引用 https://jesu.or.jp/contents/about_esports/
日本のeスポーツの歴史

日本のeスポーツの歴史はまだ浅いです。
以下から振り返ってみましょう。
1980年代:コンピューターゲームが誕生。数多くの大会が開催される。
1990年代:日本で格闘ゲームがブームに。欧米ではPGL、CPL等プレイヤーのプロ化が始まる。
インターネットの普及によってゲームのスポーツ化が加速。
2000年:「eスポーツ」という単語が使われ始め、産声を上げる。
2007年:日本eスポーツ協会設立準備委員会発足
2011年:第1回eスポーツJAPAN CUP 開催
2015年:一般社団法人 日本eスポーツ協会(JeSPA)設立
2018年:一般社団法人日本eスポーツ連合設立
海外のeスポーツ事情
海外諸国でeスポーツが盛り上がっている背景のひとつに、政府によるさまざまな支援があります。
各国がeスポーツに関して具体的にどのような政策を行っているのか、その最新動向を含めてお伝えしていきます。
アメリカ

世界最大のeスポーツ市場を誇るアメリカでは各地で大規模なeスポーツ大会が開催されています。
アメリカ国内のプロゲーマーはもちろん、海外プロゲーマーにアスリートビザを発行するなどしてeスポーツシーンを盛り上げています。
人気ゲームのジャンルがMOBA、FPS、CCG、スマホ向けのモバイルゲームなど幅広いのも特徴です。」
中国

中国のeスポーツ市場規模は2019年の時点でアメリカに次ぐ世界第2位。
さらにeスポーツ関連コンテンツの視聴者数は中国が半数以上を占めるとも言われています。
ジャンルではMOBAやモバイルゲームの人気が高く、
「League of Legends」や「王者栄耀」などのゲームタイトルでプロゲーマーが活躍しています。
韓国

韓国がeスポーツの聖地のような場所になっていることはご存知の方も多いでしょう。
「オーバーウォッチ」「リーグ・オブ・レジェンド」「スタークラフト2」などの
メジャーeスポーツタイトルの上位プレイヤーやチームの多くが韓国によって占められています。
韓国がeスポーツの世界最強国になった理由として、
かつての行政機関(現在は民間法人)であるKeSPA(Korea e-Sports Association)の活躍が挙げられます。
KeSPAが誕生したのは2000年、eスポーツという言葉が世界でもやっと使われ始めた時期に、名前に ”e-Sports” を冠して設立されました。
KeSPAの主な役割はゲームの公式大会の主催そのもので、
「国がeスポーツイベントを盛り上げている」という認識を国民に早くから持たせることができました。
韓国において男の子の「将来の夢」の上位に「プロゲーマー」が必ず上がり、最高レベルの選手を輩出しているのも納得です。
日本のeスポーツが弱い理由

諸外国に比べ、日本のeスポーツが後塵を拝しているのには、日本独自の理由があります。
スポーツという単語の認識が決定的に違う
冒頭にも書きましたが、
18世紀まではスポーツという単語は貴族階級における狩猟・競馬・弁論・ボードゲームなどに使われる単語でした。
19世紀に入ってからいろいろなことが起きて、一般大衆に広まり始め、肉体の限界を目指すものというのが加わり始めたのです。
日本では身体健康を目的とした運動だけを、スポーツと呼ぶようになったのです。
単語に対しての認識が決定的に違うので、eスポーツは運動じゃないからスポーツじゃないとなるわけです。
プロのなっても食べていけない給料事情
例えば格闘ゲームプレイヤーとして有名な梅原大吾氏、プロ活動に近いEVO2004から数えて17年になりますが、
総獲得賞金は2500万円ほどです。年収換算で156万円です。。
また、ぷよぷよのようなマイナーゲームのプロプレイヤーのTema氏が年収60万と言われています。
このようなありさまではどこかPCや関連用品の製造元がスポンサーになってもらうか、
ゲーム系Youtuberとしても活躍しないと生活できないレベルです。
育成の環境
プレイヤーを育成するプロチームや、環境が整っていないとこも理由の1つです。
プロゲーミングチームを運営するために資金繰りが、国内市場の小ささから難しいのが現状です。
大手のプロゲーミングチームは国内に多くありますが、数が少ないので、自然とプレイヤー人口も少なくなります。
チームを構えて、育成できる環境が多くなれば、プレイヤー人口も増えると思いますが、スポンサーなどの問題で難しいです。
一方、中国の育成環境は素晴らしく整っています。
中国で、2003年にeスポーツが国家の正式に認めるスポーツ種目となりました。
2019年4月に、eスポーツのオペレーターとプレーヤーが公式の職業になり、中国伝媒大学、上海戯劇学院、
上海体育学院などの5校と18の専門学校ではeスポーツを専門に学ぶ学部があり、まったく、日本と環境が異なります。
まとめ
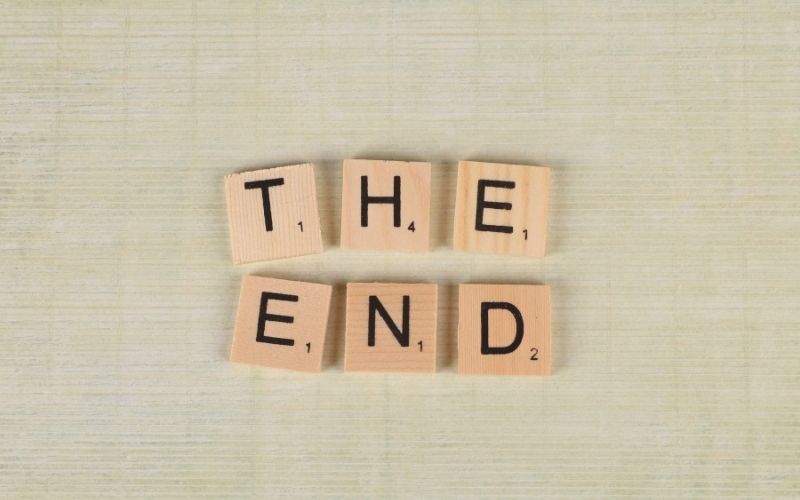
これから、eスポーツがオリンピック種目になるのでは?と言われている昨今、古い考え方は改めていきたいですよね。
サッカーやバスケットボールなど身体的特長が有利に働くスポーツだと、日本が不利になることはありますが、
eスポーツは身体的特長は全く考慮されません。
また日本人は緻密に計算して実行するのが得意と言われています。
個人的には、しっかり育てていく土壌さえ整えば、日本はeスポーツ大国に育っていく可能性は秘めていると思っています。
今後に期待しましょう!