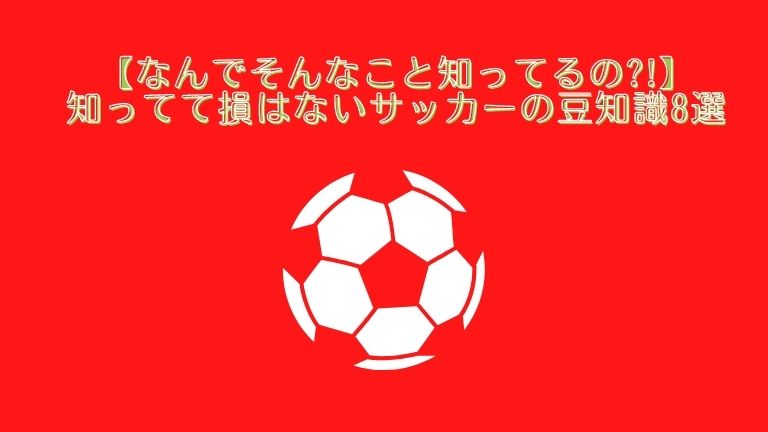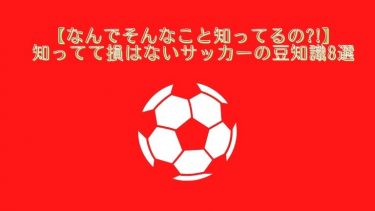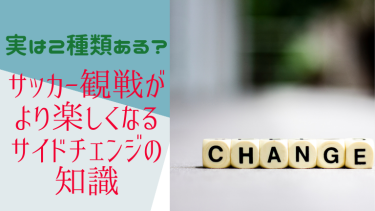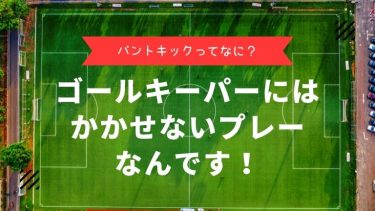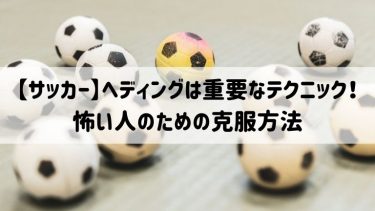日本でも、野球に並び、2大メジャースポーツの1つであるサッカー。
子供から大人まで楽しめるスポーツ・サッカーは、遊びも含めるとほとんどの日本人がやったり、見たことのあるスポーツでしょう。
1992年にJリーグが発足されてから、日本におけるサッカー人気はうなぎ登りで、それに伴い、日本代表のレベル、個々の選手のレベルも上がっています。
中田英寿選手くらいからでしょうか。
ヨーロッパリーグで活躍選手が出始め、ますますサッカー熱が高まってきているように感じます。
そんなサッカーの誰かについ話したくなる豆知識を集めてみました。
この中で「あ、面白い!」と思った豆知識を誰かに披露してみてください!
1,日本代表のユニホームの色は赤色だった?!

サッカー日本代表のユニフォームといえば「サムライブルー」が基調となっていますが、実は1988年から1991年までの3年間は赤色のユニフォームを着用していました。
当時監督を務めていた横山謙三監督の意向で日の丸の赤色をベースカラーにし、胸には日の丸の代わりに日本サッカー協会のエンブレムがつけられました。
しかし横山監督はイタリアW杯予選、またバルセロナ五輪予選でもいい結果を残せず3年で解任となり、赤色のユニフォームもともに変更となったのです。
2,日本代表のユニホームの色が青色の理由

日本代表のユニホームの色は「サムライブルー」と呼ばれているように、青色というのが特徴的です。
それでは、いつからユニホームの色は青色だったのでしょうか?
実は、日本代表のユニホームの色が青色だったのは、戦前の頃からでした。
日本は島国で、周りが海に囲まれているので、青色を採用したと言われています。
日本がワールドカップに出場するようになったのは平成の頃からで、その当時のチームは決して今ほど強くありませんでした。
しかし、その当時の日本代表が格上のスウェーデン代表を倒して、「青色、縁起がいいぞ」となりました。
そして、1992年に、青色のユニホームが正式に採用されるようになったと言われています。
3,日本代表の象徴3本足のカラスとは?

日本代表のユニホームには、3本足のカラスがボールを押さえている姿が描かれています。
これは、中国の古典にある「三足烏(さんそくう)」のことです。」※三足烏とは、中国の神話で,太陽のなかに住むという3本足のからすのこと。
昔から日本人は、カラスに特別な力があると考えていて、「八咫烏(やたがらす)」が神武天皇の軍隊を道案内したという逸話もあります。
4,10番が特別な意味を持つ理由
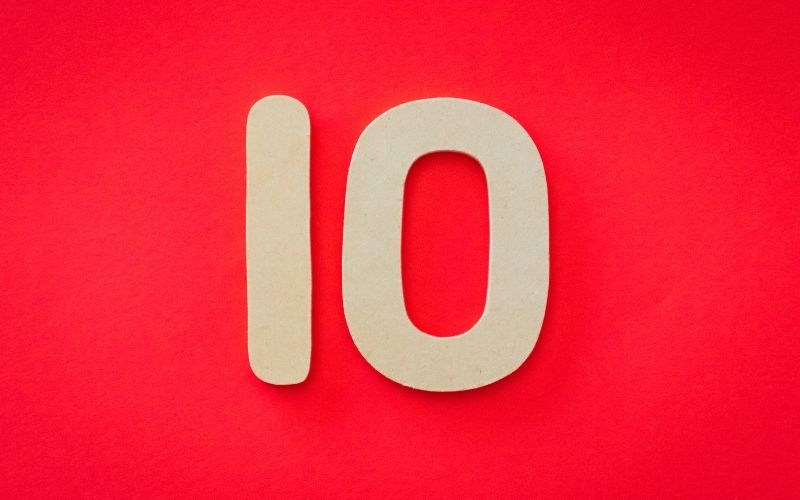
背番号10番はサッカーの神様と呼ばれるブラジルのペレがつけていたことからエースがつける番号であり、司令塔であり、
得点力も兼ね備えている選手がつけるべきとされています。
そのため10番をつけた選手は自然とチームの顔にもなり、相手チームからは特に警戒すべき重要な選手とみなされます。
ペレがFIFAワールドカップで背番号10をつけたのは1958年のスウェーデン大会から。
当時のペレは若干17歳でしたが、大会で6得点を叩き出す大活躍をしてチームに初優勝をもたらしたことから、
10番の選手がエースとして注目されるようになったのです。
ちなみにペレが10番をつけていたのは、監督が適当に割り振ったからという意外な理由でした。
それにも関わらず、いまだに10番が特別な番号として語り継がれているというところに、ペレの凄さを感じますね。
5,イギリスでは「サッカー」といわない?

近代スポーツとしてのサッカーは19世紀の初めにイギリスで生まれました。
正式名称は「association football」と言います。
その一部の「soc」に「cer」をつけ、「サッカー(soccer)」という呼び方が生まれました。
しかし、現在では「サッカー」という国は少なく、イギリスをはじめ多くの国では「フットボール」と言います。
ちなみに、アメリカでは、フットボールと言えば、「アメリカンフットボール」のことで、日本と同じように「サッカー」と呼ぶのだそうです。
6,なぜ、子供と手を繋いで入場するの?

サッカーの試合が始まる前に、選手と子供が手を繋いで入場してくることがありますよね。
あの子供たちのことは、「エスコートキッズ」と呼ばれていて、そこにはちゃんとした意味があるのです。
エスコートキッズは、フェアプレーの象徴であり、子供たちの前では、スポーツマンシップにのっとり、
反則行為などの恥ずかしい行為はしませんよ、という意味が込められているのです。
そして、同時に、子供たちに、夢や希望を与えます、という意味も込められています。
エスコートキッズは、代表戦だけでなく、クラブチームの試合でも導入されています。
また、海外リーグでは、自分の子供と手を繋いだり、抱えたりして、入場する選手もいるのです。
他人の子供でなく、自分の子供なので、なおさら、規律を重んじて、プレイしようと思うことでしょう。
7,スローインを両手で行う理由

サッカーでは、ボールがタッチラインを出ると、ボールを両手で投げ入れる「スローイン」が行われます。
スローインは両手で行われるのが普通ですが、なぜ片手ではダメなの?と思ったことはありませんか。
実は、スローインが両手で行われるのは、試合を面白くするためなのです。
昔のサッカーでは、スローインに関するルールが特に設けられてなかったので、片手でスローインする選手も中にはいたそうです。
そのため、強肩の選手の場合、次々にゴール前に投げ入れることが可能でした。
しかし、それでは、サッカーの試合の面白さが欠けるので、「スローインは両手で」というルールが定められたのです。
8,VARとは?

ここ最近の国際試合でたびたび登場した「VAR(ブイエーアール)」とは、ビデオ・アシスタント・レフェリー制度の略で、
ピッチ上で起きたファウルやゴールなど試合を決定づけるプレーに対してビデオ判定を用いて判定するシステムです。
VARが導入される前は、主審と線審だけで、判断してましたが、人間の目視だけでは、限界があるので、導入されました。
ピッチに立つ審判とは別にモニターでビデオ・アシスタント・レフェリー(映像副審)が試合を監視し、
ゴール判定やレッドカードの提示など試合の結果を左右する重要な場面において、無線で主審に助言をすることができます。
また主審だけがビデオ判定を要望する権限をもっています。
ビデオ判定が行われる場合は、主審がピッチ外に出て問題のシーンをモニターで確認した後に改めて判定を下します。
今後、映像技術の進歩によって、いかなるシーン、いかなる角度からでも、カメラが選手の動きを追いかけることが可能になるので、
悪質な反則行為が減っていくことでしょう。
まとめ
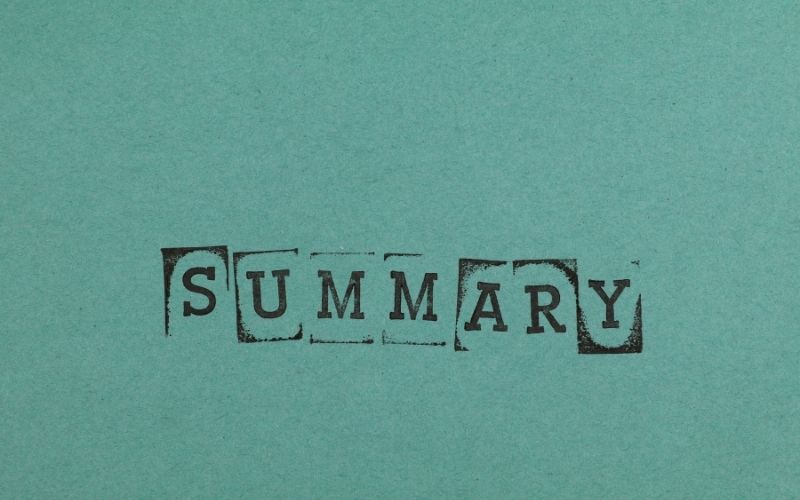
いろんなトリビアがありましたね。
ここに書いたのは、ほんの一部に過ぎません。
歴史のあるスポーツだからこそ、もっともっと、トリビアが存在するはずです。
もしこの中で、あなたにとって、興味深いのがあったら、豆知識として、誰かに教えてあげてください!
この豆知識が、「なんで、そんなこと知ってるの?」とあなたと友達との会話を盛り上げるネタの助けになったら、とっても嬉しいです!