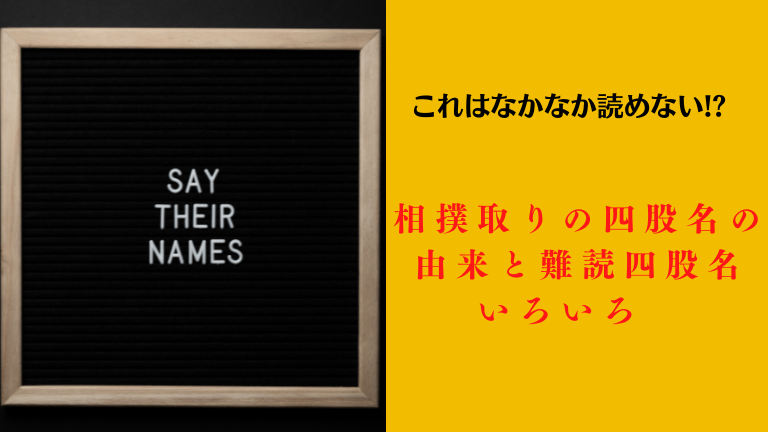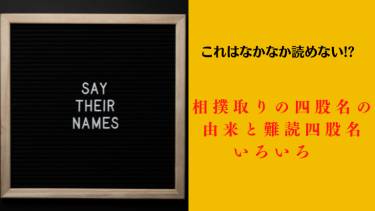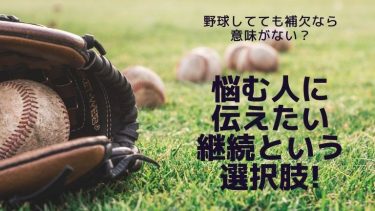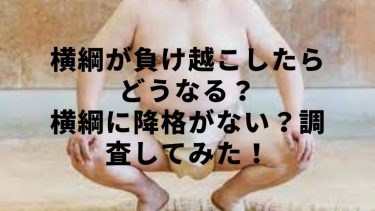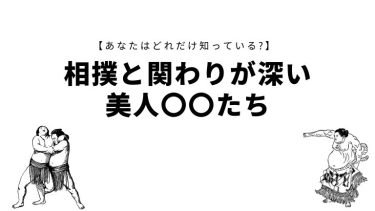力士が土俵に上がるうえで、四股名は欠かせないものです。
いろいろな四股名がある中で、「これはどうやって読むのだろう?」と思ってしまうものも少なくありません。
今回は、そういった読みにくい四股名を紹介していきます。
四股名とは?
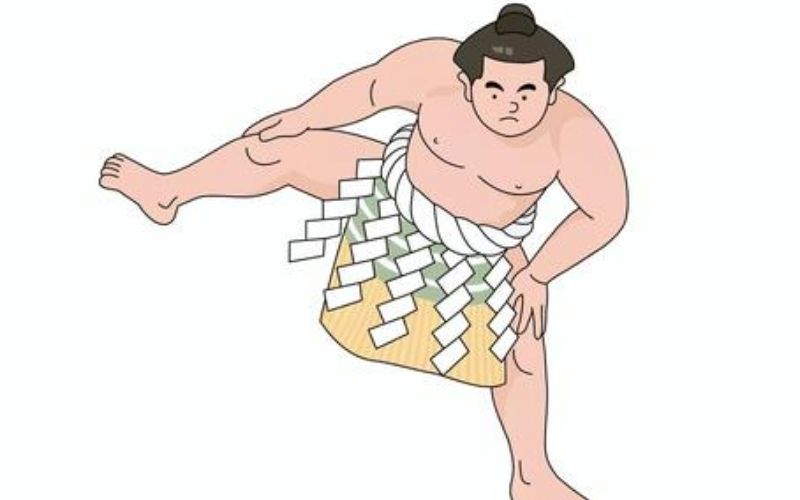
もともと、四股名は「醜名」と書いていました。
「醜」と言う字があてられていますが、
「みにくい」と言う意味ではなく、「たくましい」という意味です。
日本書紀にも、大国主神(おおくにぬしのかみ)の別名として「葦原醜男(あしはらのしこお)」と記されています。
いつの頃からか、この「醜男」は四股名と言う字があてられるようになりました。
「醜」という字にネガティヴな意味が含まれることに加え、「醜名」には「あだ名」「忌み名」など他の意味もあるため、
混同をさけるために四股名に変えられた可能性もあります。
四股名はどのようにつけられる?

そんな四股名ですが、どのようにつけられるのでしょうか。
いくつかのパターンがあるので、紹介していきます。
親方の四股名からそのまま引き継ぐ、あるいは一部を継承する
親方から四股名を引き継ぐ場合は、混同をさけるために「○代目」という表し方をすることが多いです。
有名なところでは、あの若貴兄弟ですね。
兄が「3代目若乃花」、弟が「2代目貴乃花」を襲名しています。
部屋ごとに決まった漢字を使用する
相撲部屋によって、ある決まった漢字を使っている例もあります。
代表的なものでは、
◆相撲部屋特有の継承文字◆
- 九重部屋 →「千代」
- 佐渡ヶ嶽部屋 →「琴」
- 春日野部屋 →「栃」
- 玉ノ井部屋 →「東」
などです。
このパターンでは、その力士がどの部屋に所属しているかがわかりやすくなっています。
本名をそのまま使う
入門からしばらくは、四股名がつけられず本名をそのまま使用する例も少なくありません。
最近だけでも、
- 明生(めいせい)
- 正代(しょうだい)
- 高安(たかやす)
- 遠藤(えんどう)
などが挙げられます。
ほとんどが苗字由来ですが、明生は名前を使用している珍しいパターンです。
ある程度番付が上がると改めて四股名をつけることも多いのですが、先に挙げた力士たちは、本名そのままの四股名で通していますね。
これは読めない!難読四股名8選

それでは、四股名の中でも「これは読めない!」というものを8個紹介していきます。
豪風
こちらは「たけかぜ」と読みます。
尾車部屋所属で最高位は関脇。
2019年に引退しています。
通算100場所に出場、一度十両優勝を遂げています。
四股名の由来は、「豪快な相撲で豪華な風が吹くように」との願いをこめて師匠が名付けたものだそうです。
日馬富士
初見ではなかなか読めないですが、横綱まで登り詰めたので、こちらは読める方も多いと思います。
「はるまふじ」と読みます。
四股名の由来は、元々の四股名の「安馬」の馬の字に太陽を意味する「日」をつけ、さらに師匠の旭富士の「富士」をもらったものだそうです。
「日」を「はる」と読ませるのは、「語感がきれいだから」とのことです。
モンゴル出身で、本名はダワーニャミーン・ビャンバドルジと言います。
横綱在位は2012~2017年です。
力士の中でも軽量級ですが、持ち前の強気と豊富なけいこ量により、横綱の地位を手にしました。
幕内優勝回数は9回、うち全勝優勝は3回を誇りましたが、下位力士に対する取りこぼしをする癖があり、金星の配給が多い力士でもありました。
2017年時点でもまだまだ力は健在でしたが、貴ノ岩関への暴力行為が原因で、引退を表明しています。
巨砲
こちらは「おおづつ」と読みます。
最高位は関脇。1992年の引退時の番付は東十両7枚目でした。十両優勝を一度経験しています。
また、金星は歴代5位タイの10個を獲得しています。
中学時代は野球と空手をやっていました。
野球については、有名高校から勧誘が来るほどの実力だったそうですが、元横綱大鵬に誘われて角界に足を踏み入れています。
なお、巨砲は大鵬部屋初の関取です。
璞 歳之助
こちらも、なかなか難しいですね!
「あらたま としのすけ」です。江戸時代に伊勢ノ海部屋および柏戸部屋に所属しており、最高位は東前頭二枚目です。
「璞」は「新玉」とも書き、「掘り出したままで、まだ磨いていない玉」と言う意味があります。
また、和歌などの枕詞として使われることもあります(「年」に係り、「新年」を表す)。
親方の期待の高さが分かる四股名ですね。
幕内に10年もいた息の長い力士でしたが、現役のまま38歳で亡くなったとのことです。
可愛嶽 実男
「えのだけ さねお」と読みます。
昭和初期の力士で、最高位は十両4枚目です。
幕下上位にいた際、力士のストライキ(春秋園事件)があり、力士が大量に離脱しました。
そのため、可愛嶽(当時の四股名は「嶋和泉」)が十両に上がりました。
可愛嶽は宮崎県にある山です。
西南戦争の際、西郷隆盛がこの山を越えて鹿児島へ逃れたことで有名です。
片福面大五郎(かたおかめだいごろう)
こちらは「かたおかめ だいごろう」と読みます。
『片福面鸚哥』と書いて「オカメインコ」と読むのですが、この力士の場合は、あえて「かたおかめ」と読ませているようです。
明治から大正時代にかけて活躍した力士で、最高位は幕下三枚目です。
力士としては大成しませんでしたが、宴会やちゃんこ作りでは活躍する場面が多かったとのことです。
九 九之助
これも初見ではまず読めない四股名ですね。
「いちじく きゅうのすけ」と読みます。
明治時代の力士で、最高位は小結です。
九と書いて「いちじく」と読むのは、全国に約40人程度しかいない、かなり希少な苗字と言うことです。
阿武咲 奎也(おうのしょう ふみや)
こちらは2021年11月時点で現役の力士です。
「おうのしょう ふみや」と読みます。
過去に殊勲賞1回、敢闘賞3回獲得、十両優勝も1度経験しています。
阿武咲という四股名の由来について、「阿武」は師匠の「阿武松(おうのまつ)」親方からいただいています。
「咲」と言う字には、「土俵上で花が咲くように」という願いが込められているとのことです。
阿武咲は、本名が「打越 奎也」といい、苗字は「うてつ」と読みます。
こちらも、初見で読むのが難しいですね。
まとめ
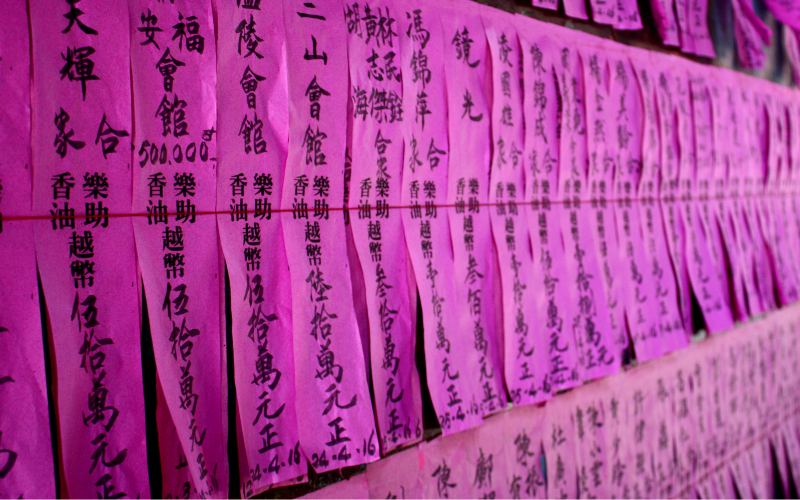
あらゆる四股名の中には、今回紹介したような読み方が難しいものもあります。
ひとつ言えることは、その四股名をつけるにあたり「どのような力士になってほしいか」という強い願い・想いが込められている、ということです。
また、今回この記事を書くにあたり、四股名の由来を調べることで大変勉強にもなりました。
今回紹介した四股名以外にも、難読であったり面白いものはたくさんあるので、調べてみるのもいいかもしれません。