老若男女だれでも気軽に始められ、また日本人選手の世界での活躍もあり、いまや大人気のスポーツとなっている「卓球」。
皆さんも、学校の授業や旅先などで一度は楽しんだことがあると思います。
また街にも卓球ができる施設が増え、楽しそうにプレーする姿を目にするようになりました。
今回は、そんな人気のスポーツ卓球はどこでどのようにして生まれたのか、日本にはいつやってきたのかなど、詳しくご紹介していきます。
卓球発祥の地はどこなのか?

卓球発祥の地は、中国じゃないの?と思われる方が多いと思います。
しかし探っていくと中国発祥ではなく、時期や形など解釈によって諸説ありますが、以下の4つの国が卓球発祥の地としてあげられています。
- エジプト説
話しは古く紀元前15世紀、約3,400年前のエジプトの壁画に、宗教的な行いとしてボールを打ち合う、
テニスをする様子(テニスの原型)が描かれているのです。
卓球のルーツといわれているテニスがこんな大昔に始まっていたとは驚きです。
- インド説
「ゴッシマテニス」という屋内での遊びが起源ではないかといわれています。
テーブルの真ん中をネットで仕切り、セルロイド製のボールをラケットで打ち合い得点を争そっていたそうです。
但し、いつ頃始まったのか、どういう経緯で生まれたかなど詳しい記述、資料が見つかっていないようです。
それでも現代の卓球に近いもので、こちらの説も有力だといわれています。
- フランス説
13世紀フランスの貴族が娯楽で始めた「ジュ・ド・ポーム」。
フランス語で「手のひらのゲーム」といわれる、手のひらでボールを打ち合う遊びです。
のちに現在のラケットに似た道具を使ってプレーするようになりました。それがイギリスへ渡り「テニス」と呼ばれ世界へ広まっていきました。
- イギリス説
フランスから伝わったといわれるテニスが19世紀後半から大人気スポーツになったイギリス。
ただ雨がよく降る気候で、テニスも雨のための中断が頻繁に起こりました。
そこでそのあいだの暇つぶしとして、室内でテーブルをコートに見立て、ラケットを葉巻の箱に変えて、テニスボールを打ち合って遊んでいました。
それが「テーブルテニス」、卓球の始まりだといわれています。
以上、卓球発祥の地といわれている4つの説をご紹介しました。
諸説それぞれ説得力があり、また捉え方によってもそれぞれ意見がわかれるところです。
今後も多くの議論が重ねられていくことでしょう。
1900年当時イギリスでピンポンゲームと呼ばれていました。
革張りのラケットでセルロイド製のボールを打つと「ピン」、相手の台に落ちると「ポン」、と鳴るところからついた呼び名です。
「卓球王国」中国の強さ
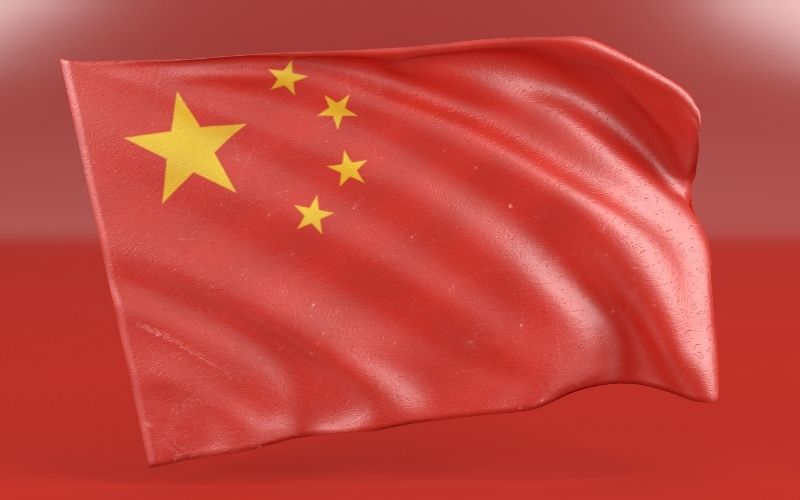
意外にも卓球発祥の地ではなかった中国ですが、その強さや競技人口、愛好者数など、やはり卓球といえば中国です。
ここでは、自他ともに認める世界一の「卓球王国」中国の強さを探ります。
中国の卓球人口
中国の卓球の強さは、愛好者の裾野の広さにあるといわれています。
一般の卓球愛好者が8000万人以上、卓球専門学校や体育学校の選手、それにプロ選手を合わせた競技レベルが3000万人といわれています。
街の公園には卓球台が置かれ、多くの市民が日常的に卓球を楽しんでいます。
学校では授業に取り入れられ、そして競技者が目指す最終目標が世界最高峰といわれている、「中国卓球スーパーリーグ」です。
中国卓球スーパーリーグ
「中国卓球スーパーリーグ」は1995年に発足しました。市や省を本拠地としている男女各10チームづつが参加しています。
また各国のトップ選手も参加していて、過去には日本の水谷隼選手や福原愛選手、平野美宇選手などが出場しています。
賞金面でも世界トップクラスのリーグで、大会賞金、クラブ給料、スポンサー料などを合わせて年収1億円プレーヤーも多く誕生しています。
これらに加えて中国でいちばん人気のある、卓球のトッププロ選手ともなるとステータスを得られ、国民からも憧れの的となります。
例えればヨーロッパの人気サッカー選手のように、街を歩けば声をかけられ、写真をせがまれたりサインを頼まれるなど超人気のスターです。
そんな憧れのトッププロ選手を目指せる、国を挙げての一貫した支援体制と、強化システムが確立していることが中国の強さの要因です。
そしてなにより最大の強さの源は、「卓球が好きな人が多い」、「卓球を愛している人が多い」ことです。
このことが「卓球王国」中国をつくりあげています。
卓球はいつ日本へやってきたのか

最後は卓球が日本に来たのはいつなのか、だれがどのように伝えたのかをご紹介します。
我が国学校体育の父
日本に卓球を伝えたのは「我が国学校体育の父」といわれる坪井玄道という人物です。
どういう人物なのかを簡単にまとめました。
| 坪井玄道:つぼい げんどう(かねみち)
生年月日:嘉永5年1月9日(1852年1月29日) 出身地:下総国葛飾郡(千葉県市川市) 没年月日: 大正11年11月2日 70歳(1922年11月2日) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー <主な経歴> 明治4年:大学南校勤務(東大の前身) 明治8年:宮城英語学校教師 明治15年:「新選体操書」を刊行 明治19年:高等師範学校助教諭 明治23年:高等師範学校兼女子高等師範学校教授 明治35年:卓球を日本に紹介 平成18年:日本サッカー殿堂入り ーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
坪井玄道は、日本で最初の体育教師となり、日本の学校体育の基礎を創ったといわれています。
慶応2年に幕府の開成所に入学して英語を学び、通訳や教師の仕事に就き、宮城英語学校を経て、体操伝習所の教師を務めます。
そこから体育授業に力を注ぎ、教え子との共編著で「戸外遊戯法」を刊行しました。
この本は日本人が初めて書いた近代スポーツ解説書になります。
体操研究のため文部省からの派遣で海外を回り、明治35年(1902年)の帰国の際、イギリスから卓球のラケット、
ボール、ネット、ルールブックなどを持ち帰ります。
そのことがきっかけとなり、日本での卓球というスポーツが大々的に始まることとなりました。
坪井玄道は卓球のほかにも、サッカー、ドッジボール、ダンスなどを日本に紹介し普及にも力を入れ、各競技の発展に尽力しました。
彼の日本のスポーツ発展にあたえた功績は計り知れません。
まとめ

卓球の起源、中国の強さ、そして日本へはどのようにして伝わったのかをご紹介しました。
卓球をプレーしている人に訊くと、卓球ほどたくさんの面白さや見どころが詰まったスポーツは他にないといいます。
魔球のようなサーブに、100㎞を超えるスピードのスマッシュ。
プレースタイルも攻めのドライブショットに、守りで勝つカットマン。ラケットやラバーの種類によっても戦い方が変わってきます。
打つコースやスピードの緩急、相手の逆をつくなど心理戦、頭脳戦の面もあります。
そしていちばんの魅力は、体格差や年齢、性別に関係なく誰もが一緒にプレーできるところです。
みなさんも、ご家族、ご近所、友人たちと誘い合って、卓球を楽しんでください。






