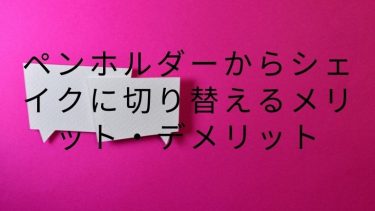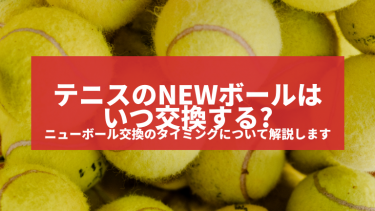卓球競技は、東京オリンピック2020において4つのメダル獲得し、その力を世界に見せつけました。
特に、金メダルを獲得した男女混合ダブルスは日本を熱狂させました。日本が卓球で中国に勝つというのはまさに歴史的な快挙でした。
そんな卓球競技のラケットに注目したことはありますか。
卓球のラケットは大きく2つの種類があります。
- ペンホルダー
- シェークハンド
今回はこの2種類のラケットの違いと、現在シェークハンドの陰に隠れているペンホルダーに注目して、
なぜ使われなくなってしまったのかを調査します。
ペンホルダーとシェークハンドの違いとは?

ペンホルダー
昔は多くの選手が使用していたラケットがペンホルダーです。
ペンホルダーは基本的には片面(表面)にのみラバーを貼るタイプのラケットで、シェークハンドよりも長細い形のものが多いです。
ただ、最近は裏面にラバーを貼るタイプのものもあります。
ペンホルダーは、『ペンを握るように持つ』という言葉に由来します。
ペンホルダーのラケットにもいくつか種類があるので紹介します。
②日本式ペンホルダー(ドライブ向き)
③日本式ペンホルダー(速攻向き)
④反転用ペンホルダー
①中国式ペンホルダーは、丸みを帯びた形のラケットで、台上や前~中陣でのプレーを得意とする選手が使用する傾向があります。
また、裏面にもラバーを貼りやすいのも特徴です。
②日本式ペンホルダー(ドライブ向き)は長細い形が特徴のラケットで、ドライブを得意とする選手が使用する攻撃的なラケットです。
③日本式ペンホルダー(速攻向き)は、②よりも少し丸みがあるラケットで、フォアやバックの操作性が優れており、攻守に適したラケットです。
④反転用ペンホルダーはラケットの両面にラバーを貼ることを前提としており、握りはペンホルダーですが、
使い方はシェークハンドのようになるラケットです。シェークハンドのように多彩な球質をつくり出すことが可能です。
①~④のようなラケットの種類はあるものの、ペンホルダーは、
現在世界のトップクラスの選手がほとんど使用することが無いラケットとなっています。
ペンホルダーの人気が無くなった原因を探ります。
シェークハンドの特徴を見ることで、違いがはっきりとします。
シェークハンド
シェークハンドとは、現在世界の主流となっているラケットです。
オーソドックスなラケットは、丸みを帯びたもので、フォア面とバック面の両方にラバーを貼ったものです。(通常赤と黒のラバーです)
両面に貼るラバーの種類を変えることで、多彩な球質をつくりだすことが可能となり、攻撃の幅が広がります。
またシェークハンドは、『握手する』という言葉に由来します。
その名のとおり、握手をするようにラケットを握るため、シェークハンドという名がつけられました。
世界のトップ選手のほとんどがこのシェークハンドを使用しています。
オリンピックや世界選手権では、ほぼすべての選手がシェークハンドを使っているといってもいいでしょう。
ちなみに、シェークハンドの中でも、
②カット用シェークハンド
というように、選手の特徴に合わせたラケットがあります。
ペンホルダーの弱いところは一体どこ?
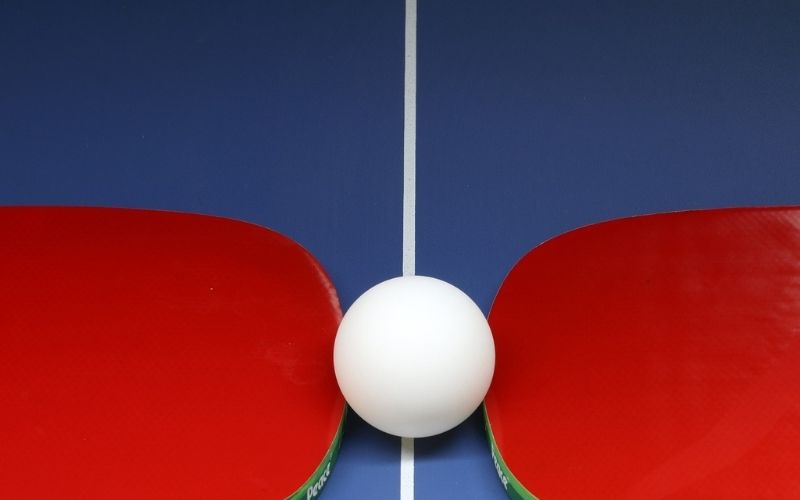
ペンンホルダーが使われなくなった理由、それは大きく2つの弱点に原因があると考えられます。
バック側での圧倒的な弱さ
どういうことか順を追って説明します。
まず、昔に比べて、ラリー時間が長くなったことにより、バック側での弱さが露呈しました。
昔の卓球は、現在のように激しいラリーの応酬はあまりなく、数回のラリーで決着することが多かったため、
白熱する展開になりにくかったと言われます。
そんな状況を打開するために、様々な案が考案されました。
ボールをわずかに大きくして、素材をセルロイドからプラスチック変えることで、ボールとラケットの摩擦が減りました。
これにより、ボールスピードが遅くなりラリーする時間が長くなったのです。
ラリー時間が長くなったことで、くしくもペンホルダーの弱点が浮き彫りになってしまいます。
バックハンドに弱点があるペンホルダーは、長いラリーの中でバックハンドを責められる機会が増え、
シェークハンドに勝てなくなってしまったのです。
ペンホルダーは基本的には片面しかラバーが無いので、フォア側はシェークハンドと同じ振りで打つことができますが、
バック側は手首を反対にひねるような形になるため、強い球が打ちにくいのです。
逆に、バック側でも手首を返す必要が無いシェークハンドは、強烈な回転をかけることができるため、ペンホルダーに対して、
圧倒的な優位性を持つようになります。
チキータの登場
東京オリンピック2020の卓球競技でも、『チキータ』という技は多用されました。
日本の伊藤美誠選手もチキータを武器としており、この技を駆使して、水谷隼選手とのペアで見事に日本卓球史上初の金メダルを獲得しました。
チキータは、ラケットの裏面を使って、手首の反動を利用した横回転のバックフリックをかける技のことをいいます。
まさにシェークハンド特有の技であり、卓球のネット際であっても強烈なスピンをかけることができるこの技は、
現代卓球では必須の技になりつつあります。
ペンホルダーは、攻撃面でもチキータを繰り出すことはできませんし、また守備面でも、
バック側に打たれることが多いこの技に対応するのは難しくなります。
このチキータの登場により、ペンホルダーの立場はさらに厳しい状況となりました。
もはやトップ選手でペンホルダーを使う選手を見ることは今後期待できません。
ペンホルダーは絶滅してしまうのか

ペンホルダーが世界トップ選手の間では、もはや絶滅危惧種のような状態になっていることはお伝えしたとおりです。
それではこのままペンホルダーは絶滅してしまうのでしょうか。
結論からいうと、すぐに絶滅することは無いので、安心してください。
現在の卓球人口は日本で900万人いると言われています。
この人数、年々増えていると言われています。
また、温泉施設に行っても卓球コーナーがあったり、市営の体育館でも卓球スペースがあったりと、
卓球というスポーツのすそ野は、どんどん広がってきています。
卓球は、狭いスペースでも大人から子どもまで楽しむことができる珍しいスポーツで、
空き地が少ない日本においては、まさにぴったりのスポーツなのかもしれません。
ペンホルダーはこのような、すそ野が広がった中では重宝される存在です。
そもそも、初めて卓球をトライする人は、トップ選手のように回転を目いっぱいかけたり、スマッシュを打ち込んだりすることがありません。
基本的には家族や友達とラリーを楽しんだり、コミュニケーションの一環として卓球をすることが多い事でしょう。
初心者のうちは、ペンホルダーの方が握りやすいという人も結構多いでしょうし、
ある程度のレベルまでなら、ペンホルダーでも十分にシェークハンドに勝つことが可能です。
その証拠に、ほとんどの卓球施設では、シェークハンド、ペンホルダー、両方のラケットが常備されています。
トッププロを目指すのであれば、シェークハンドはもはや必須といえるかもしれませんが、
卓球を楽しむ分には、ペンホルダーの存在もまだまだ捨てたものではありません。
まとめ
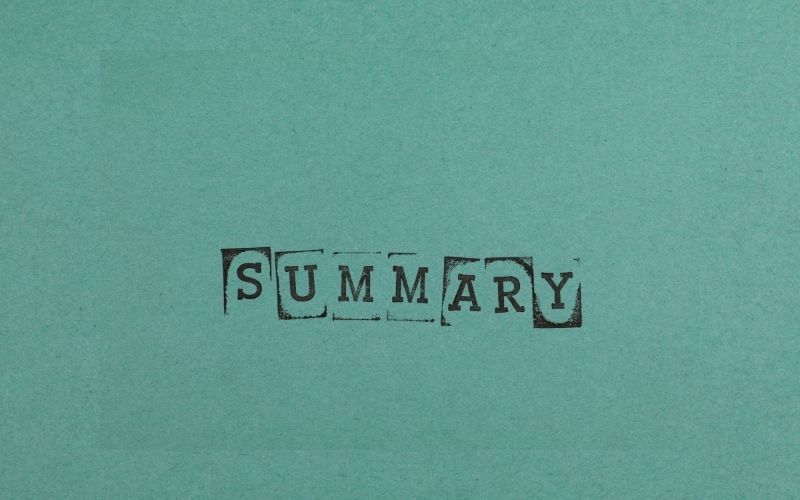
シェークハンドとペンホルダーの違いについて紹介しました。
このようにペンホルダーの需要というのは、初心者~アマチュアを中心にまだあるが、
トッププロの世界では今後も見られることはほとんどないという事が分かりました。
ペンホルダーが弱いという事は、事実だとは言えますが、絶滅することは無いでしょう。
今度はラケットに着目して卓球を楽しみましょう。