誰でも手軽に楽しむことができ、レジャーとしても人気のある卓球。
地域の体育館に行っても、卓球は人気で、プレーできるまでに待ち時間がある…なんてこともしばしば。
誰でも気軽に始めることができる反面、卓球の世界は非常に奥深いもの。
卓球の世界には、あなたの知らない意外な事実が秘められているかもしれません。
ここでは、そんな卓球の豆知識について紹介していきます。
卓球豆知識①ラバーの色について

卓球のラケットに貼ってあるラバーですが、一般的には「赤と黒」というイメージを持っている人が多いことでしょう。
ラバーが赤と黒の2色でないといけないということは、卓球のルールに定められています。
しかし、このルールが制定されたのは実は1985年のこと。
それまでは、ラバーの色は何色でも良かったのです。
当時は実際に、緑色や、紫色のラバーが販売されていました。
また、ラケットの裏と表に同じ色のラバーを貼ることもできたので、
あえて両面同じ色で違う性質のラバーを貼って、相手を惑わせるという戦法もよく採られていました。
しかし、攻撃を受ける側からすると、相手の球の性質が分からないので、ラリーの数が減ってしまいました。
ラリーの回数が減ってしまうと、観客からしても「卓球はつまらないな」という印象を持たれがちです。
これを受けて、ルールが改正される流れとなりました。
近年、ピン球の性質がセルロイドからプラスチックに完全に変わりましたが、それもラリーの回数を増やすという意図があったようです。
ところが、2021年10月21日よりピンク、紫、緑、青のラバーが解禁されることが決まりました。
ただ、同色のラバーを使う前のルールに戻ったわけではなく、今回のルール改正後も、例えば片面にピンクのラバーを貼れば、
もう片方は黒色のラバーでならなくてはならないようです。
昔のように同色のラバーから繰り出される、トリッキーなプレーは見れなくなりましたが、いろいろなカラーリングのラバーが発売されると、
目にも鮮やかで観戦する側にとっても楽しみですね。
卓球豆知識②ユニフォームについて

テニスほどではないかもしれませんが、卓球のユニフォームも、デザインに凝っていたり、女性用だとスコートがあったり、
といろんな種類のものが売られています。
実は、卓球のユニフォームに関しても規定があります。
まず、公式試合ではJTTA(日本卓球連盟)のラベルのついたユニフォームでないと、出場することができません。
地域の小さな大会だと、卓球連盟が関与していない場合もあるので、スルーされることもありますが、
基本はラベル付きのユニフォームでないと試合に出れない、と考えておいて間違いないでしょう。
卓球ショップを訪れてみると、ラベルのついていないものも売っていますが、それらはユニフォームではなく、「練習着」なのです。
同じメーカーのユニフォームと練習着を比べると、練習着の方が何割か価格が安い場合がほとんどです。
ちなみに、多くのユニフォームは上下に分かれていて、下はショーツタイプかスコートタイプですが、
下半身のユニフォームには練習着という概念はあまりないようです。
なので、そもそも練習着のタイプのショーツ等は販売されていないことが多く、普段の練習時から、下はユニフォームを穿いて練習しています。
あとは、団体戦の場合だとチームでユニフォームを揃える必要があったり、ピン球と同じ色のユニフォーム(白)は禁止されていたりもします。
また、個人戦の場合でも、対戦相手と同じユニフォームを着ることはできません。
人気のユニフォームだと、意図せずしてかぶってしまう場合もあるので、卓球選手は試合会場に何枚かユニフォームを持っていくことが多いのです。
卓球豆知識③ラケットについて
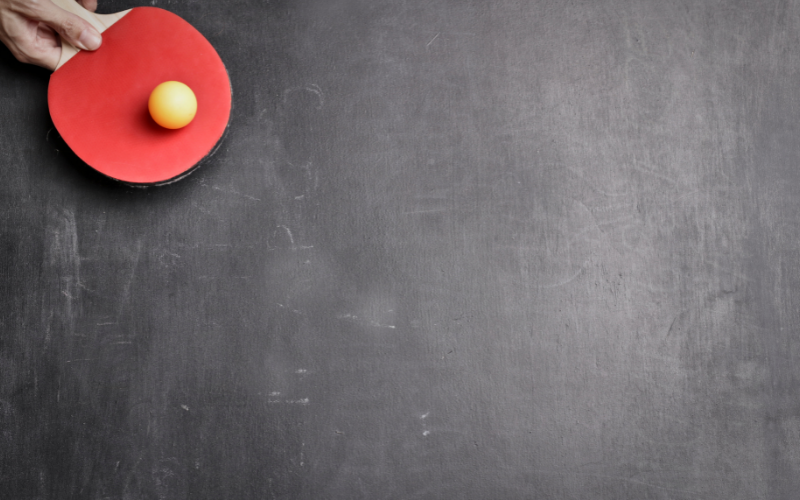
実は、卓球のラケットに関しては素材上の制約はあるものの、大きさは自由なんです。
理論的には、大きなラケットを使った方が、その分球に当たる確率が増えるのですから、
より大きいものを使った方が有利なのでは?と思われるかもしれません。
しかし、忘れてはならないのが、相手の打ってきた球には様々な回転がかかっているということ。
ただ、ラケットの面に当てるだけで必ずネットを越えてくれるのであれば、ラケットの大きさ対決になってしまい、
競技としての面白みは失われてしまうでしょう。
回転をかけたり、逆に相手の回転を殺したりして返球するには、どうしてもスイングが必要になります。
スイングが必要だということは、扱える程度の重さのラケットでないといけないですね。
ちなみに、ラケットの重さってどれくらいあると思われますか。
現在、男子のトップ選手でも、シェークハンドで大体180gくらいまでのラケットで戦っていると言われています。
180gという数字だけ聞くと、何だか軽そうに思われるかもしれませんが、この重さのラケットでフルスイングするのはなかなか大変です。
卓球選手は、引き締まった腕をしている選手が多いですが、数字以上に、ラケットは重いのです。
ちなみに、レディースや、まだ体の出来上がっていない中学生の場合だと、160g台の軽いラケットでも特に問題はありません。
こればかりは、自分に合う重さを探していくしかないです。
ラケットが重すぎても、故障の原因になったりしますし、逆に軽すぎても力が上手く伝わらなかったりとエネルギーロスが多くなったりします。
ぜひ、いろんな組み合わせを試し、自分に最適なラケットを見つけてくださいね。
卓球豆知識④軟式卓球が存在する

みなさんは、卓球の「ラージボール」という単語を聞かれたことがお有りでしょうか。
実は、テニスのように、卓球にも軟式・硬式というカテゴリーが存在するのです。
みなさんが、レジャーで楽しんだことのある卓球がメジャーであり、硬式卓球であると考えて間違いありません。
ですが、それ以外に、硬式卓球よりピン球が2回りほど大きなボールで試合をする、「ラージボール」という競技が存在します。
普通サイズのピン球を見慣れている人には、とても大きく感じられる、このラージボール。
ボールが台を跳ねる音も独特で、「シャリッ」という音がします。
硬式卓球だと、こういった異音がした場合は、「ピン球が割れているのかな?」と思ったりするのですが、
ラージボールの場合、元から独特な音がするのですね。
このラージボール、基本的なルールは硬式卓球と変わりませんが、いくつか特徴的なルールがあります。
まず、ピン球の色が「オレンジ」のみなのです。
硬式卓球にも、オレンジ色のピン球はありますが、ラージボールにはオレンジ色のピン球しかありません。
そして、ラバーの種類も「表ソフトラバー」だけに限られています。
硬式卓球では、裏ソフト、一枚、粒高など、様々な種類からプレイヤーの好みに合わせて選ぶことができるので、ここは大きな違いです。
他には、ネットの高さが通常より高かったり、マッチ数も3セットマッチに限られていたり、とローカルルールがあるのです。
ラージボールは、通常よりも大きなボールを使うことで、ラリーを長く楽しめるという利点があります。
まとめ

卓球豆知識を紹介しました。
いかがでしたでしょうか、卓球をプレーしている方であれば、いくつかご存知のものがあったかもしれませんね。
これ以外にも色々と奥深い卓球の世界。
あなたも、自分だけの豆知識を見つけてみてはいかがでしょうか。







