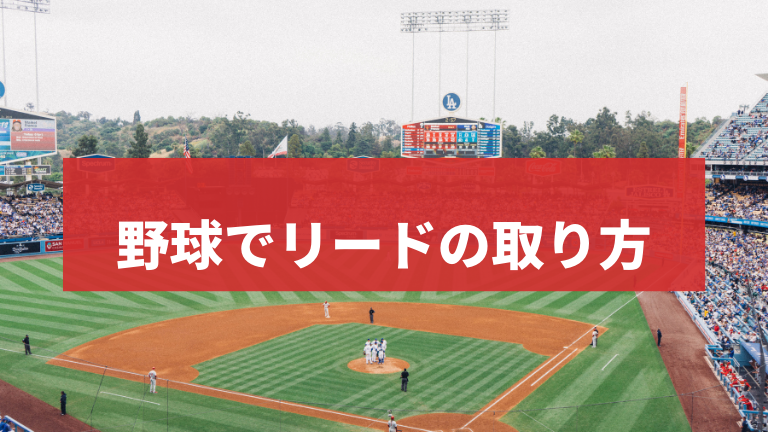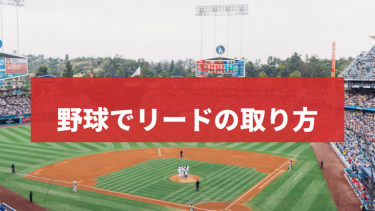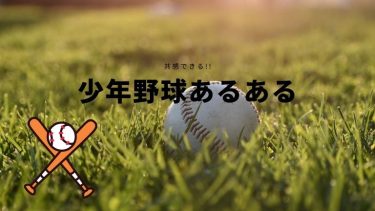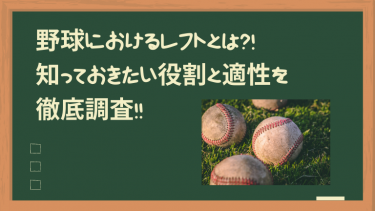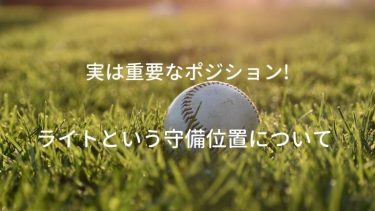プロ野球を見ていると、塁に出たランナーがベースを離れている光景を見たことがあるでしょう。
それがリードというものになります。
これは、少年野球からプロ野球まで、一貫して塁に出た場合には必ずといっていいほど、塁から離れてプレーするのです。
では、なぜランナーは塁を離れてリードをするのでしょうか?
リードするメリットはあるのでしょうか?
リードには種類があるのでしょう?
それぞれについて紹介していきましょう。
野球で塁にでたランナーはなぜリードするのか?

塁にランナーが出ると、必ずといっていいほどランナーは塁を離れてリードを取ります。
リードを取るという事は、塁から離れるために、牽制球や場合によっては、ライナーを取られて塁に戻れないでアウトになる可能性も秘めているのです。
では、なぜ野球では塁に出るとリードをしなければならないか疑問に感じる方もいるでしょう。
リードを取る理由とは何?
野球では、塁に出たランナーは必ずリードを取ってきます。
脚が遅い、速いに関係なくリードを取るのです。
・ピッチャーにバッターに集中したピッチングをさせないため
・守備にプレッシャーをかけるため
・次の塁に進塁する距離を短くするため
の3点がリードを取る理由と考えられます。
ただし、足の速い選手と遅い選手でもリードする意味は大きくは変わりありません。
簡単にいってしまえば、リードは相手のピッチャーや守備陣のペースを乱すことが大きな役割なのです。
例えば、リードをすることで、ピッチャーがあまりにもランナーを気にするあまりに、バッターに集中できずに、
ヒットを打たれたり、フォアボールを出したりする可能性が高くなったりします。
野球のリードは何種類?

野球でリードする意味が、何となく分かってもらえたと思います。
では、リードには何種類の方法があるのでしょうか?
多くの方が種類があるのか?と疑問に思われる方も多いでしょう。
リードには2種類の方法があります。
福井工大福井エース摺石、4点のリードを奪われるも落ち着いたピッチング。
それにしても健大高崎、ランナーのリードが大きい!
今にも走りそう。これは揺さぶられます。#センバツ #甲子園 #高校野球 #選抜センバツLIVE配信中!!https://t.co/5RfDD6itI4 pic.twitter.com/V932BFOj4S
— センバツLIVE! (@SenbatsuLIVE) March 26, 2017
・1次的リード
・2次的リード
に分かれるのです。
これだけでは、なんのこっちゃ!って思ってしまいますよね。
1次的リードってどういうこと?
1次的リードには「ワンウェイリード」と「ツーウェイリード」の2種類にさらに分類されます。
少し難しく感じるかもしれませんが、それほど難しく考える必要はありません。
ワンウェイリードとは
・牽制された場合、すぐに塁に戻れるリードです。
・ランナーは、盗塁するというよりも、塁に戻ることを意識しているが強いリード
・特徴としては、ピッチャーを揺さぶることを目的としているためにリードは大きめ
・リードの大きさは、塁から身長+50cmから70cmが理想的
・基本的には、牽制された場合にはヘッドスライディングで戻る
ツーウェイリードとは
・基本的には盗塁や進塁を狙うリードになりますが、牽制された場合には塁に戻れるリードです。
・特徴は、ワンウェイリードよりも、リードする幅が50cmから1mほど小さい
・相手のピッチャーに盗塁しないと思わせるリード
この2タイプが1次的リードという事になります。
ただ、各選手でリード幅が違うために、見分けるためには1人の選手に注目する必要がるのです。
野球を楽しむのにも、あの選手のリードがさっきよりも大きい・小さいという事を見比べるのも、ちょっとした楽しみ方になります。
2次的リードってどういうリード?
1次的リードは、ピッチャーとの駆け引き的要素が強いリードになりますが、2次的リードは、ピッチャーが投げた後に、
1次的リード+キャッチャーに体を向けながら、足を交差させないように1・2歩リードを広げることをいうのです。
小難しい言い方をすると、リードオフといいます。
状況によっては、進塁をすることを意識していますが、キャッチャーからの牽制もあるために、ランナー自身が塁に戻れるギリギリで行う事になるのです。
これは、常に体を動かしていることで、進塁にも塁に戻るにしても動きがスムーズにできることになります。
人間の体の構造上、止まった姿勢から動くという行動よりも、動いている姿勢から動く方が、スムーズに体を動かせることが出来るのです。
野球のリードのメリットやデメリットは?

リードの種類やリードの取り方がわかったのではないでしょうか。
では、野球でリードすることで、メリット・デメリットはあるか考えてしまいますよね。
アウトになりたくなければ、リードをしなくて塁上にいればいいわけです。
では、野球でリードしなければならないのでしょう。
リードをするメリットとは?
野球でリードするメリットとはどんな事なのでしょう。
・1塁、2塁ランナーの場合には、ワンウェイリードをすることで、ピッチャーがバッターに集中させないようにすることが出来る。
・ランナーがワンウェイリードをすることで、内野の守備にもプレッシャーをかけることが出来る
・2塁ランナーのみの場合には、アウトカウントでリードのする位置が変わることで、外野や内野の守備にプレッシャーをかける
・3塁ランナーの場合は2次的リードをすることで、スクイズを警戒させることが出来る
・ワンウェイリードで、リードが小さいからといってピッチャーに盗塁をしないと考えさせる
などの事が考えられます。
ランナーはただ、進塁することを目的ではなく、ピッチャーや守備陣にプレッシャーをかけることが、主な役割と考えてもいいです。
盗塁しなくても、その素振りをするだけで守備の混乱を引き起こすことができるようにもなります。
また、リードから走った場合にも、キャッチャーからの送球のミスを誘う可能性や盗塁成功によってピッチャーに
ヒット1本でランナーがホームに帰るというプレッシャーをかけることが出来るのです。
野球のリードでのデメリット
メリットがあれば、当然ながらデメリットは存在します。
高知中央高校…
タッチもロスなく、空タッチでもない。よく見るとセンターの喜び方からもアウトにしか見えない。
ランナーの指が長いのか(笑)
この場面はまさに勝負の別れ目‼️3-0中央リード…ツーアウト満塁のピンチからのワンシーン‼️
プロ野球と違いビデオ判定なし、だからこそしっかり見てほしい。 pic.twitter.com/TReiMRXjbX— 最後は気持ち!デブかわドットコム (@debukawa_com) July 26, 2021
・ワンウェイリードを大きく取り過ぎて塁に戻れず、牽制でアウトになってしまう。
・ツーウェイリードで、盗塁を狙ったが相手に察知されて盗塁を阻止されてしまう。
・2次的リードを大きく取ってしまい、キャッチャーからの牽制球で塁に戻れずアウトになってしまう。
・2塁ランナーの場合、塁に戻る事をあまりに考えるあまりに、ヒットでホームに帰れず3塁の進塁に止まってしまう、またはホームでアウトになってしまう。
リードのデメリットは、牽制球はリードの大小によって試合の流れを止めてしまう可能性があるという事なのです。
リードをしていて、牽制球でアウトになってしまう場合には、完全にランナーのミスになります。
これは、ランナーの一瞬の気のゆるみや経験値の差が大きくかかわっていると考えていいでしょう。
まとめ

野球でリードする方法や種類・メリットデメリットを紹介! について紹介してきました。
確かに、イチロー選手や大谷選手などのリードを見る限り、かなり大きく取っていることがわかると思います。
ワンウェイリードをしているのですが、ツーウェイリードも兼ねているという事になるのです。
リードをする場合に考えていることは、次の塁に進塁することなのですが、そこに一瞬のスキが出来たりします。
プロ野球選手でさえ、ピッチャーの牽制球にリードしたままの状態でアウトにされてしまう事もあるのです。
それだけ、ピッチャーも足の速い選手や遅い選手によって、バッターに集中するかしないかを決定している可能性が考えられます。
リードと牽制球は確かに試合を遅くする原因ともいわれていますが、それだけピッチャーが集中を欠いているともいえますよね。