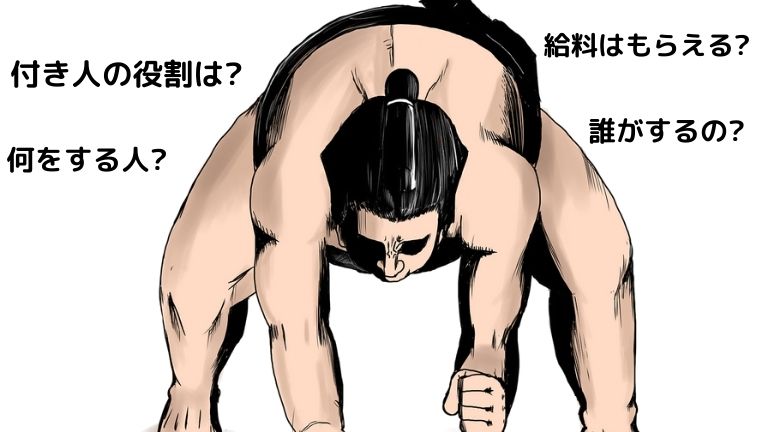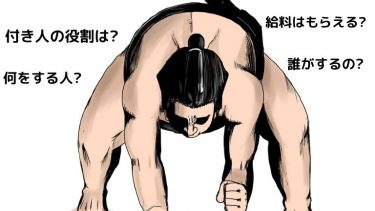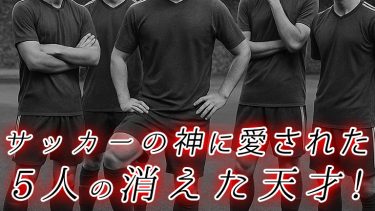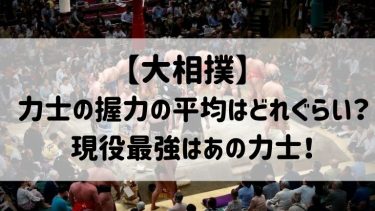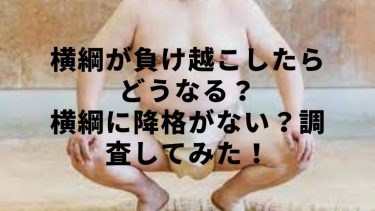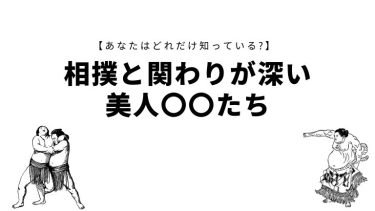日本の伝統文化でもあり、国技にもなっている「大相撲」。
そのはじまりは古く、古事記や日本書紀にも記されているほどです。
悠久の時を越えた現代も相撲の人気は絶大です。
横綱をはじめ、大関、関脇、小結の三役から、幕内力士と、それぞれが力強く、個性的な相撲でファンを魅了しています。
しかしその陰で主役たちを支え、裏方として欠かすことができない「付き人」とよばれる人たちがいます。
今回は力士なら誰でも1度は経験する付き人にスポットをあて、その役割、仕事など詳しく解説していきます。
大相撲のはじまり

「付き人」について詳しく解説する前に、まずは簡単に相撲のはじまりから現代までを紹介します。
奈良時代から平安時代
古墳時代の埴輪に力士の形をしたものがあり、古事記や日本書紀にも記述が見つかるほど、古くから相撲がおこなわれてきました。
当初は力くらべに勝った者に朝廷から領地を授けられたのですが、奈良時代や平安時代になると、当初の力くらべから、神事や祭り、儀式としての要素が強くなります。
五穀豊穣、天下泰平を祈り、天皇や貴族の前、宮中で相撲がおこなわれるようになりました。これが徐々に全国各地にひろまっていきます。
鎌倉時代から戦国時代
武士の時代になり、相撲も純粋に強さを争そうようになりました。
武将たちも相撲の強い者たちを集めて、戦の戦力にするようになります。
かの織田信長も相撲が好きで、よく城で相撲を催しては勝者を兵として使ったようです。
江戸時代から現代大相撲へ
相撲人気が続き、職業としての相撲がはじまります。勧進相撲といって各地で興業がおこなわれるようになりました。
雷電、小野川、谷風など人気力士も登場して、相撲人気は益々拡がり、娯楽として歌舞伎とともに庶民の間で定着していきました。
ルールも整備され、スポーツとしても普及していき、今も当時と形をほとんど変えることなく、人気を博しています。
力士の番付・階級
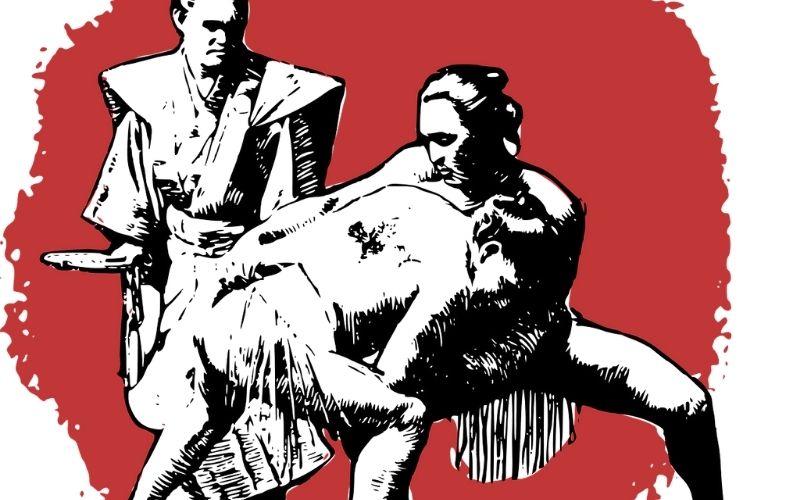
ここでは相撲の格付けや階級、相撲に関わる人たちを紹介します。
- 横綱
相撲界の頂点、最高番付。しめ縄をつけて土俵入りをおこなうので横綱とよばれます。
1789年、谷風梶之介、小野川喜三郎の両力士が初めて土俵入りをおこなったといわれています。
- 大関
大関の関は関門の関からとったといわれ、関門を守る強者のことを指し、その中でも特に強いものが大をつけ大関とよばれるようになりました。
- 関脇
大関の次に強い者、大関の脇に位置するので関脇とよばれます。
- 小結
小結の名称の語源は、諸説あるのですが、ひとつには大関、関脇がいない興行で、結びの一番を取った者を小結とよんだところからといわれています。
- 幕内
前頭筆頭から前頭何枚目とよばれます。幕内の定員は42名とされています。
- 十両
正式な名称は十枚目といいます。十両になってはじめてプロ、関取とよばれ給料が支給されます。
- 幕下・三段目・序二段・序の口
幕下以下は、正式には力士養成員とよばれています。関取となる十両目指して壮絶な闘いが繰り広げられます。
大相撲に欠かせない人たち
- 行司
力士の階級のように行事にも格付けがあり、立行司を筆頭に、三役格行司、幕内格行司、十両格行司などがあります。
ちなみに行司が持っている軍配ですが、戦国時代に武士が相撲を取るとき、武将が持っていた軍配で勝負を裁いたところから使われるようになったといわれています。
- 呼出
こちらも力士、行司と同じく格付けがあり、立呼出、副立呼出、三役呼出、幕内呼出、十枚目呼出などがあります。
- 床山
力士の髪を結っているのが床山さんです。十両以上の力士が結うことのできる大銀杏や、幕下以下のいわゆる、ちょんまげを結う仕事です。
力士を支える「付き人」
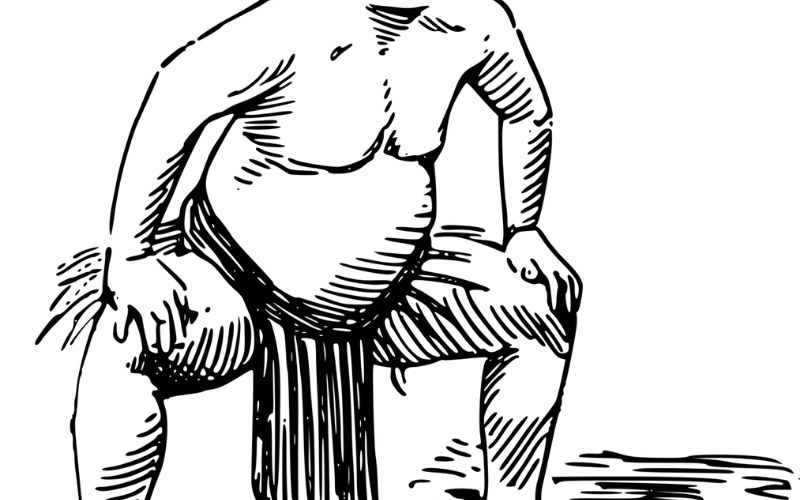
大相撲について簡単に説明してきました。ここからは、付き人について詳しく解説していきます。
付き人とは?
- 付き人の役割
相撲の付き人とは、十両以上の関取に付き稽古から本場所、日常生活にいたるまでの、身の回りの世話や雑用をする人のことをいいます。
- 付き人は誰がするの?
付き人をつける関取と、同じ部屋の幕下以下の力士が付くことになります。
相撲の世界は実力社会で番付が優先されるので、先輩後輩や年齢は関係ありません。よって後輩や年下の付き人をすることも珍しくありません。
また、その部屋で付き人が足りなくなれば同門から力士を借りることもあります。
- 1人の関取に何人付くの?
| 横綱:8~10人
三役:4人~6人 幕内:2人~4人 十両:1人~3人 |
人数に規定はないのですが、この人数が目安になります。また親方や行司にも付き人がつく場合があります。
付き人の仕事と給料
- 本場所
本場所の主な仕事は、明け荷とよばれる、締込みや化粧まわしなどが入った道具箱の運び込みや、回しを巻く手伝い、
花道のボディーガード役などになります。
- 稽古場&部屋
稽古の時は準備運動を手伝ったり、関取の汗を拭いたり、水を差しだしたりと常に気を配ります。
稽古が終わった後や、稽古がない日は、食事や風呂の世話、部屋の掃除に買い出しなど、細々した雑用が多くなります。
- 給料
いろいろと雑務をこなす付き人ですが、実は給料は支給されていません。
相撲協会からは幕下以下の力士へのは給料がなく、その代わりに場所手当といわれるものが2ヶ月に1回支給されます。
| 【場所手当】
幕下:15万円 三段目:10万円 序二段:8万円 序ノ口:7万円 |
生活していくのには少ない金額のような気もしますが、衣食住のうち、食べることと住まいは部屋住みなので心配いりません。
また付いている関取が、食事に連れて行ってくれたり、お小遣いをくれたりします。
ねぎらい金とうい名目のお金を付き人に包む習慣もあるようで、普通の生活には困ることはないようです。
付き人と関取の関係
関取と常に行動をともにし、気を配りながら、身の回りの世話をする付き人ですが、関取との関係は決して主従関係ではありません。
付いている関取から稽古をつけてもらい、相撲界のしきたりを学び、社会人としてのマナーや言葉遣い、礼儀作法を教えてもらいます。
教える関取のほうも、自分の付き人を力士としてはもちろんのこと、人として育てていくという大きな責任があります。
関取、付き人どちらも互いに信頼しあい、支えあい、強い絆で結ばれていきます。
まとめ

横綱や大関の力強い相撲や、小兵が大きな力士を投げ飛ばす痛快な相撲、多彩な技を繰り出す力士など、
どれも土俵を大いに盛り上げる大相撲の魅力です。
そんな関取たちを、陰で支え無くてはならない存在が今回紹介した付き人です。
将来の関取目指して日々精進している付き人たちにも注目し、これからも大相撲を楽しんでください。