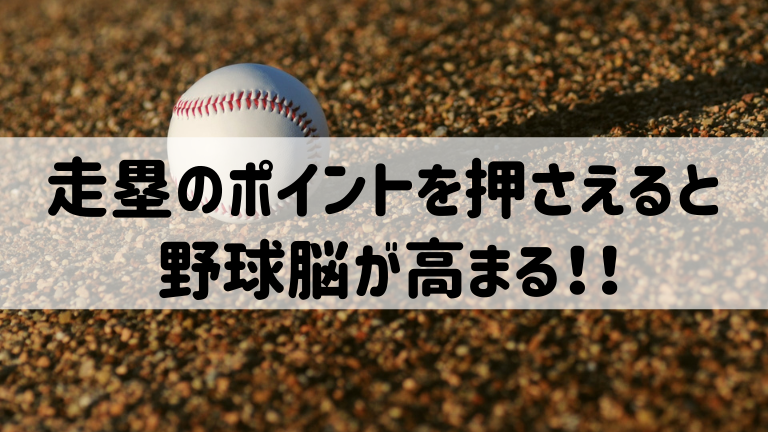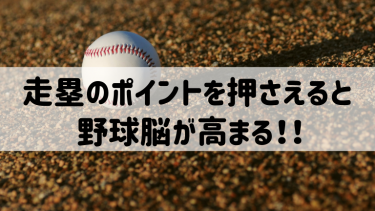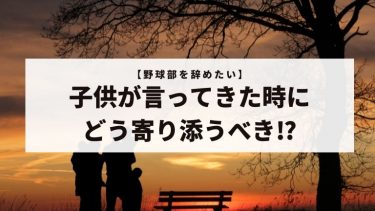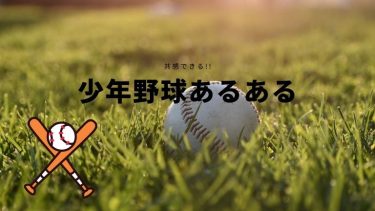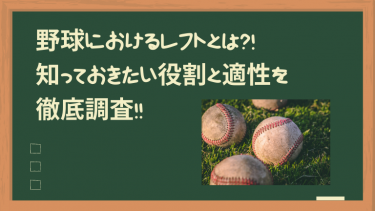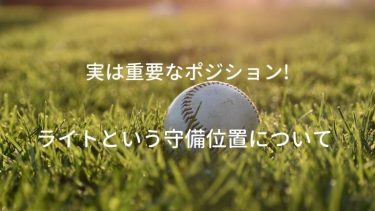野球は【走・攻・守】から成り立つスポーツです。今回は【走】の部分に絞って、その重要性を解説します。
野球脳(野球に関する基本的なルールというよりも、シチュエーションに応じてプレーができる能力)がしっかりしている人は、
走塁についてポイントをきちんと押さえているということが分かります。
野球における走塁の位置づけとは
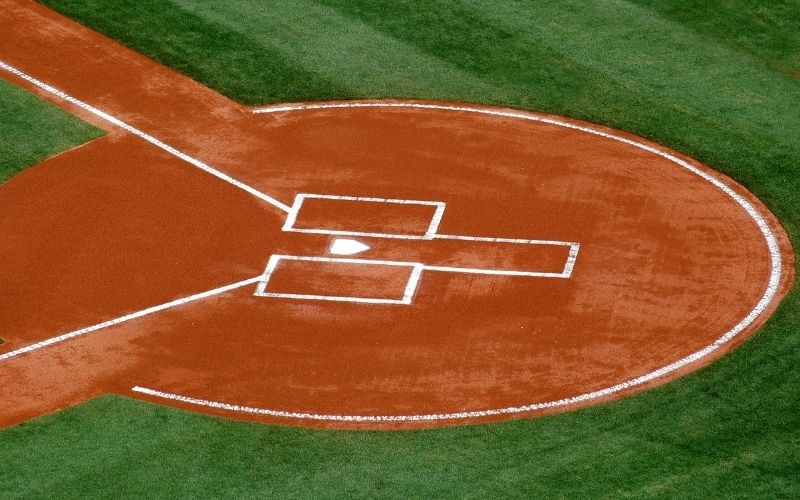
【走・攻・守】の中で【走】については、他の二つに比べて、少し軽んじられる傾向があります。
野球の練習をする際は、バッティング練習や守備練習に割かれる時間は多いですが、走塁練習をする時間は少なくなります。
友達と「野球をしよう」といって集まったときに、走塁練習ばかりしている集団はいません。もしいたとしたら余程ストイックな走塁集団です。
やはり、一般的には野球の醍醐味は打つことと、守ること(投げること)とされています。特に経験が浅い初心者にとっては、
走塁は取るに足らないものと思われがちです。
そんな【走】ですが、軽んじてはいけません。【走】の意識が低いチームは、特に1点を争うような緊迫したゲームで、泣くことになりかねません。
以下の項目では、具体的な場面ごとの走塁のポイントをお伝えしつつ、その重要性についても解説します。
普段あまり重きをおかれない走塁という部分をしっかりと認識して、野球脳を鍛えましょう。
場面によって、走塁で意識するべきポイント

野球の攻撃中、様々なシチュエーションがあります。
・ワンアウト
・ツーアウト
・1塁
・2塁
・3塁
・1-2塁
・2-3塁
・1-3塁
・満塁
これらの状況によって、様々な組み合わせが考えられます。走者はどういった場面でどのような走塁を行うのか、常に頭に入れておかなくてはいけません。
打者走者
まずは、打者走者について解説します。
打者走者は基本的にはどのアウトカウントであっても、塁上に走者がいるいないにかかわらず、ボールを打てば全力で走る。これが基本になります。
フライが上がったとしても、平凡なゴロを打ったとしても、相手守備のミスがあるかもしれませんので、力を抜いて走るという事はしてはいけません。
チームの士気が下がる原因にもなります。
例外的に、ピッチャーが打者の場合は、次の回の投球に影響が出る場合があるので、全力走塁は求められないこともあります。
打者走者は、アウトかセーフが際どいタイミングの際は、1塁ベースを駆け抜けてファールグラウンドに出るという走塁が基本となります。
また、ヒットを打った際は、常に先の塁を狙う走塁が大切です。
このため、1塁ベースをオーバーランして、2塁ベースを狙う動きをする必要があります。
オーバーランし過ぎて、1塁への返球があった際に、タッチアウトにならないよう、注意しましょう。
1塁走者
1塁走者は、盗塁も含めて相手バッテリーを揺さぶる選手が良い選手とされます。やはり足の速い選手は嫌がられます。
リードをしっかりと取ることで、相手バッテリーにプレッシャーをかけることができます。
仮に足に自信がなくても、第二リードをしっかりと取るということはできます。チームとして、このような意識づけはしっかりとするべきです。
そして、1塁走者はノーアウトやワンアウトという場面では、ライナーバックを意識しましょう。
ライナーバックというのは、打者が打った打球がライナーだった場合、走者が飛び出してしまうと、
たちまちダブルプレーになってしまうという事態を避けるプレーです。
常に、どんな打球がどこに飛んだら、どう動こうということを頭に入れておく必要があります。
2塁走者
2塁走者は、ワンヒットでホームに帰ってこれるかが、最大のポイントです。
そのためには、第二リードをサボらずにしっかりと取ることや、相手の守備陣形を常に意識しておく必要があります。
また、同じようなヒットが出たとしても、点差やイニングによっても、ワンヒットでホームに帰るべきかどうかが変わるのが野球の面白いところです。
例えば5点差で負けている場面でヒットが出た場合、2塁走者はホームでの際どいクロスプレーになるタイミングでは、
無理に突っ込まず3塁でストップするのが一般的です。点差が開いた場面では、走者をためていくことが最優先とされるからです。
また、ツーアウトといった場面では、2塁走者はホームでのプレーが際どいタイミングになる場合、勝負をかけるというケースが多いですが、
ノーアウトやワンアウトの場合は、3塁でストップするケースがあります。
これも、ノーアウトやワンアウトの場合は、チャンスのまま次の打者で点が入る可能性が高いという判断により、塁上に走者を残すというものです。
点差、イニング、次の打者など、打球の速度、相手の守備陣形など、様々な状況判断が求められるのが2塁走者です。
もっとも、3塁を回るかどうかの判断はサードコーチに任されるという事が一般的ですが、走者自身、しっかりと意識をしておく必要があります。
3塁走者
3塁は、ホームに一番近い塁ということもあり、微妙な当たりの内野ゴロや、犠牲フライで生還できるかどうかが重要です。
ツーアウトの場合は、とにかく打球が前に飛べばホームに向かって走るだけなので簡単ですが、
ノーアウト、ワンアウトの場合は、試合状況によって動きを変える必要があります。
内野手は前進しているのか、外野手の肩の強さはどのくらいか、このような情報は大前提として認識します。
これに加えて、点差やイニングを考えた上で、ギャンブルスタート(ボールがバットに当たった瞬間走る)するのか、
ゴロゴー(打球がゴロだと分かった瞬間走る)するのかなど、頭に入れた上でプレーしなければなりません。
さらには、ピッチャーのワイルドピッチなどで、キャッチャーがボールをわずかに弾いたケースでも、ホームに突っ込むか止まるのか、瞬時に判断する必要があります。
まとめ
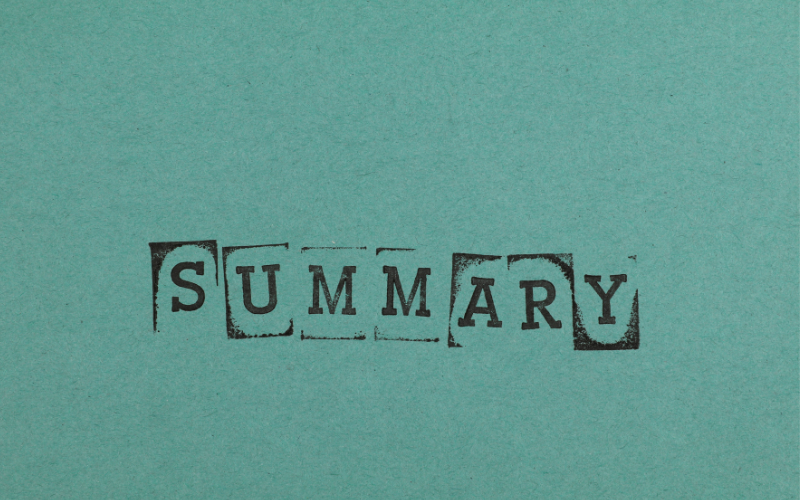
今回は走塁のポイントを場面ごとに解説しました。
野球の知識(野球脳)が一番発揮されるのは走塁の場面と言っても過言ではありません。
走者は常に試合状況(点差・イニング・ボールカウント)を頭に入れて、可能な限り次の塁を狙う必要があります。
プロ野球の世界では、走塁のスペシャリストと呼ばれる存在もいるように、走塁一つで試合の流れが一気に変わることはよくあります。
ただ1つのファーボールから代走が出て、盗塁、内野ゴロ、犠牲フライで1点が入るというケースは相手チームにものすごいダメージを与えます。
チーム全員の走塁意識を向上させることで、接戦で貴重な1点をもぎ取ることができるチームができるのです。