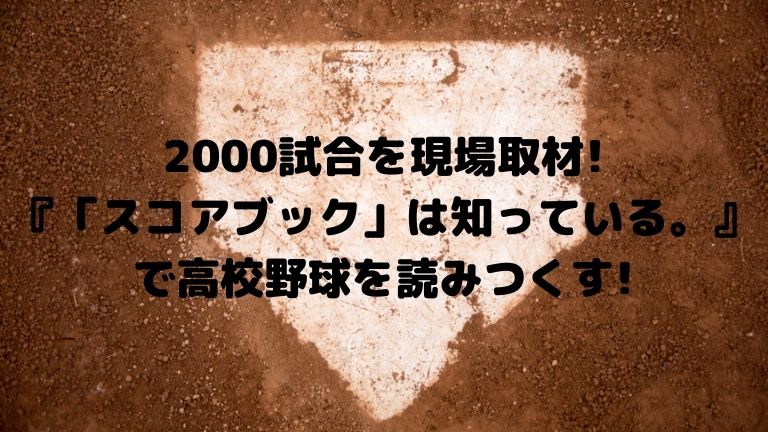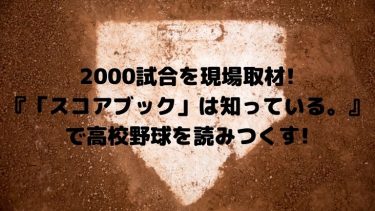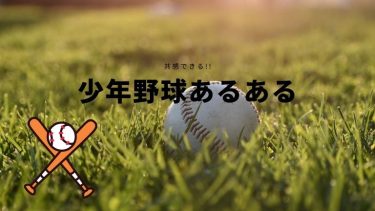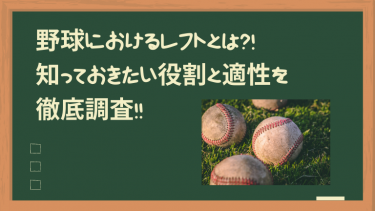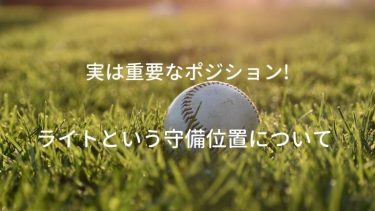春夏の甲子園において約2000試合を現場で取材し、スコアブックに記録してきたスポーツライターの楊順行。
眼前に繰り広げられるドラマを、歴史の証人として、数字、記号、メモに置き換えてきました。

今回の記事では、書籍『「スコアブック」は知っている/楊順行/KKベストセラーズ/2015年』の内容を紹介し、
スコアブックが物語る高校野球の魅力と問題点に迫ります。
松坂大輔と2人の名将

通算58勝のプロ製造機
著者の楊がとくに印象深いとするのは、1998年春夏と2006年夏のスコアブックです。
1998年の高校野球を席巻した横浜高校の投手・松坂大輔。
楊は、春夏連覇の横浜に敗れ去った2校の名将にスポットをあて、松坂の怪物ぶりを際立たせます。
PL学園の中村順司と、明徳義塾の馬淵史郎です。
「松坂、ガッツポーズする余力もない」と走り書きされた、ぼろぼろのスコアブック。
延長17回までもつれた春のセンバツ準決勝における、横浜対PLの試合終了直後に書かれたメモです。
98年当時の甲子園で、松坂大輔と2回対戦した唯一のチームがPL学園でした。
PL学園・中村監督の戦績は、高校球史100年のなかでも突出しています。
甲子園通算58勝。
しかもその勝利数を、わずか18年という短期間で積み上げてきました。
センバツ準決勝で横浜に破れた中村は、松坂に引導を渡されるかたちで勇退することになります。
本人は「選手に恵まれた」と謙遜しますが、在任中に35人のプロを排出しただけでなく、
1981〜1998年までの全学年でプロ選手を生み出した手腕は他に類を見ません。
コト起こしの史郎
PL学園の中村監督に、1998年のセンバツで甲子園最後の勝利を記録させたのが、馬淵史郎が采配を振るう明徳義塾です。
愛媛県の八幡浜市出身の馬淵。
「漁師になりたかった」と語る名物監督は、地元の三瓶高校から東都リーグ2部の拓殖大学野球部に入部しました。
甲子園の出場経験はなく、選手としての経歴は華やかではありません。
高校時代から「コト起こしの史郎」と呼ばれていたほど、トラブルメーカーの側面もあります。
社会人野球ではチームを転々とし、やがて縁あって明徳義塾高校の監督に就任。
1992年の夏には、星稜・松井秀喜への5打席連続敬遠を指示したとして日本中を騒然とさせます。
そして、1998年の夏。
むかえた準決勝の相手は、松坂大輔を擁する横浜高校です。
前日の激闘を考慮して、横浜はエース松坂の先発を回避。
8回の裏までは、明徳義塾が6-0と大量リードしていました。
しかしここから、スコアブックをつける手が震える展開に、、、。
8回裏の攻撃で、相手のエラーをきっかけに4点を返した横浜。
9回の表には、満を持して松坂を登板させます。
マツザカコールにつつまれる甲子園。
流れが大きく変わりました。
球場全体を味方につけた横浜が、9回に3点を奪い7-6でサヨナラ勝ちしたのです。
スコアブックで7点目のホームインを表す、7を丸で囲った部分は歪んでいました。
「1998年の春夏が特に印象的なのは、松坂大輔を交点とした人間ドラマが、例年にもまして濃密であったからだ」と著者の楊は記しています。
北の怪物vsハンカチ王子

2006年の夏で記憶にも記録にも残るのは、駒大苫小牧・田中将大と早稲田実業・斎藤佑樹の投げ合いです。
じつは両雄が最初に対峙したのは、ともに高校2年の神宮大会での準決勝。
4回の攻撃途中まで3点をリードしていたのは、早稲田実業でした。
しかしここで、駒大苫小牧は田中をマウンドへ送ります。
北の怪物と呼ばれた男の決め球は、135キロ超えの「消えるスライダー」。
高校生が打てるレベルではありません。
スコアブックに刻まれた三振を表すKの数は、9回終了時で16におよびました。
試合は、駒大が5対3で逆転勝利します。
そして、高校球史に残る名勝負が生まれた2006年の夏。
田中と斎藤は、決勝の舞台でふたたび相まみえることとなります。
名門の早稲田実業が夏の甲子園初制覇か、はたまた駒大苫小牧が戦後初の3連覇を果たすのか、、、。
本書には実際のスコアブックも記載され、呼吸を忘れるような熱戦の臨場感が秀逸です。
また、社会現象になった斎藤佑樹のハンカチは現場のスタンドからほとんど見えず、楊は話題になっていたことを大会後に知りました。
スコアブックと「高校生らしさ」

高校野球の暗黙のルール
楊は本書で、SNSを中心にたびたび議論の的となる「高校生らしさ」についても言及しています。
2014年夏に甲子園を沸かせた、健大高崎の「機動破壊」。
2回戦の利府との試合では、スコアブックに盗塁を表すSが計11個ならびました。
大会記録の1試合13個に迫る圧倒的な走力を武器に、健大高崎は10対0で勝利します。
健大高崎・青柳監督の考え方はこうです。
「強打のチームは、毎年はつくれない。その点、足にはスランプがない。走るチームなら、毎年つくれる」
ただこの試合で物議をかもしたのは、8点リードでむかえた8回の盗塁。
「対戦相手を侮辱している」
「点差が開いたら盗塁しないというマナーは教えないのか」
ネット上に批判的な意見が投稿されたのです。
たしかに、派手なガッツポーズ禁止など、高校野球にも暗黙のルールはあります。
大差のついた試合終盤に、勝っている側は盗塁しないというモラルが存在するのも確か。
ただ技術的にも精神的にも、ブレが大きいのが高校生です。
1998年の夏に横浜が明徳義塾につけられた6点差を、8、9回だけで逆転したように、甲子園の歴史で大逆転劇は多々あります。
やり玉に挙げられた健大高崎の盗塁もその後の得点に結びついており、もし利府が終盤に粘っていれば勝敗を分けるプレーになっていたかもしれません。
遅いボールがマナー違反!?
また2014年の夏には、東海大四の西嶋亮太が武器にした50〜70キロの超スローカーブが、
ツイッター上で「投球術とは呼べない」と批判され、議論を巻き起こしました。
とらえかたによっては、打者をおちょくっているように見えるかも知れません。
しかし楊は、「スコアブックになにも書いてない」とし、論争になるとすら思わなかったとしています。
身長168センチ、59キロと小柄な西嶋がチームに貢献するため、考え抜いて編み出した「頭脳プレー」だからです。
そして、2013年の済美高校。
安楽智大投手の、投げ過ぎ問題です。
センバツでの安楽は9日間で5試合を投げ、トータルの球数は772におよびました。
この短期間での連投に対し海外のメディアが、「酷使。メジャーの投手なら5〜6週分に相当する」と糾弾し、これに日本の大手メディアも追随。
議論となります。
しかし、1998年に春夏連覇を果たした横浜の松坂大輔は、夏の12日間で782球、3回戦以降は4日連続で計535球を投げています。
当時は、松坂をヒーロー扱いこそしても、批判めいた論調は聞こえてきませんでした。
そもそも高校時代の投球数とその後の故障との因果関係は、科学的に証明されていないと楊は言います。
ほかにも2013年夏・花巻東・千葉翔太のカット打法、1995年夏・柳川高校の長髪、
そして1992年夏・星稜対明徳義塾での松井秀喜5打席連続敬遠、、、。
観戦側が高校球児に求める「すがすがしさ」と、
グランド上で全知全能を尽くし「勝利」を目指す姿勢はときに乖離し、摩擦を生むのかもしれません。
まとめ

甲子園には、現場でしか味わえない熱があります。
球場をつつむその瞬間の空気までは、テレビは伝えきれません。
2006年・夏の決勝で、駒大苫小牧と早稲田実業の引き分け再試合が決まった瞬間に、楊は立ち上がって拍手したそうです。
ときに興奮した震える手で、あるときは世間の喧騒から距離をおき冷静に記された甲子園のリアル。
人々の記憶はやがて薄れていきますが、スコアブックだけはドラマを未来に語り継いでいきます。