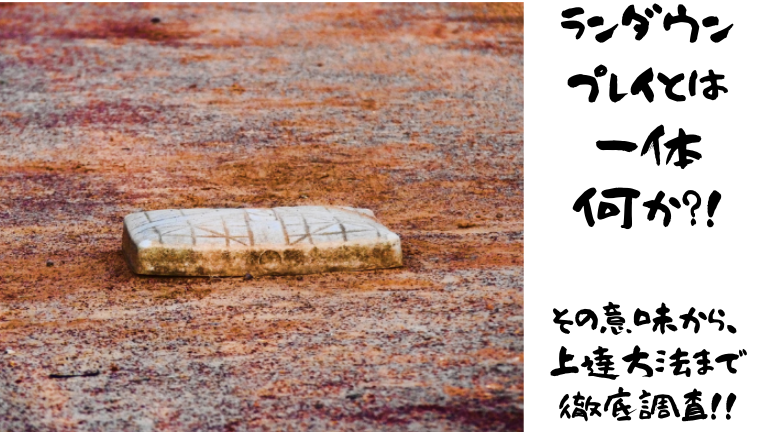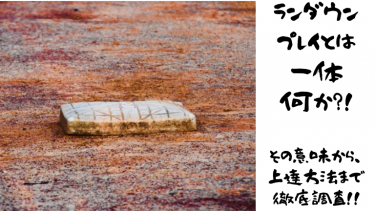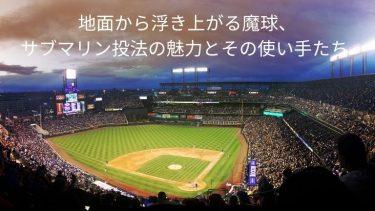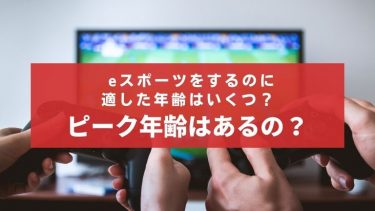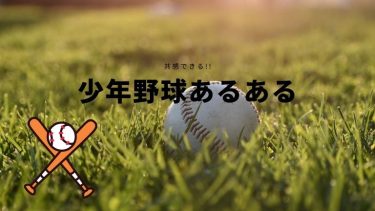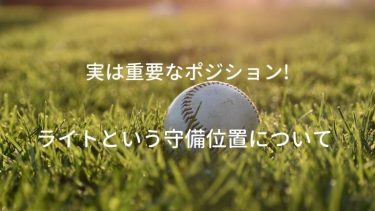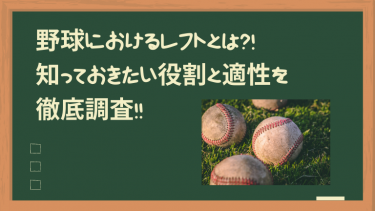野球は好きだけど、自分ではプレーしたことはない、という方も意外と多いのではないでしょうか。
その一方で野球経験がなくても野球が好きなら、長年応援するうちに覚えている専門用語も多いと思います。
そして、野球の世界では1つの言葉を指すのに英語が使用されることと日本語が使用されることが多いのも特徴的なことだと思います。
なぜなら、日本でテレビ中継を見る限り、大相撲で技の名前が英語でアナウンスされることはありませんよね。
しかし、野球では自然にピッチャーとも投手とも言います。
それでは≪ランダウンプレイ≫とは一体何でしょうか。
「初めて聞いた」と思う方も多いかもしれませんね。
実は≪挟殺(きょうさつ)≫のことです。
今日はこの≪ランダウンプレイ(挟殺)≫についてお話します。
ランダウンプレイとは何か?!

ランダウンプレイは≪挟殺≫と呼ばれる、守備側のプレーです。
試合を観ていると、ランダウンプレイでは多くの場合で守備側がアウトをとって終了することが多いですよね。
ところが、アウトをとろうとしているうちに他のランナーが次の塁に進んでしまうこともあります。
さらには、アウトをとろうとしてボールを悪送球した結果、ランナー全員が進塁してしまうことも、
最悪の場合、得点を与えてしまうこともあります。
ランダウンプレイとは難易度が高いプレーなのです。
野球ファンならプレー自体は観たことがあると思いますが、どのようなプレーなのか確認してみましょう。
ランダウンプレイの意味
まずは≪ランダウンプレイ≫という言葉についてご説明します。
≪ランダウンプレイ≫とは、“走る”という意味の「run(ラン)」と“下げる”という意味の「down(ダウン)」を組み合わせた野球用語です。
塁間にいるランナーを守備側のプレイヤーははさんで、アウトにしようと追いかけます。
それを回避するために、ランナーは次の塁に向けて走ったり前の塁に戻ったり(ダウン)することから、ランダウンとよばれます。
ランダウンプレイが起こる状況
ランダウンプレイは次のような状況で発生します。
- 牽制球の際にランナーが飛び出していてはさまれた時
- スクイズに失敗してホームに向かうランナーがはさまれた時
- 内野ゴロの際の走塁ミスでランナーがはさまれた時
- 外野からのバックホームの際にランナーがはさまれた時
ご覧の通りランナーのミスで発生するので、ランダウンプレイでアウトをとれることは守備側のチャンスを広げるだけでなく、士気を高めます。
逆にランダウンプレイでアウトをとれなかった場合、攻撃側はミスを帳消しにできるだけでなく、
一気に追撃や反撃のムードを高めることができます。
ランダウンプレイを成功させるコツとは?!

相手のムードを良くしないためにも、なんとしても確実にアウトがとりたいランダウンプレイ。
それでは、ランダウンプレイを成功させるにはどうしたらいいのでしょうか。
そのポイントを順番に見ていきましょう。
前の塁(ホームベースから遠い塁)に追い込む
少しでも失点を防ぐための守備なので、守備陣はできるだけホームベースから遠ざけるように追い込みます。
偽投は避ける
偽投とは文字通り、≪投げたフリ≫です。
偽投は一見ランナーを惑わせてアウトをとりやすくなるように思えますが、残念なことに味方も惑わされてしまいます。
つまり、ミスにつながる可能性が高くなってしまうのです。
ルールとしては禁止されていませんので、絶対にダメではないのですが、ミスが生じればランナーは進塁してしまいますから、避けた方が無難です。
送球の回数はできるだけ少なくする
送球の回数が多くなるとその分悪送球や落球などのミスが発生する可能性が高くなります。
また、他にランナーがいる場合は送球回数が多くなることで時間的な余裕ができ、進塁のチャンスを与えてしまいます。
そのため、できるだけ少ないやりとりでアウトをとれることが理想です。
捕球したらすぐに投げる
捕球したボールを握りなおしてすぐに投げることを、スナップスローと言います。
ランナーは次の塁を狙って走っているので、ボールを捕ったらすぐに投げ返すことが必要になります。
しかも、通常の守備とは異なり、この動作を走りなが行わなくてはいけません。
つまり、ランニングスナップスローができることが必要なのです。
これまで何気なく見ていた(かもしれない)ランダウンプレイですが、このようなプレーが要求されるところに、難易度の高さがうかがえますね。
ボールを投げたらすぐにバックアップに回り、バッターからずれる
ボールを持っていない野手がランナーの走路を妨害すると、走塁妨害となってしまい、ランナーは次の塁に進めることになってしまいます。
ランダウンプレイで走塁妨害になってしまうのは痛恨のミスですので、ボールを投げたらすぐに、投げた塁の後ろに回ってバックアップしましょう。
そうすることで、送球回数が多くなってしまったときにもすぐに対応できるようになります。
ボールを見せて、味方がとりやすいボールを投げる
味方がとりやすいようにボールが見えるようにしておくことも重要です。
味方の合図を受けて投げれば、捕球ミスも減るので確実性が高まります。
ランダウンプレイを上達させる練習方法とは?!

先程、ランダウンプレイを成功させるコツをご紹介しました。
≪コツ≫と言ってしまうと、コツをつかめば簡単に実践できそうですが、多くの注意点があり、
スナップスローという技術も身につけていないといけません。
日々の練習が非常に重要だということがよくわかりますね。
そこで、ランダウンプレイを上達させるための練習方法について、非常にわかりやすい動画がありますので、ご紹介します。
ランナーからみたランダウンプレイとは?!

ランダウンプレイとは守備側の技術なので、これまでいかにアウトをとるか、上達するにはどうするか、という視点からお話してきました。
では、ランナーとしてはさまれた場合はどうしたらいいのでしょうか。
今度はランナー目線で重要な点についてみてみましょう。
自分が生き残る
相手のミスを誘って、自分が生き残れることがまず第一に考えるべきことです。
先程、「送球回数が多くなればミスする可能性が高くなる」とお話しました。
つまり、ランナーは一度の送球でアウトにならず、できるだけ多く送球させるようにするとミスを誘える可能性が高くなります。
また、投げ手と受け手がお互いよく見えないと投げにくく捕りにくい状態になりますので、野手と重なるような位置を意識するのも有効になります。
後続のランナーを進塁させる
「できるだけ多く送球させればミスを誘える」とお話しましたが、もうひとつ大きなメリットがあります。
それは、自分がはさまれてランダウンプレーが行われている最中に、他のランナーを進塁させることができる、ということです。
ただし、ひとつの塁に2人のランナーが存在することはできません。
塁にいられる権利があるのはもともと塁にいたランナーです。
つまり、自分がランダウンプレイをしている時に、前の塁にいたランナーが走ってきて、
自分も元の塁に戻った場合は走ってきたランナーがアウトになってしまいます。
まとめ

今回はランダウンプレイの意味・上達方法からランナーからみたランダウンプレイについてお話しました。
≪挟殺≫はよく目にするプレーですが、実は奥が深いものがありましたね。
守備陣のみではなく、攻撃陣にもいろいろな思惑が存在するランダウンプレイの魅力が伝わり、今後ますます野球を観るのが楽しくなれば幸いです。