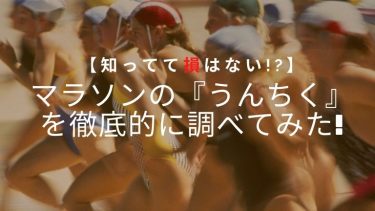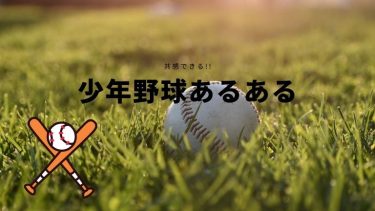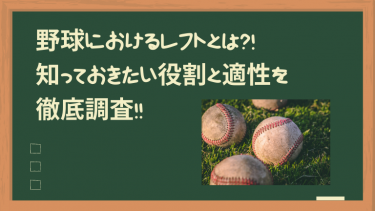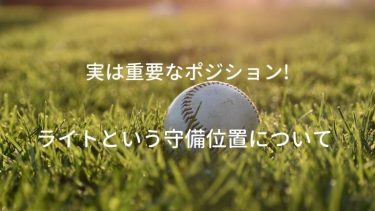高校野球の監督は、野球のことだけでなく生活や教育などあらゆる場面で球児のケアをしていく必要があります。
そんな中で、野球戦術や戦略・指導観や倫理観などが培われていき、それぞれの監督の個性となります。
今回は、個性的な高校野球監督の「名言」について紹介していきます。
高校野球監督の名言
高校野球の監督の名言を紹介します。
小倉全由(日大三高)

「みんな、咲いた花を見るのは好きだけど、咲くまでの過程に興味がない。花が咲くには強い根があってこそ」
小倉全由(まさよし)監督は、1957年生まれの千葉県出身です。
日大三高→日大と進学、日大在籍時には、母校の日大三高でコーチを務めました。
25歳の時に関東第一高の監督に就任、1987年春のセンバツでは、チームを準優勝に導きました。
40歳の時に母校の監督に就任、春1回、夏2回の全国制覇を経験しています。
確かな実績を持った監督ですが、ある有名高校の監督によると、「生徒と話をする時、彼は自慢話をすることなく、自分の失敗談をする」と評されています。
また、胡蝶蘭を育てることが趣味であり、上記の発言は植物を育てる人物ならではのものです。
「練習や普段の生活態度=根」「試合やその結果=花」と考えると、納得がいくのではないでしょうか。
前田三夫(帝京高)

「自主性を間違えるととんでもないことになる。指導者が管理してやらないとダメ」
前田三夫監督は、1949年生まれの千葉県出身です。
木更津中央高(現:木更津総合高)を経て帝京大に進学、選手としての実績は特筆すべきものはなかったようです。
1972年より帝京高の監督に就任し、2021年夏に勇退するまで、実に50年近く帝京高ひと筋で監督を務めました。春1回、夏2回の優勝経験があります。
帝京高での教え子に、吉岡雄二(巨人→近鉄→楽天)、中村晃(ソフトバンク)、山崎康晃(DeNA)などがいます。
上記の名言は、「選手の自主性」が声高に叫ばれていた1990年代末に、チームづくりで失敗したことを受けてのものです。
試合当日の午前中、選手の外出を許可した際に、選手がゲームセンターに行ってしまい、前田監督はそのことをあとから知ったそうです。
結局、チームはその試合に逆転負けを喫し、その反省から選手管理の重要性を再認識します。
選手の自主性をどこまで尊重するかは、線引きが難しい問題です。
前田監督も、こういった自身の経験をもとに、管理と自主性のバランスに悩み続けてきたと言えます。
木内幸男(常総学院高)

「高校野球は大人がどうにかするもんじゃない」
木内幸男監督は、1931年生まれの茨城県出身です。
土浦一高で主将を務めていましたが、甲子園出場は叶いませんでした。
慶応義塾大学に合格していましたが、母校のコーチを務めるために進学はしなかったということです。
その後は取手二高→常総学院高とキャリアを積み、取手二高で夏1回、常総学院高で春1回、夏1回の優勝を経験しています。
上記の名言は、木内監督の指導方針そのものです。特に、取手二高時代はその方針が色濃く出ていたようです。
1984年に取手二高は決勝戦まで勝ち進みました。相手は桑田・清原選手のいる、あの名門PL学園。
緻密なPL学園の野球に比して、木内監督率いる取手二高は「のびのび野球」と呼ばれていました。
前評判ではPL学園が圧倒的有利とされ、大会前の練習試合でもPLが圧勝していましたが、この決勝戦では、取手二高が8-4でPL学園に勝利しています。
その後の常総学院高でも、選手の自主性に任せる指導方針を貫いています。
また、他の高校では一生懸命練習や努力をした選手をベンチ入りさせることが多いですが、木内監督はもっぱら選手の能力を重視してベンチ入りさせることが多く、
高校野球界においては異質と言えます。
狭間善徳(明石商高)

「野球において最も大事なことは、備えること」
狭間善徳監督は、1964年生まれの兵庫県出身です。
明石南高から日本体育大学に進学し、その後は母校や高砂南高で野球部コーチを務めています。
1993年からは明徳義塾中等部の軟式野球部を率いて、4度の日本一を成し遂げました。
2007年に、明石商高の硬式野球部監督に就任しています。
その頃は、ちょうど地元の明石市が市下の野球部のレベル向上のために、野球部指導経験者の教員を募集していた折でした。
明徳義塾高では、馬淵史郎監督の影響を受けて、勝つためのチーム作りがどういうものかを学びました。
「相手チームを徹底的に分析する」「チームが最悪の状態でも、選手が各々最善手がとれるようにする」ことを信条に、明石商高を全国レベルの強豪に育て上げました。
2019年には、中森俊介投手、来田凉斗外野手を擁して春夏ともにベスト4進出という偉業を成し遂げています。
狭間監督の野球は、「とにかく徹底的に相手を研究・分析する」ことから始まります。
相手校に偵察に行って練習風景を録画したり、夜中までビデオをチェックして相手選手の特徴をつかむことに腐心します。
また、練習の際は監督自ら率先して用具の準備や片づけを行うそうです。監督のそんな姿を見て、選手も発奮し試合で実力が発揮できるということですね。
荒井直樹(前橋育英高)

「本物というのは中身の濃い平凡なことを積み重ねること」
荒井直樹監督は、1964年生まれの神奈川県出身です。
日大藤沢高を経ていすゞ自動車でプレー経験があります。
いすゞ自動車では都市対抗野球に7度出場する活躍を見せました。
現役引退後に母校で3年間監督を務め、2002年からは前橋育英高の監督を務めています。
荒井監督が実践しているのは「裸の指導」。ひとりひとりの部員に対して、ごかましなく全力で向き合うのが信条、とのことです。
選手と野球日誌のやり取りをしてコミュニケーションをとる、レギュラーと控えの隔てなく全員に自らノックを行う、などを継続して行っています。
これら「凡事徹底」することで、2013年夏には初出場初優勝の栄冠に輝き、2016年以降夏は5大会連続で出場を果たすなど強豪校の仲間入りをしています。
なお、自らが培った経験を引き継ぐ意味を込めて、前橋育英高のユニフォームのデザインはいすゞ自動車のものを流用しているとのことです。
まとめ
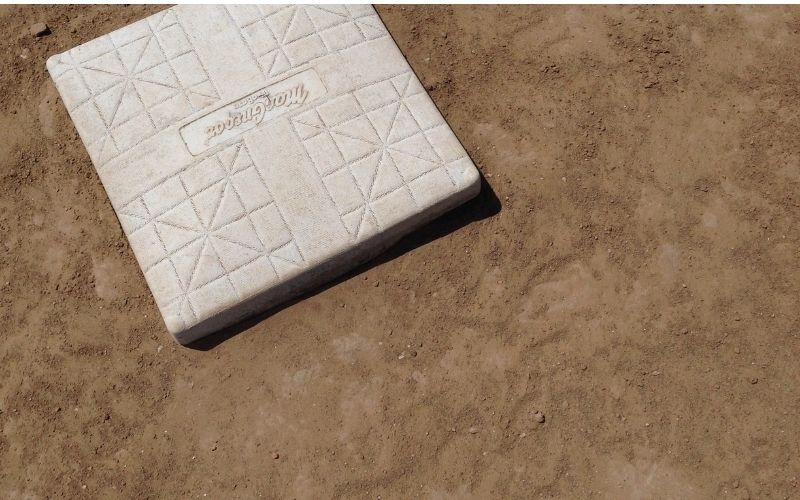
高校野球の監督は、野球の技術や戦術を教える以外にも様々なことに気を配る必要があります。
今回紹介した監督たちには、経歴や考え方などいろいろと個性がありますが、共通するのは「選手に対する思いやりや愛情」です。
練習を厳しくする、あるいはなんでも選手の言うとおりにする、というだけでは選手は育たないし、結局チームも勝てない。
上記の名言はそのことを端的に表していると言えます。
高校野球が始まって100年以上の時間が経ち、選手の性質も変わってきています。
指導者の在り方もさまざまであり、今後も変化していくと思われますが、根っこの部分はいつまでも変わらないのかも知れません。