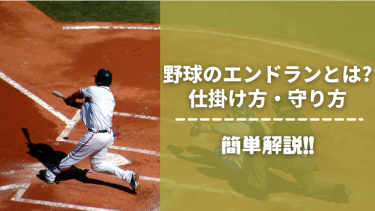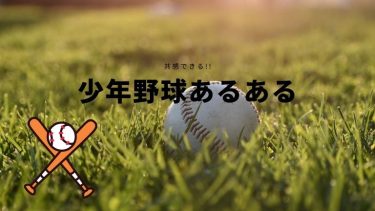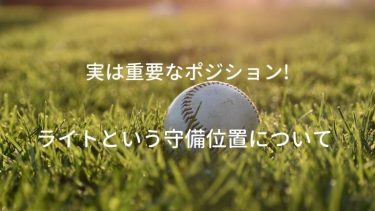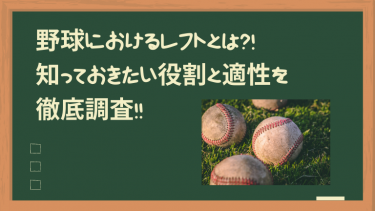楽天の田中将大投手のスプリットや、ソフトバンクの千賀滉大投手のフォークなど、プロ野球ではその投手の決め球・代名詞と言われるさまざまな変化球があります。
しかしながら少年野球では変化球が禁止されています。
この記事では、変化球が禁止されている理由について紹介します。
なぜ変化球禁止なのか?

少年野球で変化球が禁止されている理由について、「全軟連競技者必携」に記載がありました。
それが下記となります。
学童野球における <変化球禁止> について関節の障害防止のため、まだ骨の未熟な学童部の投手に対して変化球を投げることを禁止していて、変化球を投げた場合はペナルティが課せられるそうです。
変化球を投げた場合とは、投球が審判によって変化球と判断された(投手の意図を感じた)場合を言い、すべて審判の判断です。
変化球を投げたときのペナルティは、少年の肘・肩の障害防止が目的で、特に肘や手首などをひねって投げるような投球方法を禁止しているので、監督・コーチは、この点に十分留意して指導しなければいけません。
引用:全軟連競技者必携
基本的には、投手の怪我を防止するために変化球が禁止のルールが設けられているようです。
投手の未来を考えての禁止ということですね。
ペナルティがある

もしも審判が変化球と判断した際は、投げた投手に罰則があるとのことです。
- 変化球に対してボールが宣言されます。
- 投手が変化球を投げた場合は、投げないように監督および投手に厳重注意します。注意したにもかかわらず、再び変化球を投げたときは、その投手は交代させられます。さらにその投手はほかの守備位置につくことは許されますが、大会期間中、投手として出場することはできません。
- 変化球が投げられたときにプレイが続けられた場合は、打者が一塁でアウトになるか、走者が次塁に達するまでにアウトになった場合は、プレイは無効になり、打者のカウントにボールを加えます。ただし、打者が安打や四球などで一塁に生き、走者が進塁するか、占有塁にとどまっている場合は、変化球とは関係なくプレイはそのまま続けられます。
どんな球もボール判定になる
審判によって変化球と判断された場合ストライクゾーンに入ったとしてもボール判定になるそうです。
極端な話ですが、ど真ん中に入ってもそれが変化球であればボール判定です。
改善されない場合は交代させられる
注意しても改善されなかったら注意された投手は交代させられ、さらにその大会期間中は投手として試合に出られないそうです。
もしもチームのエースがペナルティを受けてしまったら、その試合だけならまだしも、大会期間中ずっと投手として試合に出られないのはチームとしても痛手ですね。
打者に有利なペナルティ
あたりまえですが、投手がルール違反をしたので打者に有利な状況になります。
どんなにストライクゾーンに投げたとしてもボール判定になり、変化球を打ってアウトになった場合、それが無効になります。
勝つために変化球を投げてしまうケースがあるかもしれないですが、
結果的に攻撃側のチームを助ける行為になってしまうので投手がわざわざルールを破ってまで変化球を投げるメリットはないですね。
全ては審判の判断

規則に記載されているように、すべては審判の判断に委ねられるということです。
審判は規則に則り判断をすると思うのですが、明確な判断基準が記載されていないためさまざまな問題が考えられます。
そこで考えられる疑問点をいくつか挙げてみました。
意図せず変化してしまったら?
投手が投げた球が意図せずに変化してしまっても、審判が変化させたと判断したらペナルティが与えられます。
規則には、手首をひねるような投げ方はいけないが、握りを変えて投げてはいけないとか、
具体的にこんな投げ方はいけないとは記載されていないので、ここの判断が難しそうです。
投手によっては、ストレートがナチュラルシュートしてしまったり、意図せず手首をひねってしまいそれが変化した場合でも、
審判が変化させたと判断した場合ペナルティになるみたいです。
審判が変化球と判断しても意図して投げていない場合は審判と交渉することはできるのでしょうか?
大事な大会の時に交渉できないと何かしらのトラブルになりそうですが。
詳しく知りたい方は連盟に問い合わせてみてください。
公平性に欠けるのでは?
先ほども書いたように、これをやったらダメというのが、具体的に記載されていないため、公平性に欠ける可能性が考えられます。
こっちの投手は変化球と判断されたが、向こうの投手は変化球と判断されなかったということが起きないように、審判も慎重に見極めないといけません。
少年野球の練習試合だと、どちらかのチームの関係者が審判をすることもあるので、どちらかに有利なようにジャッジできるのも公平性に欠けてしまいます。
仮に投手が意図して変化させても審判が守備側のチームの関係者で、それを良しとしてしまうと、投手が勘違いしてしまい、他の試合でも変化球を投げてしまう可能性も考えられるので、審判にはちゃんと公平に判断してもらわないといけません。
審判はとても責任重大です。
スローボールやチェンジアップなどの緩急は?
少年野球では変化球が投げられないので、緩急を使ってピッチングを組み立てていくと思うのですが、その緩急もどこまでがOKなのでしょうか?
調べてみるとスローボールは大丈夫なのですが、スローボールを投げるときは明らかに腕の振りが遅くなるのでスローボールが来るとバッターに気づかれてしまいます。
そうなるとチェンジアップを使いたくなりますが、一応チェンジアップも変化球のひとつです。
あからさまに変な握り方で投げたら審判に注意されるかもしれませんが、握りを変えて投げてはいけないとは規則に記載されていないため、審判の判断に任せられます。
審判によってOKだったり、ダメだったりとありそうなので、チェンジアップありきでピッチングを組み立てるというのはあまりおすすめはしません。
まとめ

いかがでしたか?
今回はなぜ少年野球では変化球禁止なのかについて調べてみました。
選手のためのルールであることがわかりましたが、規則を見ただけではわからないこともたくさん出てきました。
規則を見てわかりづらいところ、具体的に知りたいことがあれば直接連盟に問い合わせてみるといいと思います。
いずれにしても選手たちには正々堂々と試合をしてお互いを高めあってもらい、これからの日本野球界を盛り上げていってもらいたいですね。