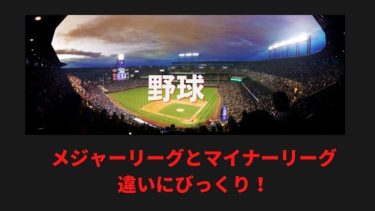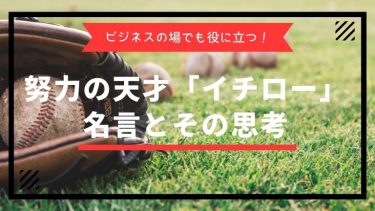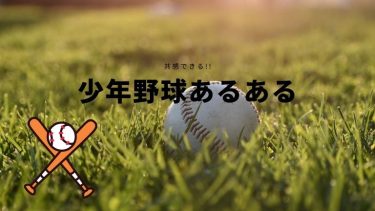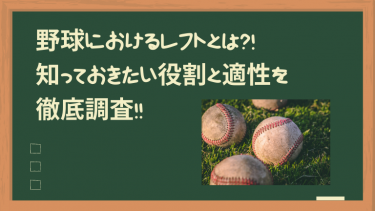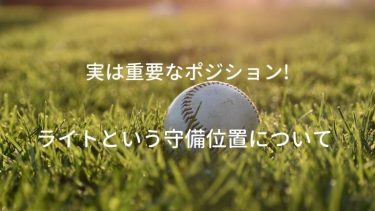野球といえば、相撲を凌ぐ日本の国技と言ってもいいほど、ポピュラーなスポーツです。
今でこそ少なくなりましたが、昔は普通にゴールデンタイムの地上波で放送されていました。
試合が延長戦に入れば、放送時間も当たり前のように延長され、家族ぐるみで贔屓のチームを応援していたものです。
そんな野球を日本に根付かせる基礎を築いたのは誰か皆さんご存知ですか?
何人かいる中でも一度は聞いたことがある名前と言えば、その通り!正岡子規ですよね!
今回は正岡子規がどれほど野球を愛し、野球が日本で愛されるスポーツになるまで、どのくらい貢献したかを掘り下げてみたいと思います。
正岡子規の生い立ち

正岡子規は、1867年9月に愛媛県松山市の松山藩士であった正岡常尚の長男として誕生し、本名は、常規(つねのり)と言います。
子規がまだ4歳のとき、父・常尚は酒好きが災いしてか病死してしまい、母親・八重によって育てられることになります。
八重の父親・大原観山は、儒者であり、その影響を強く受けた子規は、幼少期から漢詩や書画などの学問を学びます。
周囲の環境に恵まれていた子規は、この時期に身につけた教養により、優れた才能を開花させたのです。
その後、数々の俳句や短歌などを創作し、明治時代を代表する文学者になるのです。
柿食へば鐘がなるなり法隆寺
でしょう。
教科書にも登場するこの俳句は、明治28年に子規が、旅先で立ち寄った法隆寺で、好物の柿を食べながら詠んだものです。
季語である「柿」から秋に詠まれた俳句であり、涼しいお寺の境内にゴ〜ンと鳴り響く鐘の音が、なんとも言えない旅情を表していますね。
正岡子規と野球の出会い
1884年に、第一高等学校(今でいう東京大学教養学部)に入学した子規は、すぐに野球に没頭します。
子規は野球以外の競技には全く関心を示すことなく、その野球愛は相当なものだったようです。
ちなみに推薦枠で有力選手をかき集める現代の大学野球とは違い、他に強豪チームが無かった当時の東大野球部は、
向かうところ敵なしの常勝軍団だったようです。
正岡子規の守備位置はどこだった?
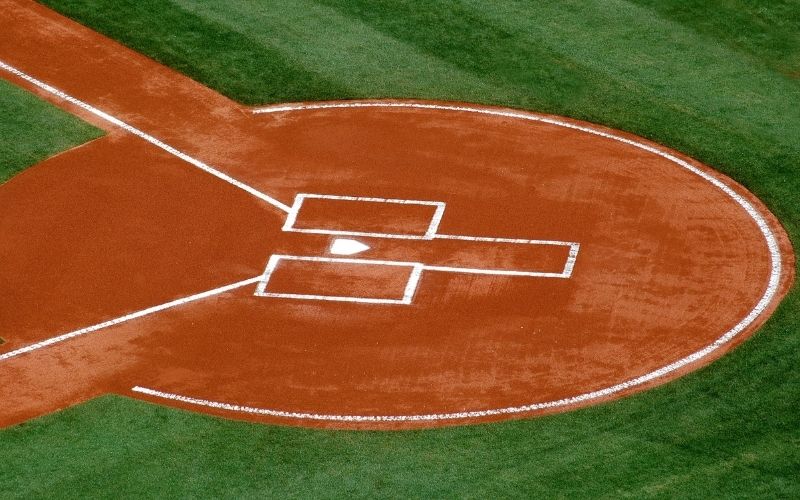
そんな子規のポジションは、キャッチャーでした。
キャッチャーというと、立ったり座ったり投げたりとなかなか重労働なポジションです。
さらに、キャッチャーだけ他の野手とは逆方向を向いているため、チーム全体を見渡す視野の広さが求められます。
野球愛が強かった子規が、チームメイトに指示を出し鼓舞しながら、チームをまとめていた姿が想像できますよね。
野球の語源は?
ところで、ベースボールを野球と名付けたのは誰かご存知ですか?
よく勘違いされていますが、正確に言うと、名付け親は子規ではありません!
ただし、自身の「のぼる」という幼名を文字って、子規が「野球(のぼーる)」というペンネームを使っていたことがあるため、
「野球」という表記を最初に世に広めたのは、子規であることに間違いありません。
本当の名付け親は、子規の後輩にあたる中馬庚(ちゅうまかなえ)という人物です。
中馬は、「Ball in the field」という言葉をヒントに、野原でボールを追い掛けるスポーツという意味からベースボールを「野球」と和訳したのです。
子規が野球に残した爪痕とは

子規は、1896年7月の新聞『日本』の記事中で、野球のルールや道具について解説しています。
さらに、現代でも馴染みのある数々の外来野球用語を和訳しています。
例えば、以下のような言葉です。
「ランナー」⇨「走者」
「フォアボール」⇨「四球」
「ストレート」⇨「直球」
「フライボール」⇨「飛球」
野球に詳しくない人でも知っている言葉ばかりですよね。
ちなみに、子規は、「ショートストップ」という外来語を「短遮(みじかくさえぎる)」と和訳していますが、
現代野球に根付いているのは、「遊撃手」という中馬庚の訳です。
たしかにこっちの方が聞こえ方がカッコイイですね。
野球と俳句
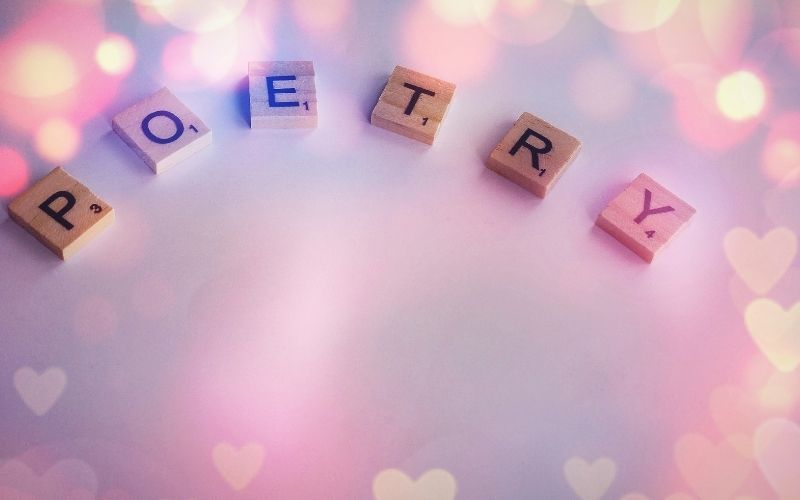
もちろん子規は、野球にまつわる句も新聞『日本』に発表しています。
野球のナインにちなんで、以下の歌九首を詠んでいます。
・國人ととつ國人と打ちきそふベースボールは見ればゆゝしも
・若人の すなる遊びは さはにあれど ベースボールに 如く者はあらじ
・九つの 人九つの 場を占めて ベースボールの 始まらんとす
・九つの 人九つの あらそひに ベースボールの 今日も暮れけり
・打ち揚ぐるボールは高く雲に入りて又も落ち來る人の手の中に
・なかなかに打ち揚げたるはあやふかり草行く球のとゞまらなくに
・打ちはづす 球キャッチャーの 手に在りて ベースを人の 行きがてにする
・今やかの 三つのベースに 人満ちて そゞろに胸の 打ち騒ぐかな
どの句からも、子規が野球に明け暮れる日々を過ごしていたことがよく感じ取れます。
これだけの野球に関する句を詠んでいることからも、いかに子規がこよなく野球を愛していたのかが分かります。
晩年の子規
子規は、1889年5月に初めて喀血してからも、精力的に俳句や記者活動を続けました。
1895年4月に日清戦争へ記者として従軍しますが、その帰りの道中に再び喀血し、意識不明の重体になってしまいます。
その後、神戸の保養所で療養し、松山へ帰郷することになります。
肺結核により多量の血を吐く自身の姿をホトトギス になぞらえ、1897年に俳句雑誌の「ホトトギス」を創刊します。
実は、子規という名称は、ホトトギスを漢字で表した俳号であり、世間によく知られている正岡子規という名前はこのとき、誕生したものなのです。
松山に帰郷してからも、俳句活動を精力的に行う子規でしたが、病魔は容赦なく子規のからだを蝕み、最期の3年間は寝たきりの状態になってしまいます。
そして、ついに1902年9月19日、わずか34歳という若さで死去した子規は、東京都北区田端の大龍寺にあるお墓に眠っています。
まとめ〜日本球界への功績を讃えられる

子規は、喀血するギリギリまで愛する野球を続けていました。
そんな子規の日本野球界への貢献を讃えるため、没後100周年を記念して、ついに野球殿堂入りを果たしました。
短命に終わった子規でしたが、もっと長生きしていれば、有能なスポーツライターとして日本スポーツ界で幅広く活躍していたかも知れませんね。
子規の出身地である松山市内にある坊っちゃんスタジアム内に『の・ボールミュージアム』という野球資料館がオープンしています。
また、1886年から喀血するまで、子規が野球を楽しんでいた上野恩賜公園内には、
東京都が管理・運営している『上野恩賜公園正岡子規記念球場』という子規の名前を冠にした草野球場があります。
現在、私たちがこうして野球を楽しむことができるのも、子規ら先人たちの苦労や活躍があってこそなのだと思うと非常に感慨深いですね。