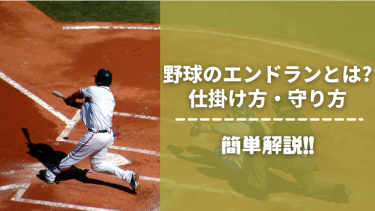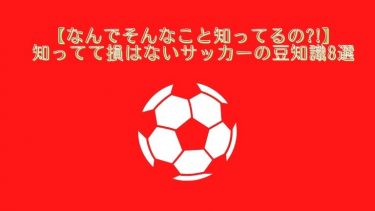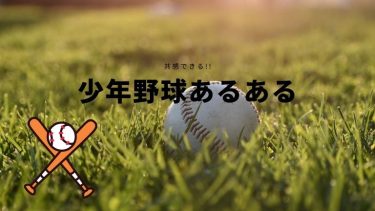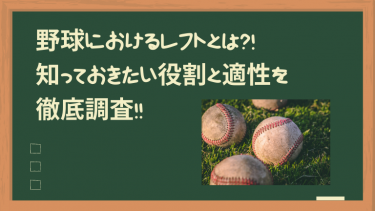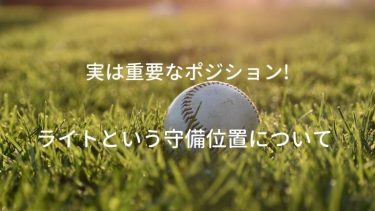野球は失敗のスポーツといわれます。
特に打者は3割打てば好打者といわれるように、7割は失敗しているという現実があります。
はたから見たら空振りは失敗にうつるかもしれませんが、実際のところ、空振りは一概に失敗とはいえません。
具体例をみることで、野球の見方が少し変わるかもしれません。
空振りによって生じる効果

空振りは一概に失敗ではないとお伝えしました。
その理由は、空振りによって生じるプラスの効果がいくつかあるためです。
打ち損じを無くす
空振りをすることで、打ち損じを無くすことができます。
どういうことかというと、バッターが難しい球に手を出して、かろうじてバットに当てたような打球は、往々にして打ち損じとなり、アウトとなります。
バットを振ろうとしたけど、難しい球がきた場合、思い切って空振りをすると、ワンストライクは相手に献上することになりますが、
次の球で勝負することができるため、結果的にプラスになる可能性があります。
当然、ツーストライクの場合は、三振となってしまうので、このケースには該当しません。
盗塁のサポートができる
これは、故意に空振りをするパターンと、結果的に空振りとなったパターン、両方があります。
塁上のランナーが盗塁をする際、バッターが空振りをすると、キャッチャーが送球をしにくくなります。結果として、盗塁のサポートになるケースがあります。
絶対に盗塁を成功させたいような場面では、故意に空振りをするように命じるサインも出ます。
バッターとしてはボール球が来ても空振りをすることで、ワンストライクを相手に与えてしまい、
打席での勝負は不利になりますが、チームプレーとして、このようなプレーが求められることがあるのです。
相手の守備位置を変える可能性
強い空振りをすることで、相手の守備位置を変える可能性があります。
守備をしている内野手が想像していたよりも、バッターが強い空振りをしたら、守備位置を一歩後退させるかもしれません。
それによって、ボテボテのゴロがヒットになる可能性もでてきます。野球はゴロを打った際、1塁ベースでのアウト、
セーフのタイミングが際どいことがよくあります。
強いスイングで守備陣形を少し後ろに下がらせたことが、次の結果を変える可能性があるのです。
このように、空振りにもプラスの側面があることが分かりました。
それでは、三振の場合、【空振り三振】と【見逃し三振】が与える影響はどのように違うのか解説します。
【空振り三振】と【見逃し三振】の違いについて

三振をすれば、ワンアウトを相手に献上するという点で、【空振り三振】と【見逃し三振】は同じです。
しかし、同じアウトでも、両者は似て非なるものです。
空振り三振は後悔しにくい失敗
特にアマチュア野球の世界では「見逃し三振ではなく、空振り三振をしましょう」という事が言われます。これは、空振り三振が後悔しにくい失敗だという理由からです。
例えば、高校野球の3年生が最後の引退試合で、見逃し三振でゲームセットになってしまったことを想像したら、その選手が後悔することは容易に想像できます。
空振り三振だったら後悔しないかというと、そうは言いきれませんが、『見逃し三振=受動的』『空振り三振=能動的』という点から、
積極的に振った結果の三振ということがいえるので、見逃し三振より後悔は少ないでしょう。
また、少年野球では空振り三振したら、指導者から怒られることを恐れて、委縮して見逃し三振をする選手もいます。
指導者は、選手が積極的にスイングできる環境を作ることが大切です。
相手投手への恐怖心を植え付ける
空振り三振をするもう一つのプラス材料は、相手投手に対する恐怖心を植え付けることができるという点があげられます。
バッターが三振した場合、見逃し三振の場合は、投手の完勝というイメージが強いため、ピッチャーの中には良い印象だけが残るでしょう。
しかし、バッターがものすごいスイングで三振した場合は、『もしもバットに当たっていたら危なかった…』というような気持が沸き上がる可能性があります。
その結果、次の打席で、ピッチャーは配球に気を使ったりすることで、心理的にプレッシャーをかけられる可能性があるのです。
三振をするなら【見逃し三振】よりも【空振り三振】の方が良いという点を紹介しました。
しかし、そうは言っても「空振りはしたくない」というバッターが圧倒的ですので、空振りの減らし方について見ていきます。
空振りを減らすためには?

コンタクト率を上げる
空振りを減らすには、コンタクト率を上げるという事が一番重要です。要は、ボールにバットを当てる技術を上達させるという事です。
これができたら苦労しないという声がたくさんありそうですが、練習によって上達させるしか方法はありません。
バッティングの練習は、
- マシンを使った練習
- ティーバッティング
- トスバッティング
- 実践形式
など、さまざまな方法があります。練習をこなすことでコンタクト率は上がりますので、自分に合った練習を見つけましょう。
また、自分のバッティングフォームがコンタクト率を下げる原因になっているケースもありますので、監督、コーチに意見をもらうのも良いでしょう。
動体視力を強化する
バッターの仕事は、早く動く球を打つことです。
これをミスせずバットに当てるには、動体視力がいかにしっかりしているかが重要です。
川上哲治氏の「ボールが止まって見える」というフレーズは有名ですが、これは動体視力が極限に高められていたからこそ出てきた言葉なのでしょう。
人間は年を取ると動体視力が低下します。
プロ野球選手も30代を迎えると、徐々に動体視力が低下していき、今まで対応できていたボールに全く対応できなくなってしまうというケースもあります。
年齢とともに落ちた動体視力を回復させるのはなかなか至難の業ですが、
今では様々なトレーニング方法がありますので、若いうちから動体視力を強化することで、その劣化を抑えることができるでしょう。
まとめ

今回は、野球における『空振り』について深掘りしてみました。
一般的には、空振りという言葉は、イメージはあまり良くないかもしれません。
しかし、野球において、空振りが試合や個人にもたらす影響が様々あることをお伝えしました。
単純なマイナスイメージから、空振りがもたらすプラスの要因があるという点にも注目して、野球を見るのも楽しいかもしれません。