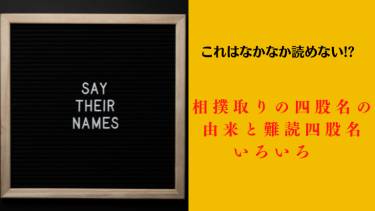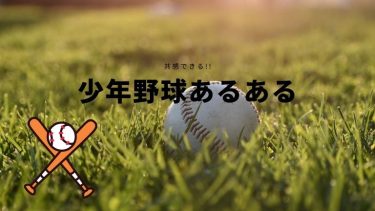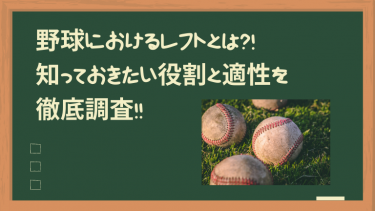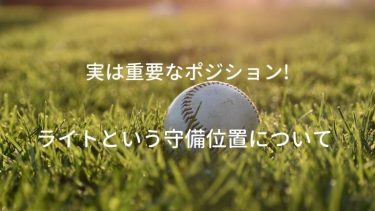ここ数年の高校野球人気は今までにも増して、凄く高まっています。
「高校野球って、ただの高校生の部活じゃないの??」
そう思われる方もいるかもしれませんが、日本における高校野球はものすごく歴史の長いスポーツであり、振り返ってみると人気の理由が分かります。
高校野球の歴史はいつ、どのようにスタートしたのか??

それでは高校野球の歴史について、そのスタート時点を探っていきましょう。
1915年、第一回大会がスタートしたのは、現在の会場となっている甲子園球場(正式名称:阪神甲子園球場)ではなく、大阪の豊中グラウンドでした。
当時甲子園球場はまだ誕生していません。
第一回大会の名称は第1回全国中等学校優勝野球大会。現在の全国高等学校野球選手権大会(いわゆる夏の甲子園)にあたる大会です。
当時の出場校は10校で、第一回大会の優勝校は京都代表、京都二中でした。
ちなみに、大会名も全国中等学校優勝野球大会という名前で、優勝校も京都二中です。
中学生の大会と勘違いしてしまいそうですが、当時の中学というのは、現在の高校にあたるものでしたので、このような名称となっています。
その後の第2回~第9回大会で他球場での開催を経て、現在の甲子園球場で大会が開催されるのは1924年の第10回大会からです。
高校野球の歴史を語る上で、甲子園球場の存在は外すことはできません。
甲子園球場が建設された要因としては、高校野球人気に火がつき、いわゆる小さい地方球場では客が入りきらなくなってしまったからです。
球場を建設するところまでいってしまうことからも、当時からすごい人気だったことがうかがえます。
当時は甲子園大運動場という名称であり、野球以外でもさまざまなスポーツを行う場所でした。
例えば、バスケットや水泳、冬のスキージャンプまで行われていた万能な施設だったのです。
甲子園球場の大きさを物語るエピソードとして、ベーブルースの言葉があります。
当時アメリカから日米野球で訪れたスーパースター、ベーブルースはあまりの大きさに「too large(大きすぎる!)」と感嘆したと言われています。
このように誕生した甲子園球場を舞台に、1924年の第10回大会から高校野球の熱戦が繰り広げられることとなりました。
ちなみに、現在の選抜高等学校野球大会(いわゆる春の甲子園)は、1924年に第1回大会がスタートし、翌1925年の第2回大会から甲子園球場を舞台にしています。
高校野球で歴史上もっとも強い都道府県はどこ??

1915年から100年以上の歴史を持つ高校野球ですが、歴史上最も優勝している都道府県はどこなのか?
夏の大会、101回大会(2019年)までの優勝校を元に優勝している都道府県ランキングを作成してみます。
春の大会は、全都道府県が出場しないので、このランキングでは反映していません。
第2位(8回)・・・愛知
第3位(7回)・・・東京、神奈川、兵庫、和歌山、広島
第4位(6回)・・・愛媛
第5位(4回)・・・京都、福岡
第6位(3回)・・・千葉
第7位(2回)・・・北海道、茨城、栃木、群馬、奈良、香川、高知、佐賀
第8位(1回)・・・埼玉、長野、岐阜、静岡、三重、山口、徳島、大分、沖縄
高校野球の歴史的名勝負をピックアップ
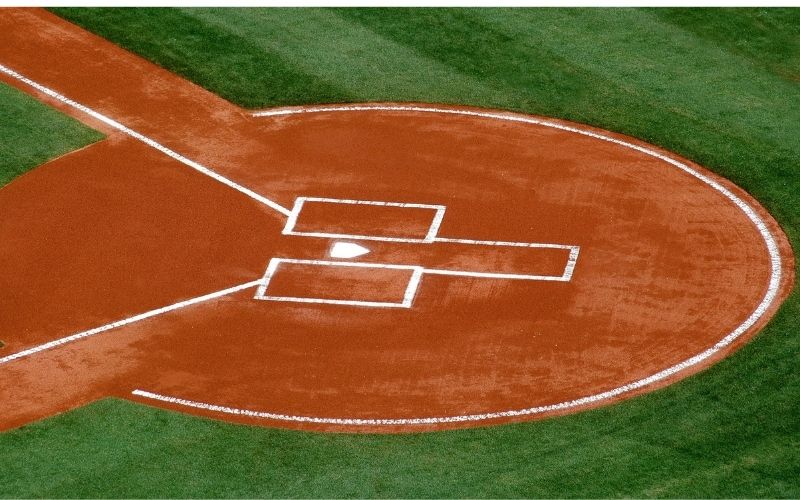
1996年 第78回 決勝 松山商業(愛媛) 6 – 3 熊本工業(熊本)
第78回、夏の高校野球決勝は古豪同士のカードでした。
9回裏に1点ビハインドで負けていた熊本工業ですが、2アウトから1年生澤村の起死回生のホームランで3-3の同点に追いつきます。
続く10回裏、勢いに乗る熊本工業は、1アウト満塁でサヨナラの大チャンス。この場面で、守備側、松山商業の監督は、ライトを矢野選手に交代します。
交代直後の1球、代わった矢野選手の元へ、大飛球が飛びます。見ていた誰もが熊本工業のサヨナラ勝利は間違いないという大飛球でしたが、
キャッチした矢野選手は、ノーバウンドの送球をホームにストライク返球し、見事にタッチアップのランナーを刺しました。
試合終了と思われたところから生き返った松山商業は11回表に3点を奪い、6-3でゲームセット。
信じられないこのプレーは、今なお『奇跡のバックホーム』として語り継がれています。
2006年 第88回 決勝
【1日目】 早稲田実業(西東京) 1 – 1 駒大苫小牧(南北海道)
【2日目】 早稲田実業(西東京) 4 – 3 駒大苫小牧(南北海道)
まとめ
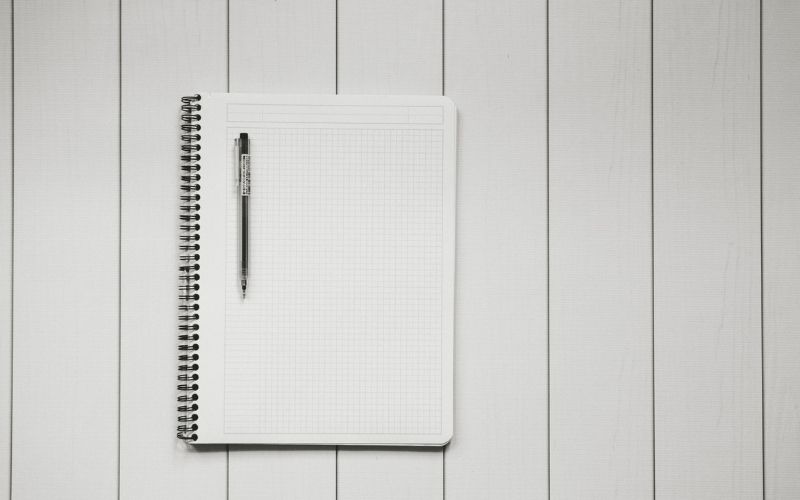
いかがだったでしょうか。
高校野球の歴史、これだけ長い歴史なので、紹介しきれない名勝負も本当にまだまだあります。
負けたらそこで終わる、という緊張感の中、全力で戦う球児たちの頑張りに、私たちは心打たれます。
今後も後世に語り継がれる名勝負が甲子園球場で繰り広げられることを楽しみにしながら、高校野球を楽しみましょう。